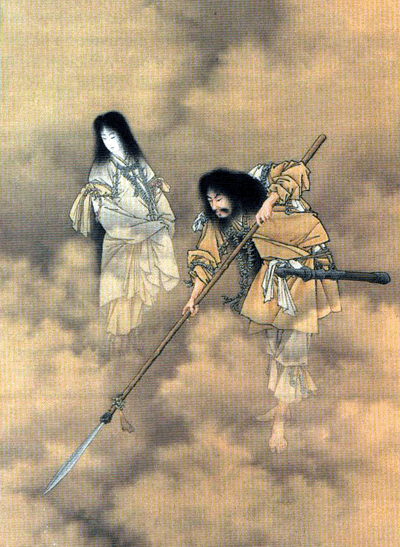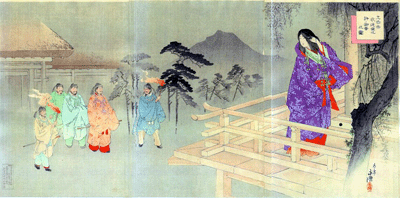蒲原
小林永濯 その2 小林永濯(こばやしえいたく)は、1843年(天保14年)の生まれで、江戸は日本橋の魚問屋のせがれで、名は秀太郎。13歳で狩野永悳(かのうえいとく)に弟子入りしたそうです。彼の号である鮮斉(せんさい)というのは、鮮魚を扱う家の出身だということかもしれません。 しかし、狩野派としての正統的な絵をかくのではなく、いささか意表をついた画風が彼の本領。ボストン美術館所蔵で、去年日本でも公開された「道真天拝祈祷の図」は、これが日本画か!とまさしくぶっとぶ絵柄で、ポスターになっているのを見て、なんじゃこりゃ! と思った人も多いはず。 しかも、この絵柄は、月岡芳年の道真図と場面がよく似ていて、芳年の場合は、命と引き換えに復讐を誓うために天上に竹に刺した願文を差し上げている「激情の道真」を描いているのですが(まことに、つたないながらも、芳年好きの私もこんなものを描きました)、小林永濯の場合は、まさに願いが天に届いて、「お前の命確かにもらった!」とでもいう天の声の、まさにその瞬間で、雷が落ちかかり、願文も竹串もふっとび、冠もすっ飛んで、身体に電流が走ったその場面を描いているのです。月岡芳年とは交流があった永濯ですから、芳年の絵を見て「わしは決定的瞬間を描くぞ!」と意気込んだのか、そこんところはわかりませんが、なかなかにスゴイ絵ではありませんか。 小林永濯 その1 イザナギ・イザナミのところでもちょこっとふれましたが、近頃気になっているのが、幕末明治に活躍した小林永濯(こばやしえいたく)という画家。 狩野派の狩野永悳(えいとく。とくは直の下に心)の弟子で、東京国立博物館にある「黄石公張良図」という絵があるのですが、この絵は、「日本の美術 明治の日本画」(至文堂)にも乗っていたので、ずいぶん、昔から知っていましたが、なにしろ、黄石公が石の幽霊みたいな爺さんだってのは、まあ、仙人だから許すとして、張良の姿が、あまりにも・・あまりにもひどすぎる・・・。これじゃあ張飛か李逵(この二人は、私の中ではもう同じキャラなのです)ではないか! 史記にだって「好婦の如き」容貌だと書かれているのに、これはないだろう! 古典も読んでなくて歴史画を書くなんて・・と一蹴していましたんです。しかし、ミョーに印象に残っていたのは確か。 しかし、調べてみると、黄石公と張良というのは、江戸時代から画題としてしばしば、取り上げられていて、根付や刀の鍔や馬具などにもなっているものだということがわかってきました。その場合、仙人黄石公に履を差し出す若い張良を描くというのが定番です。画家では、かの北斎や、曽我蕭白も描いています。ぶっ飛び画家の曽我蕭白にしても、張良は若い男に描いてある。それなのに・・・・小林永濯の、この肥満体のおっさんはなに? しかも、伝統的な画題ならば、橋で出会う若い張良と黄石公のエピソードのはず・・。 では、この絵には何か、画家なりの主張があるのか?