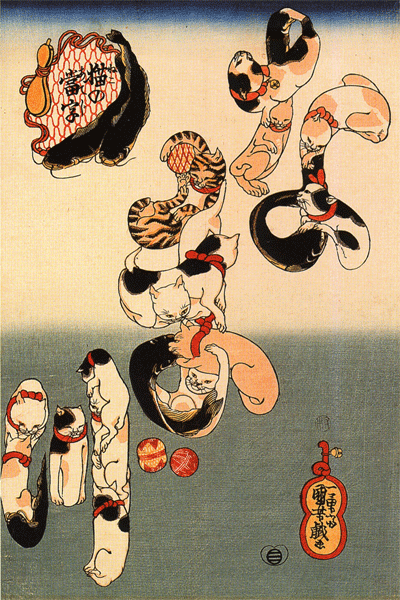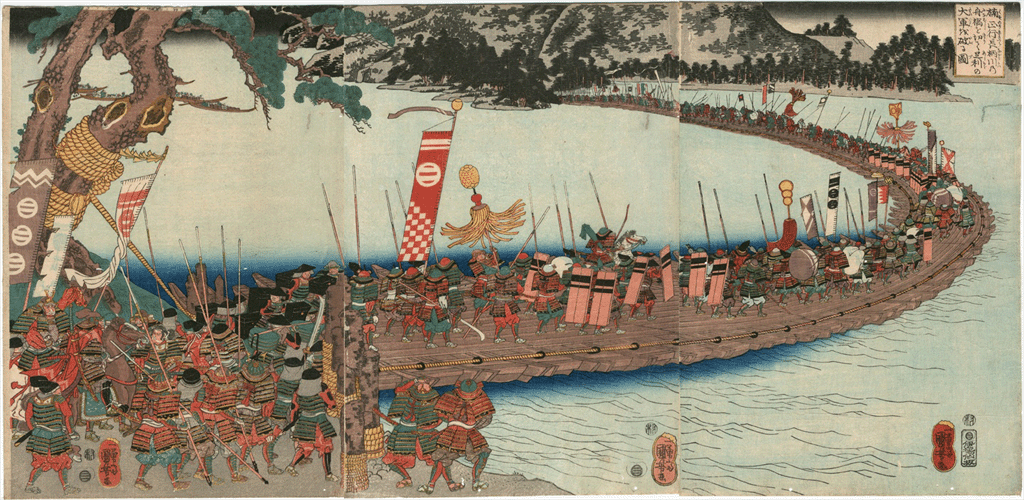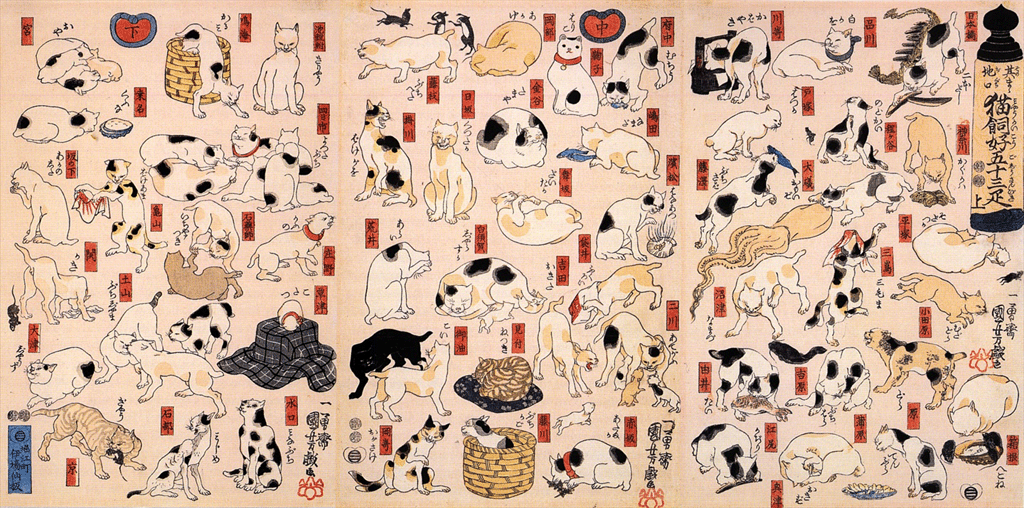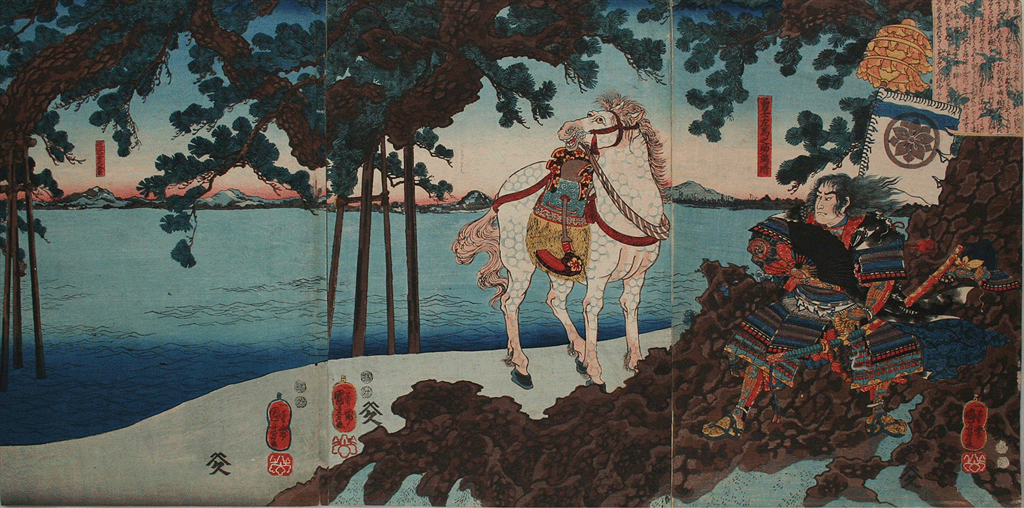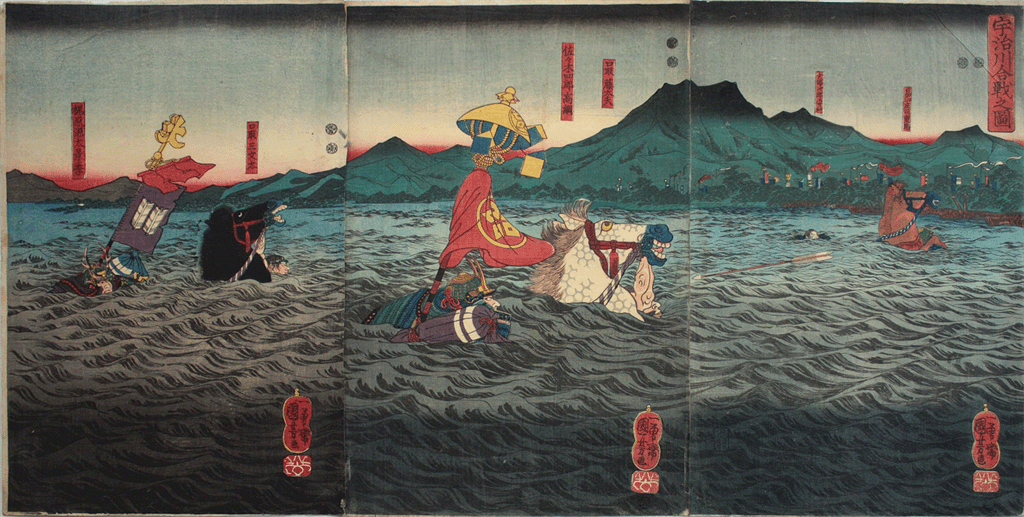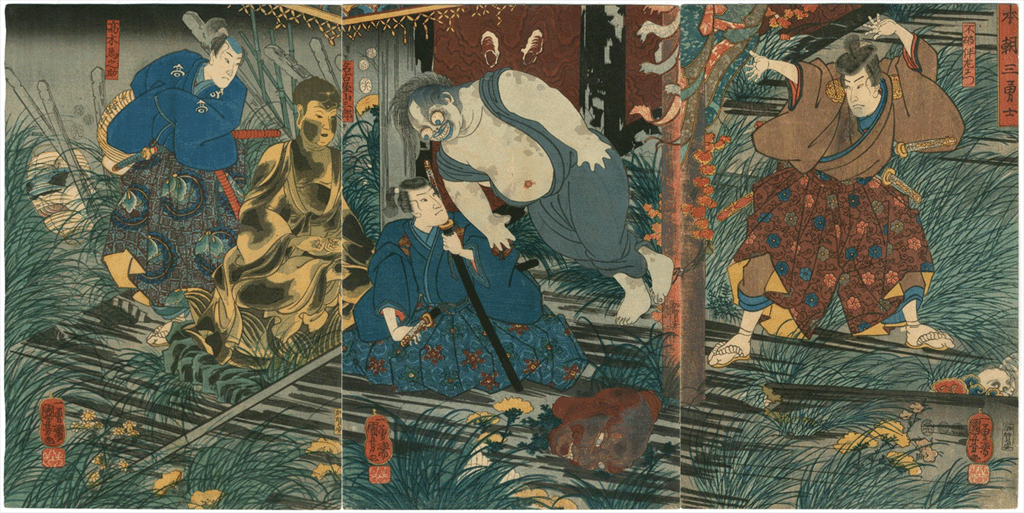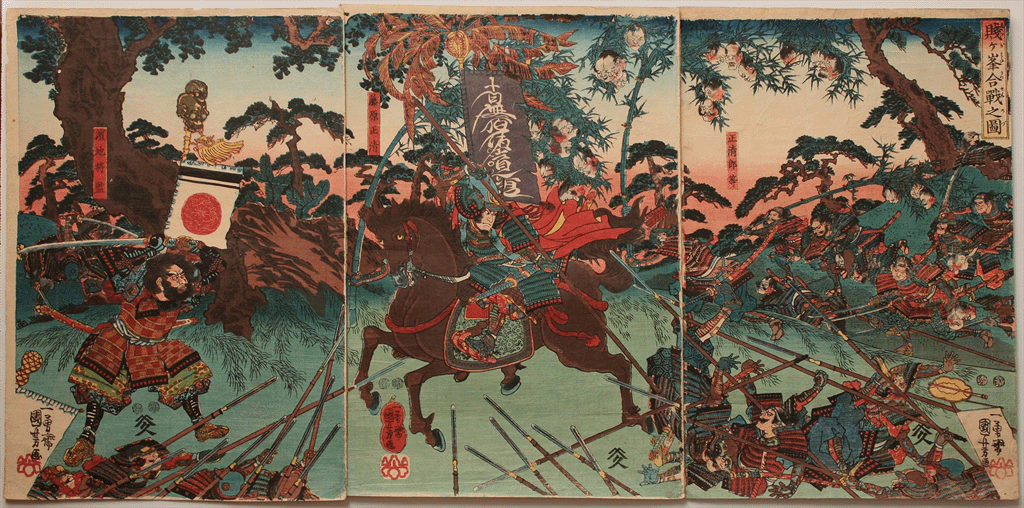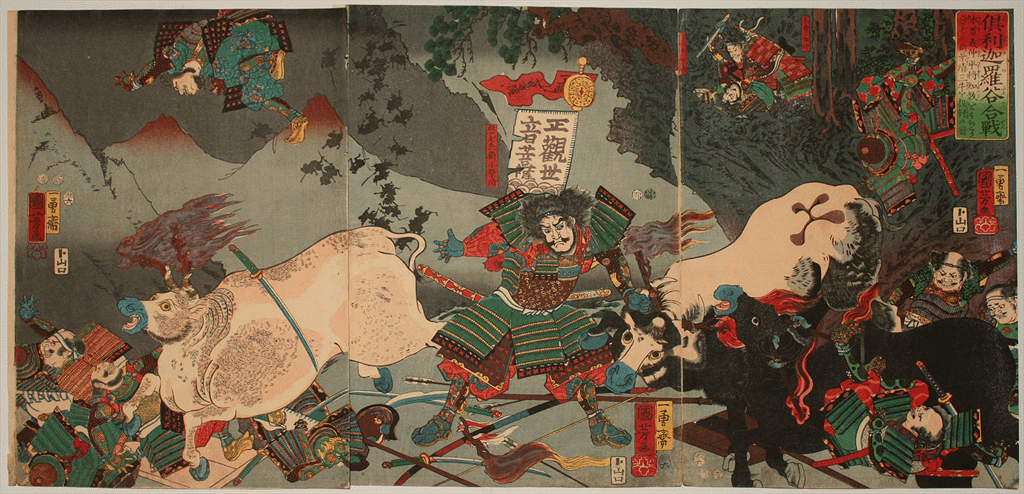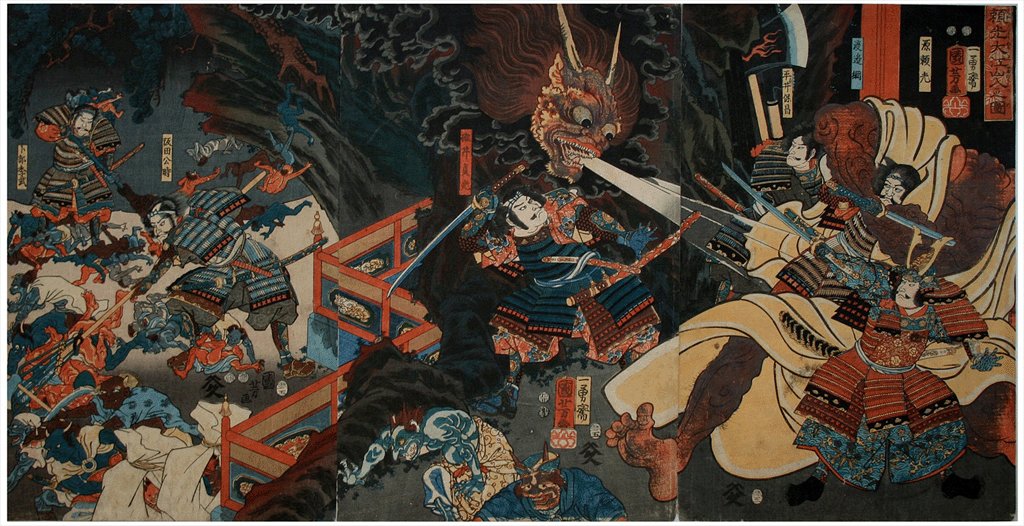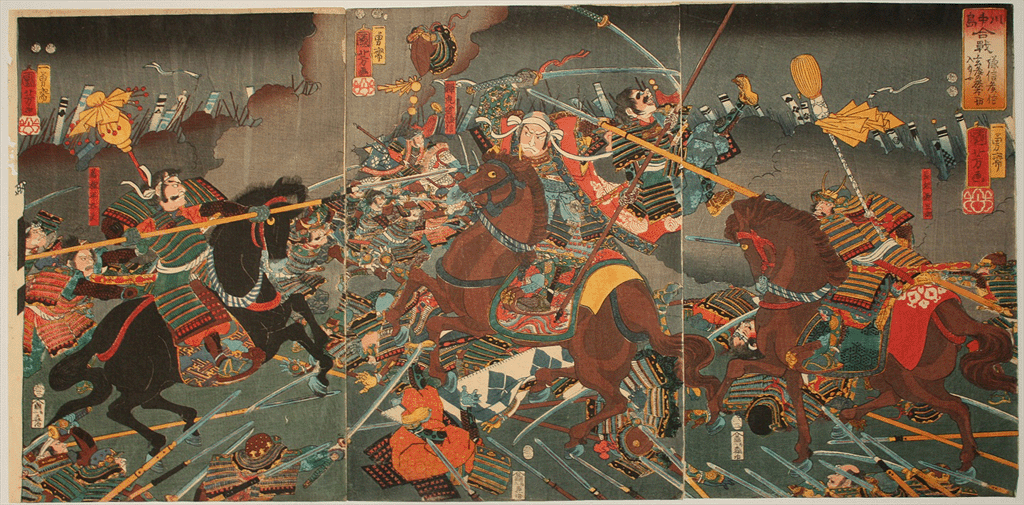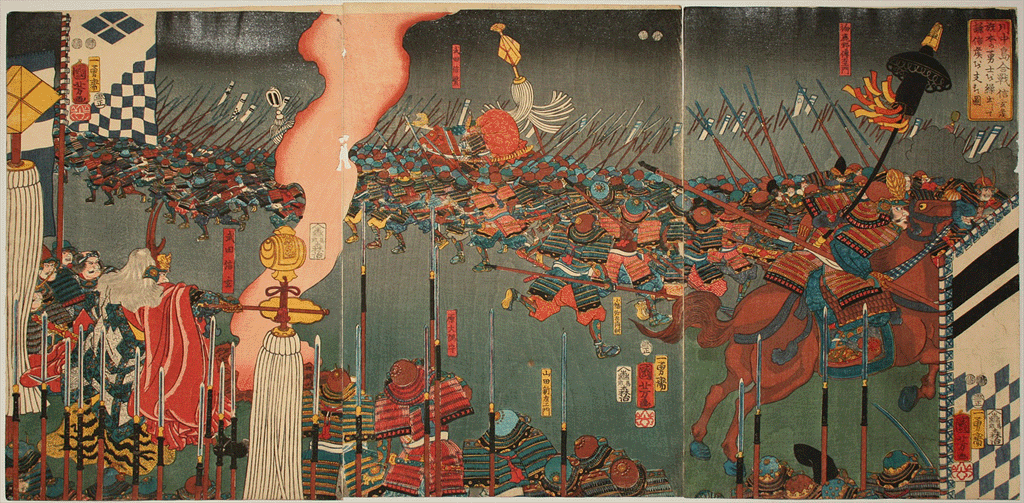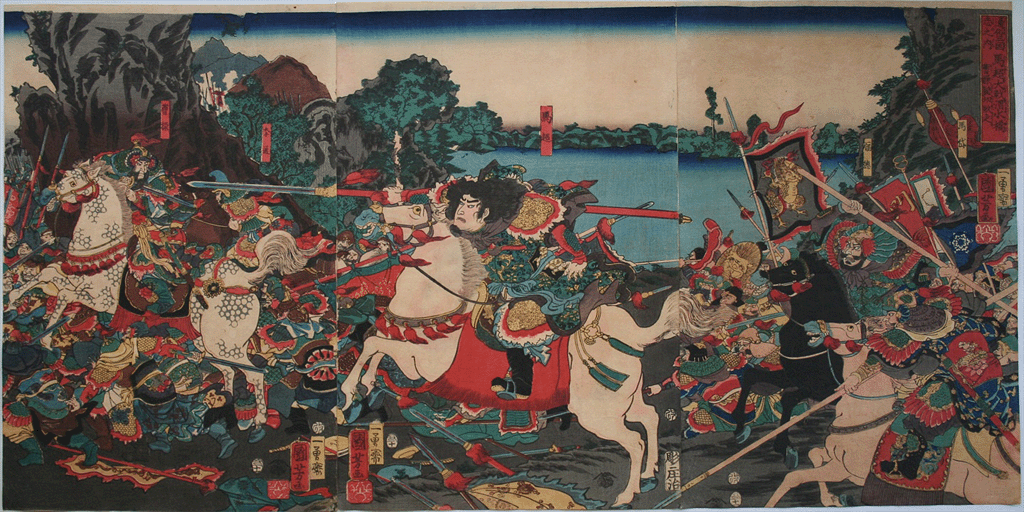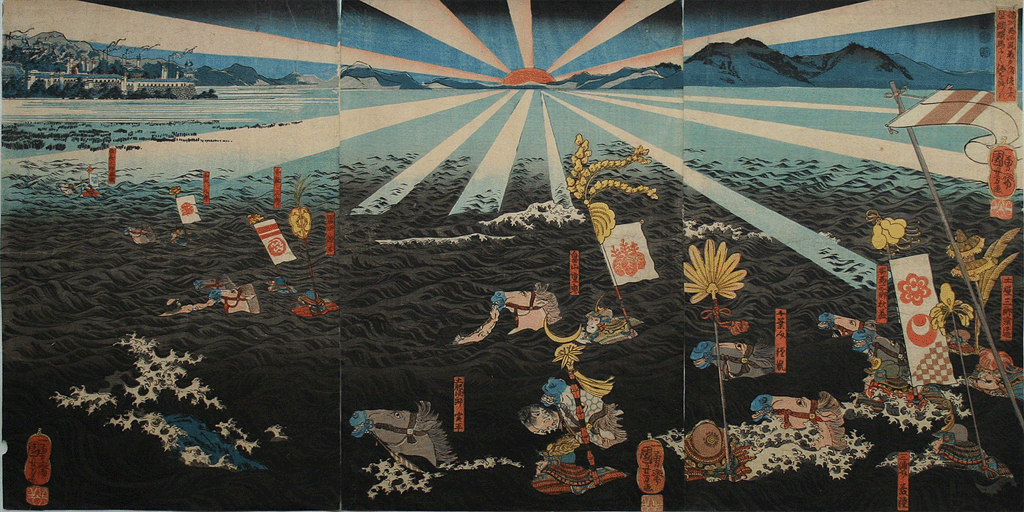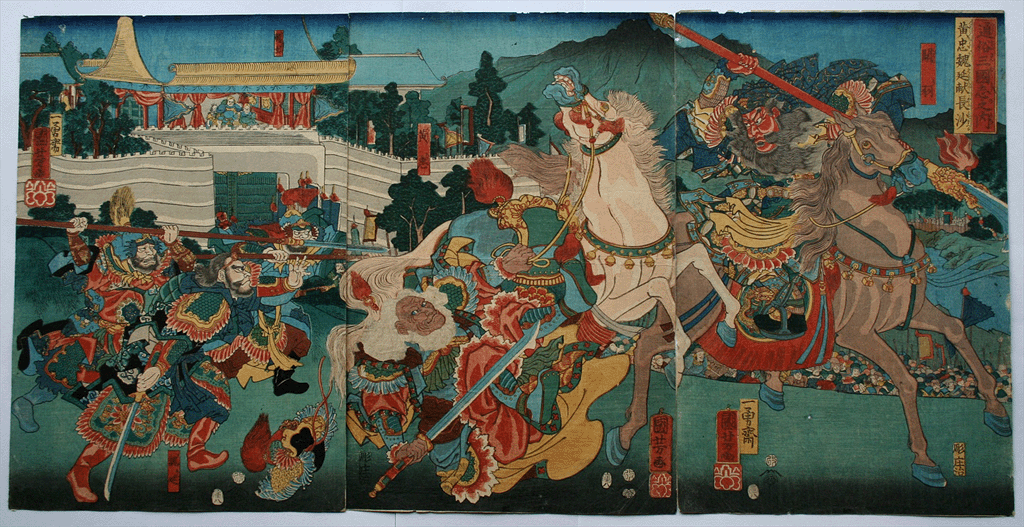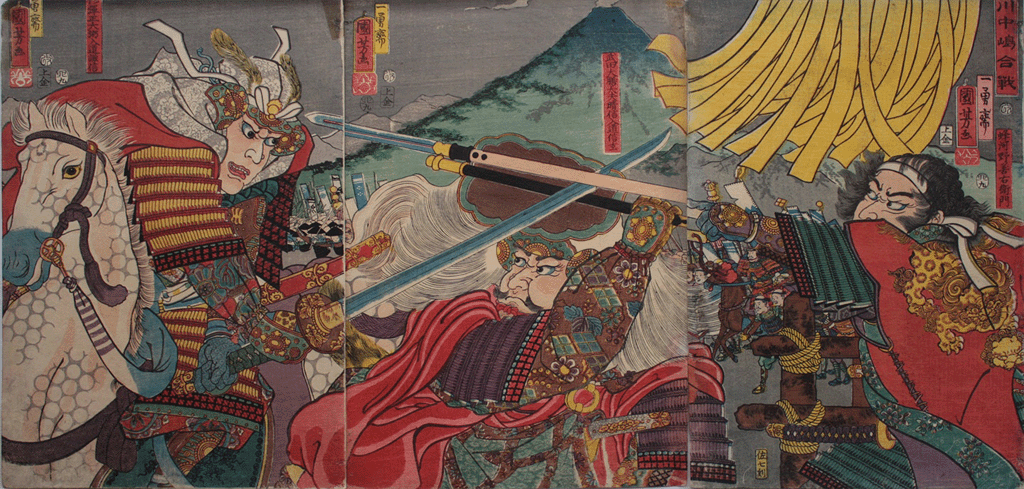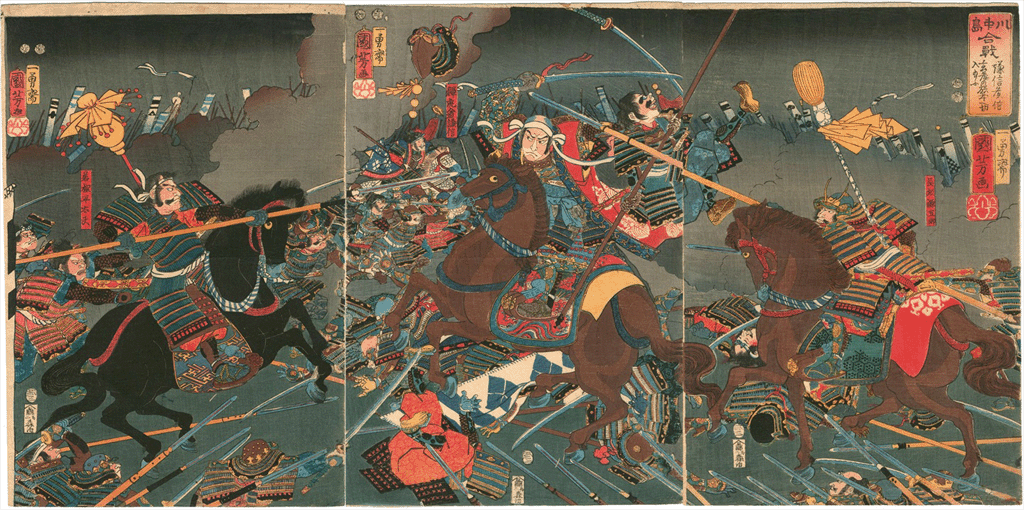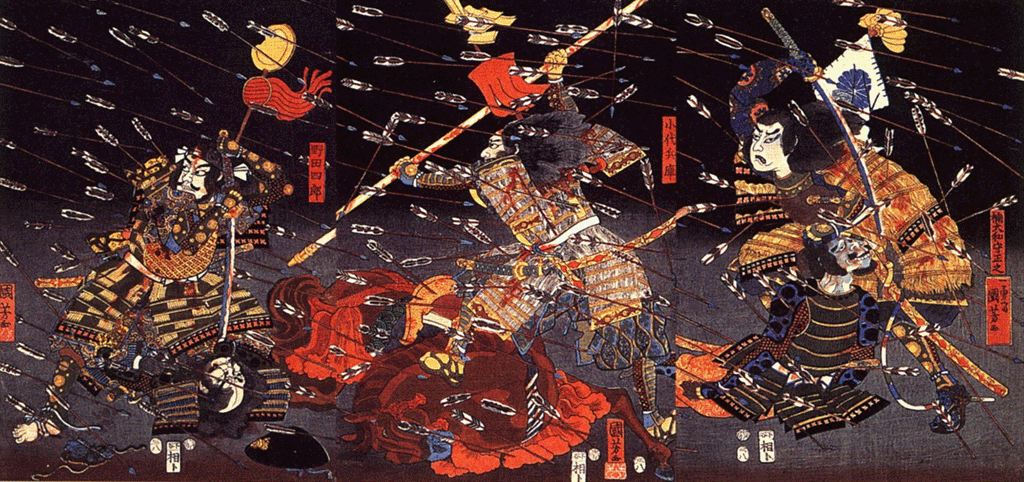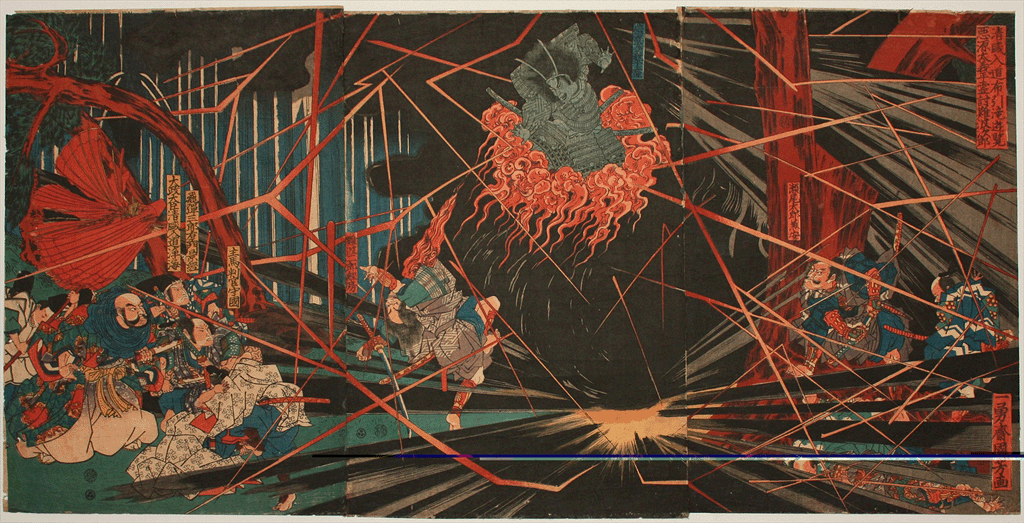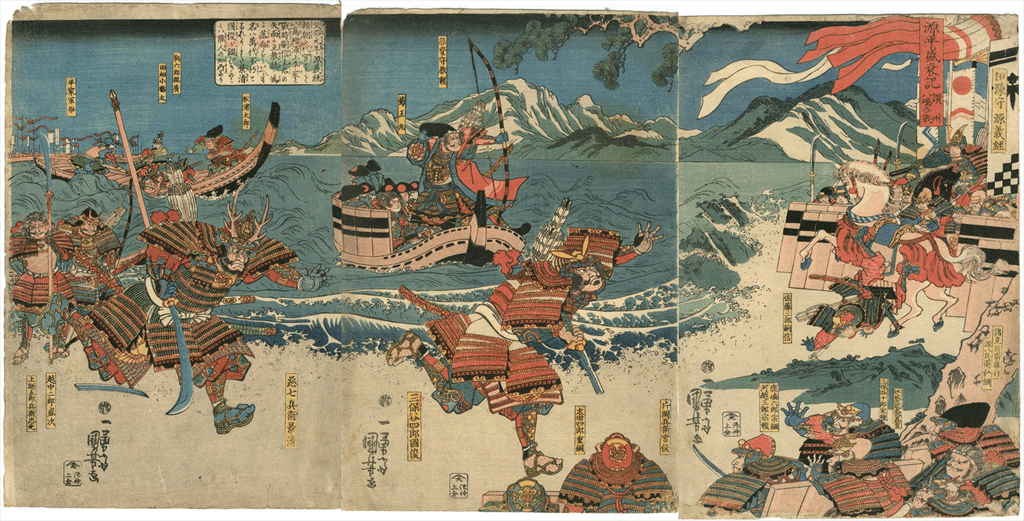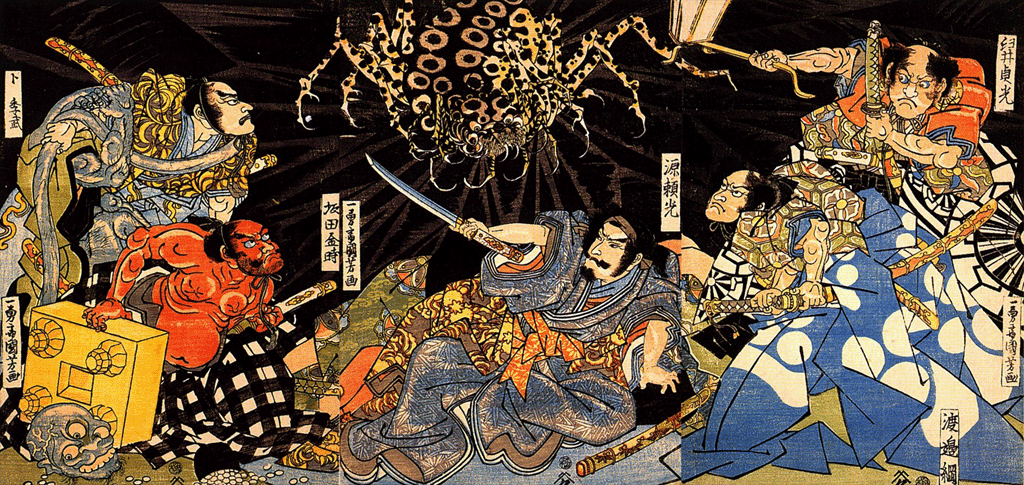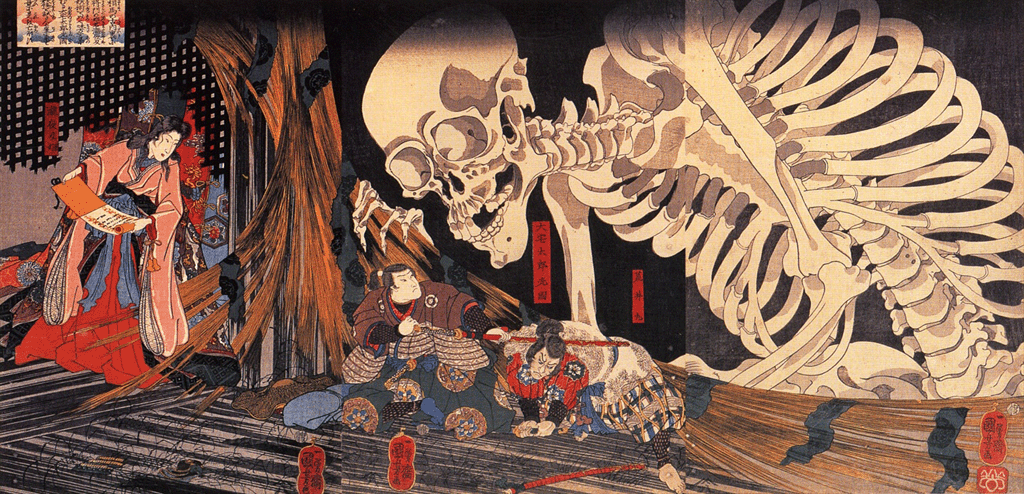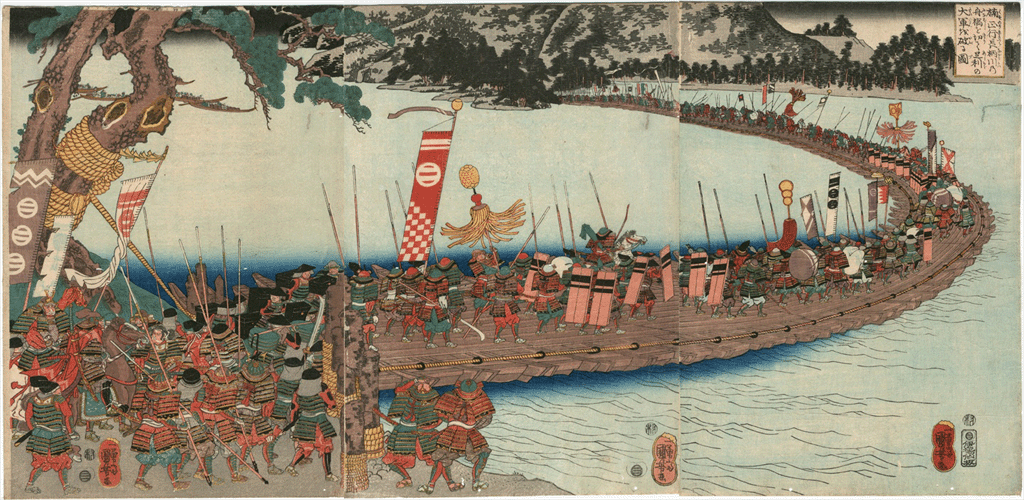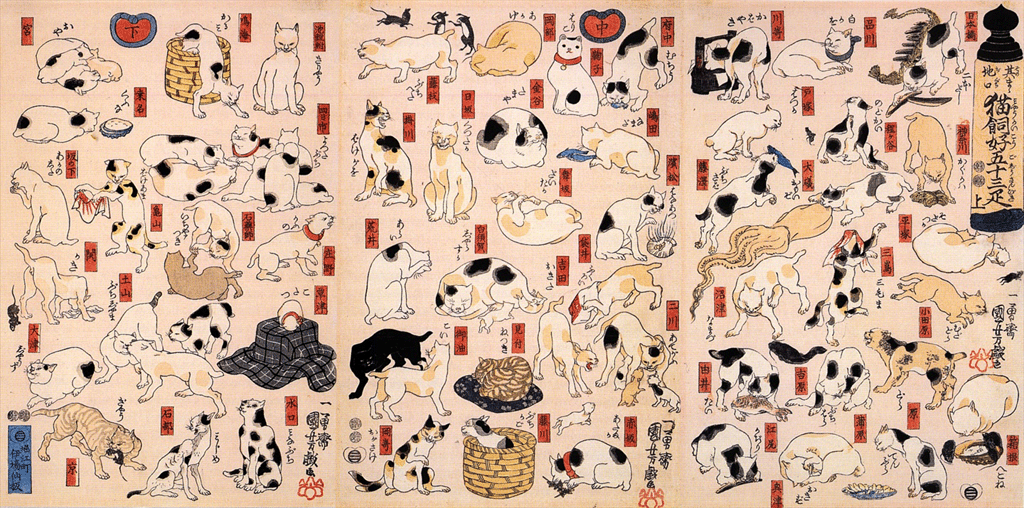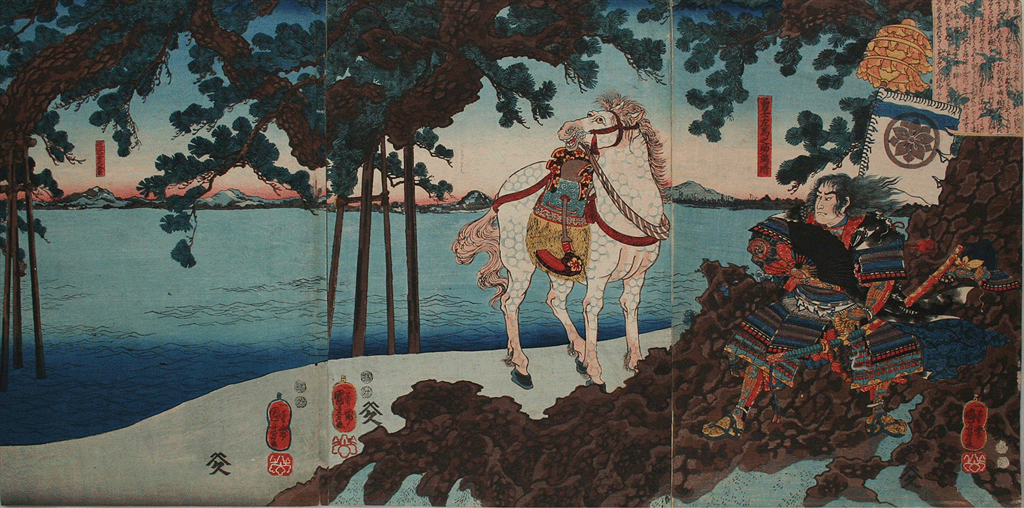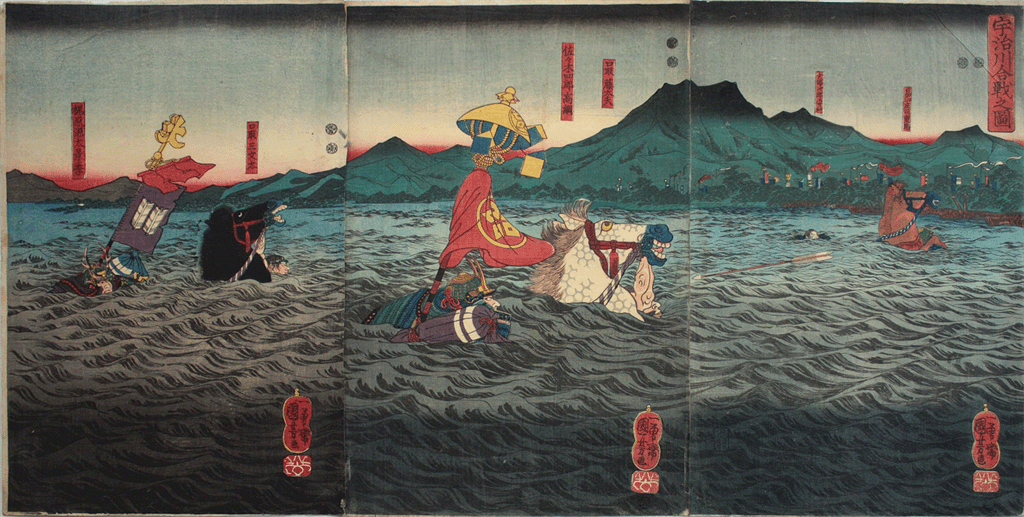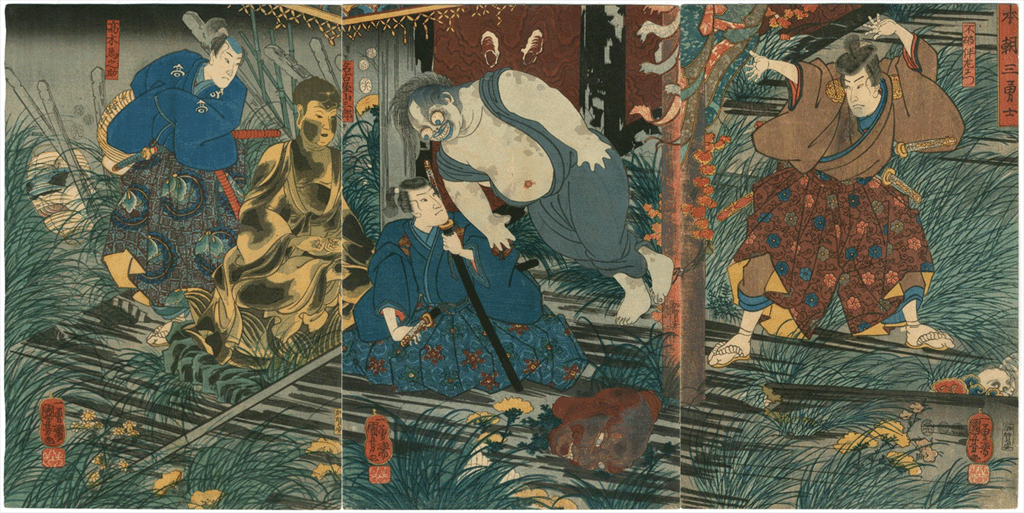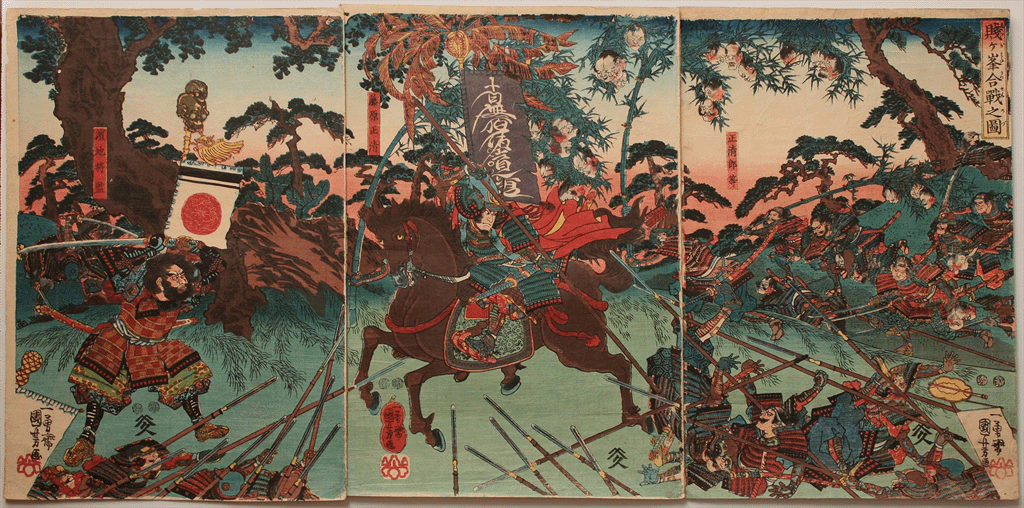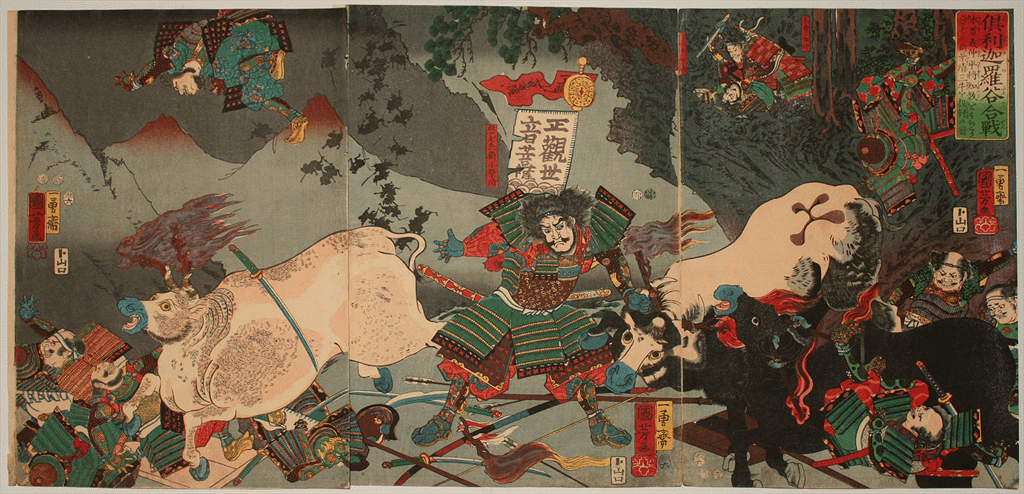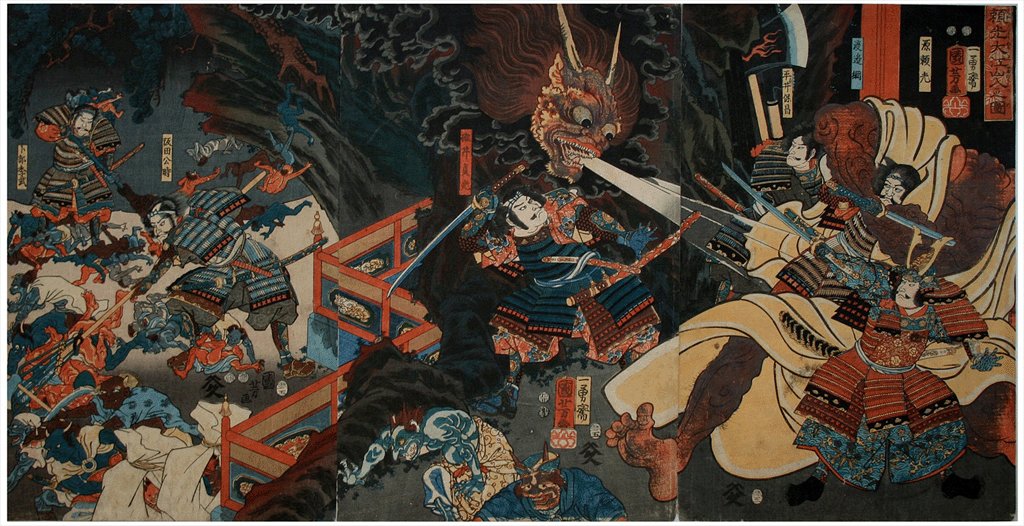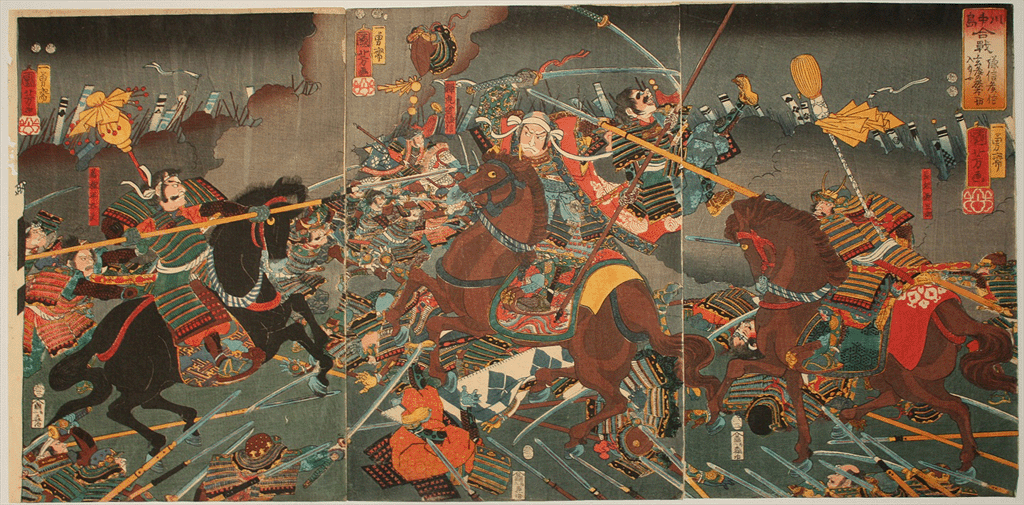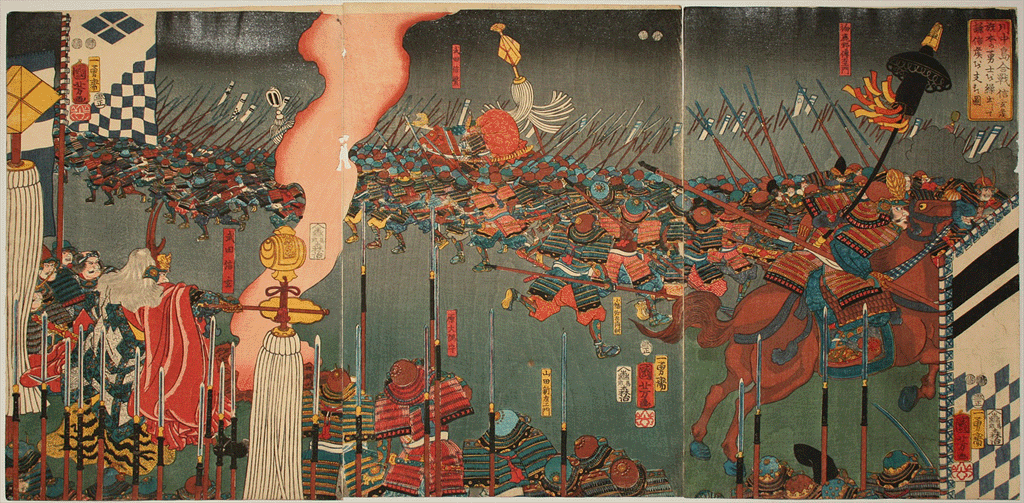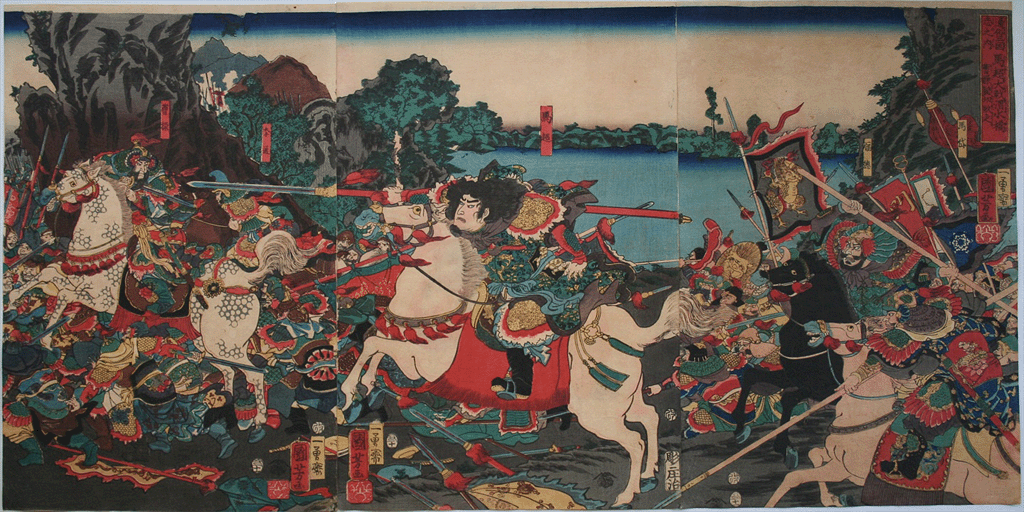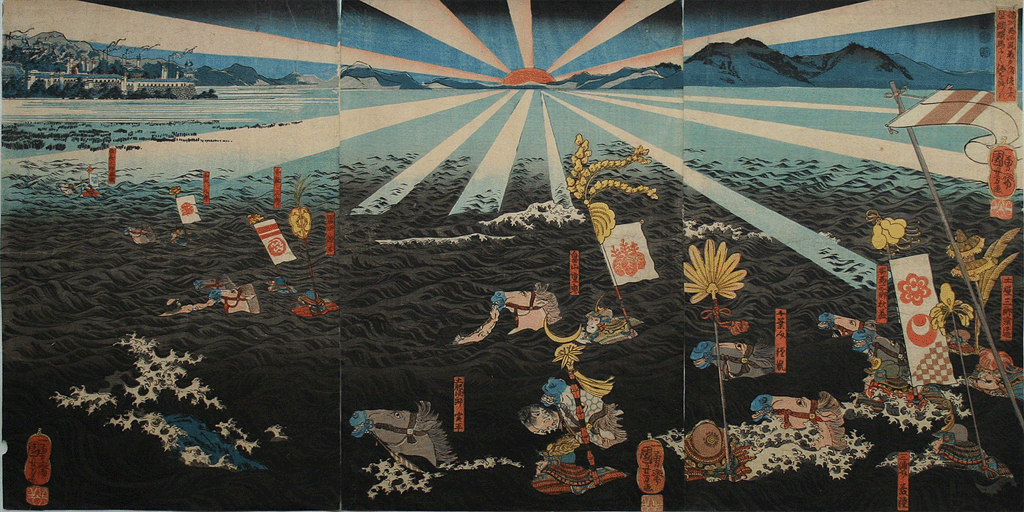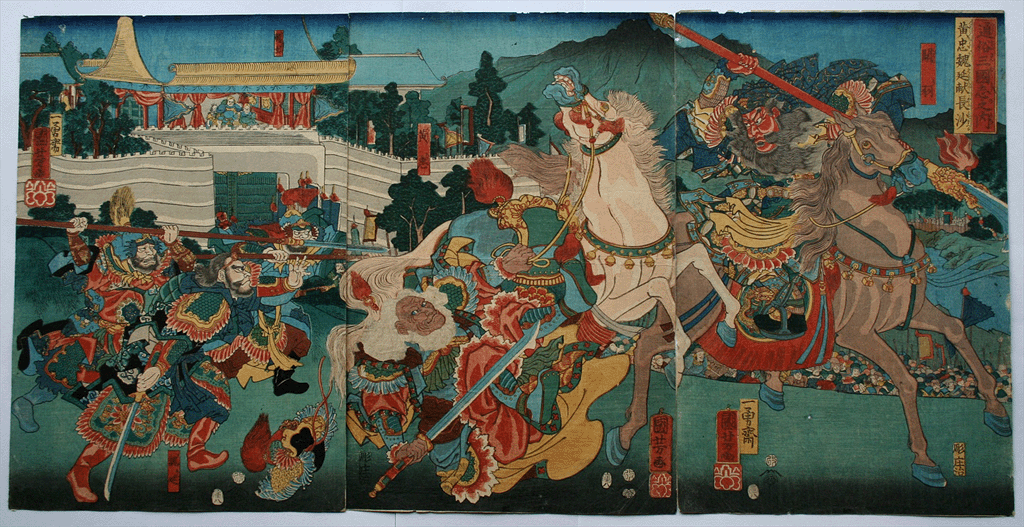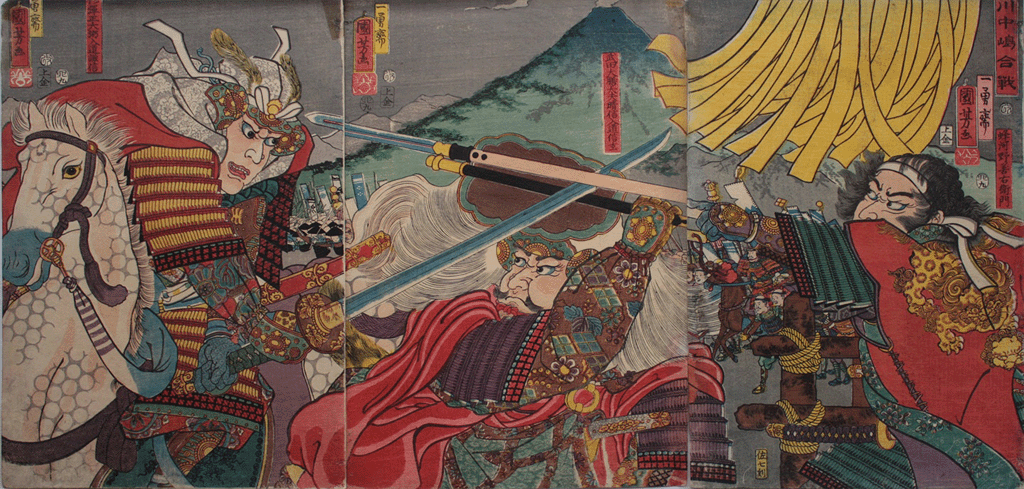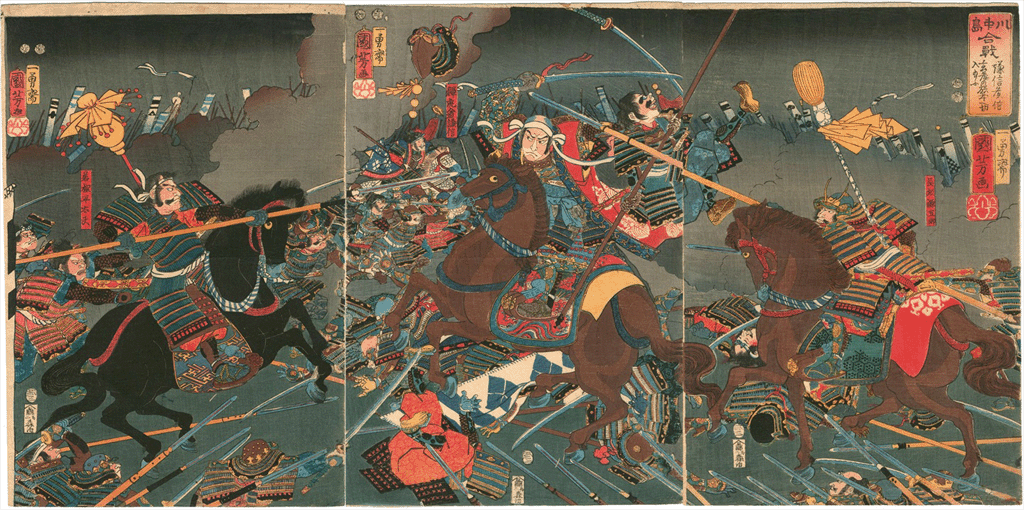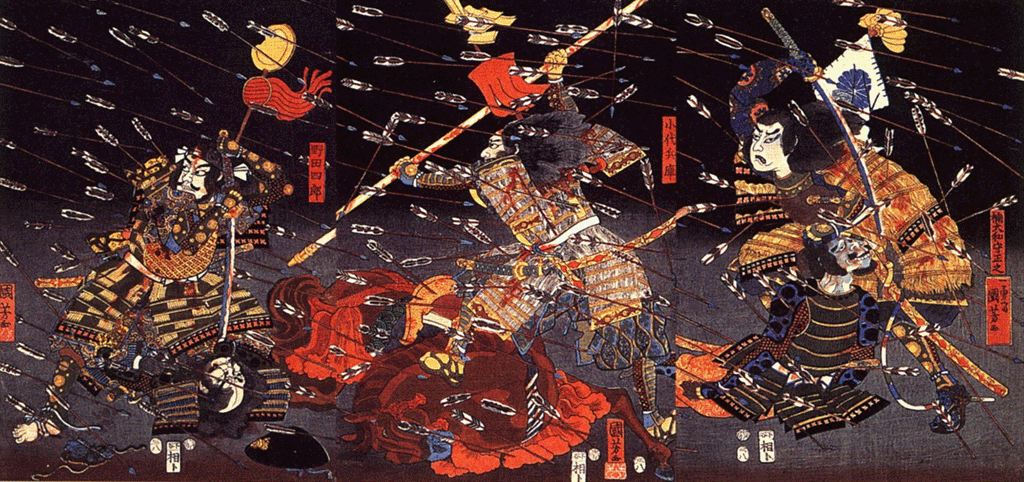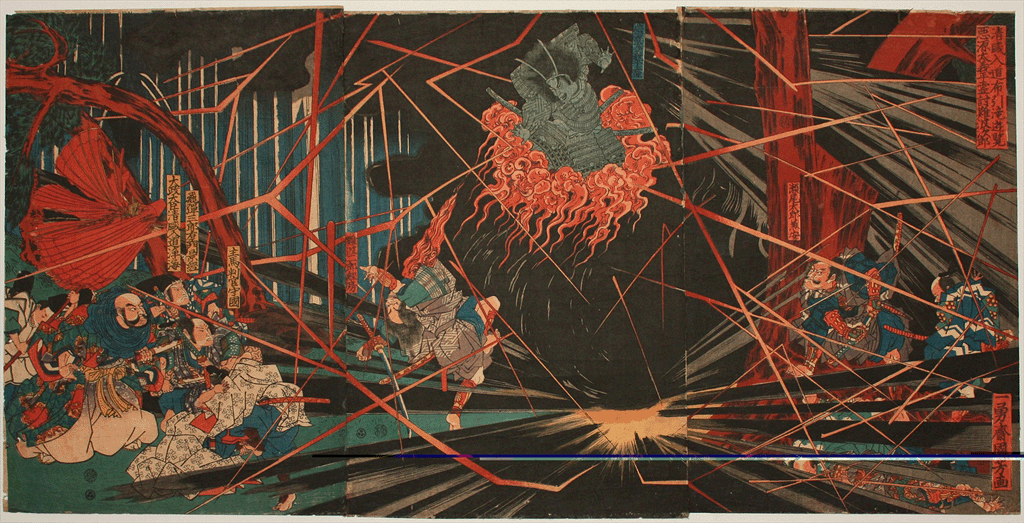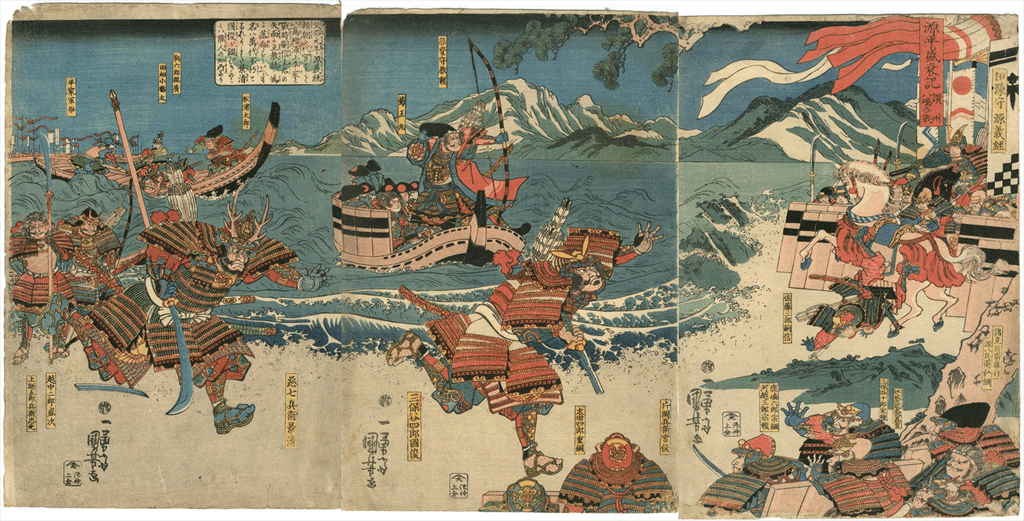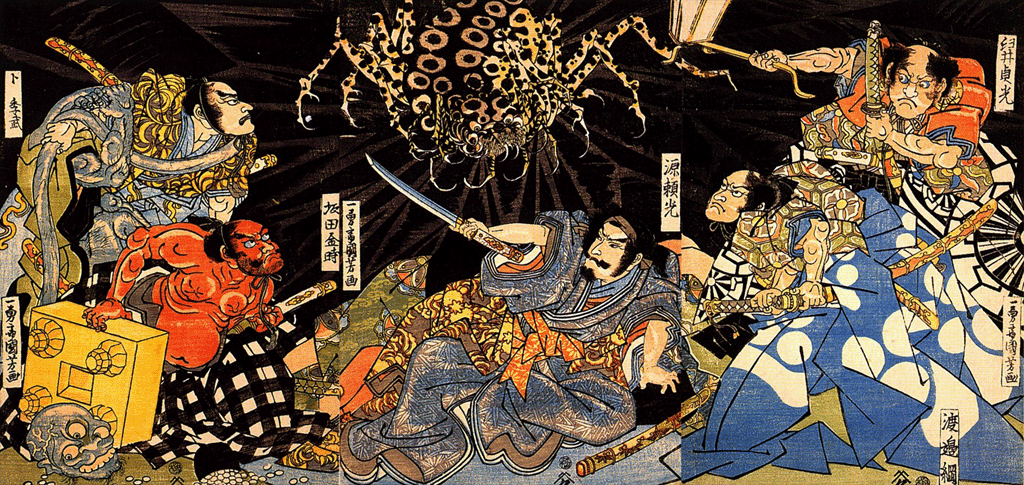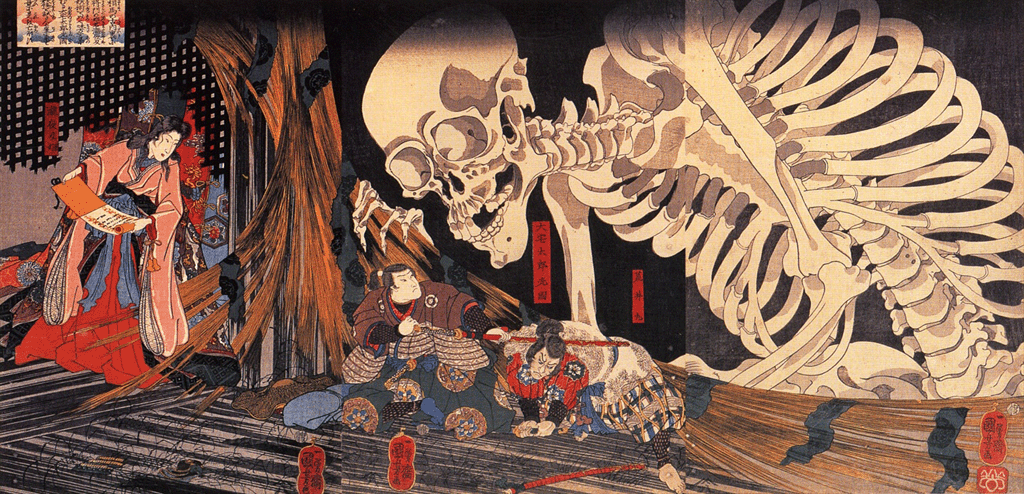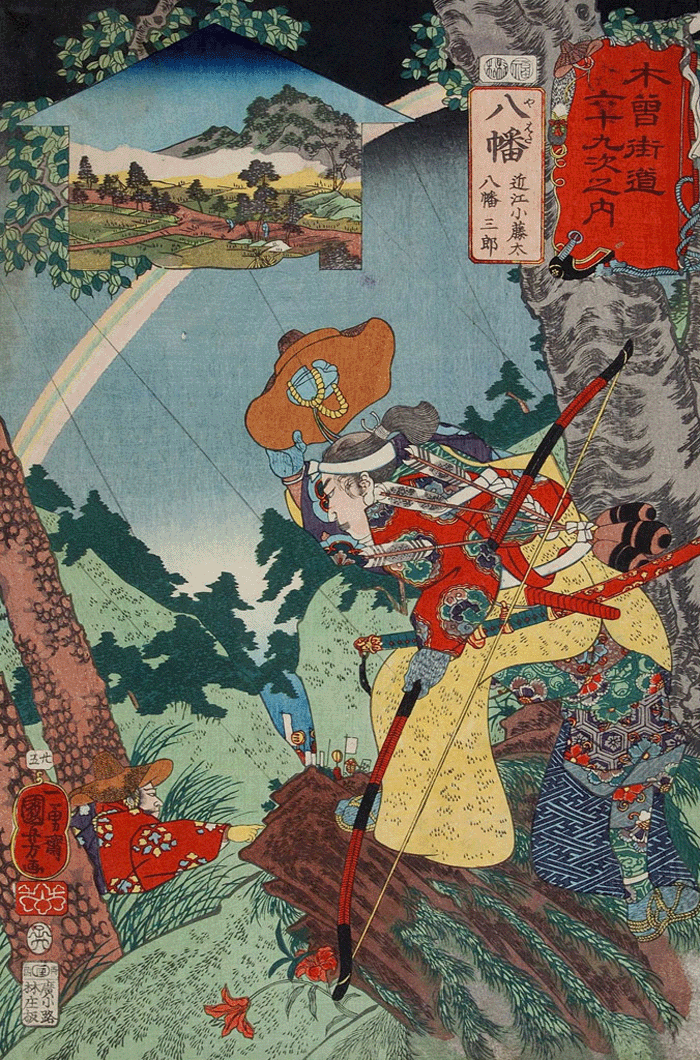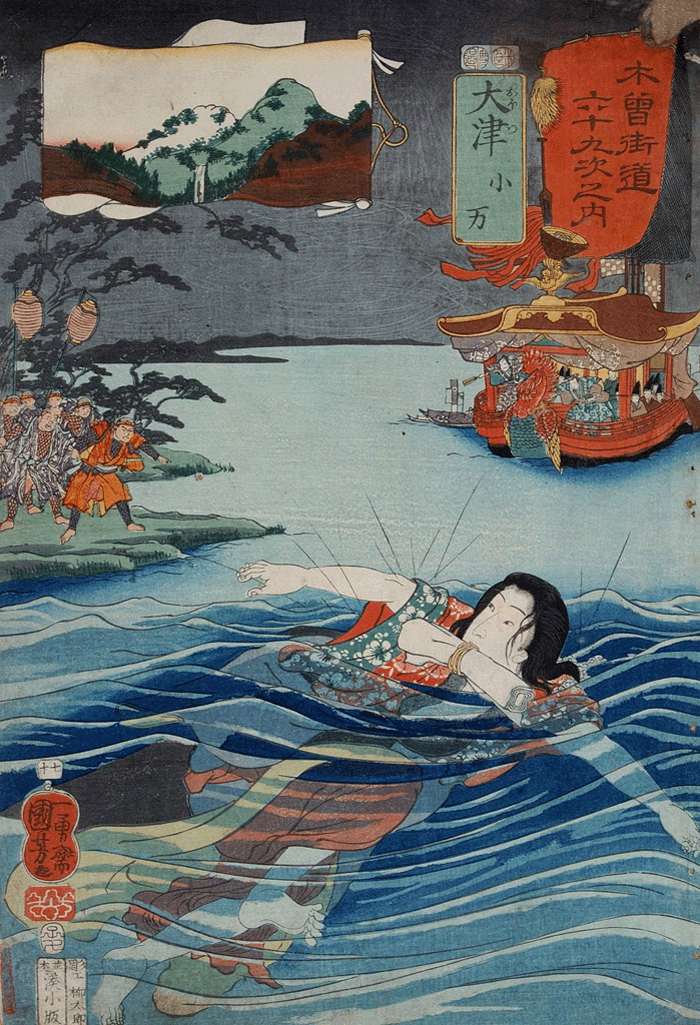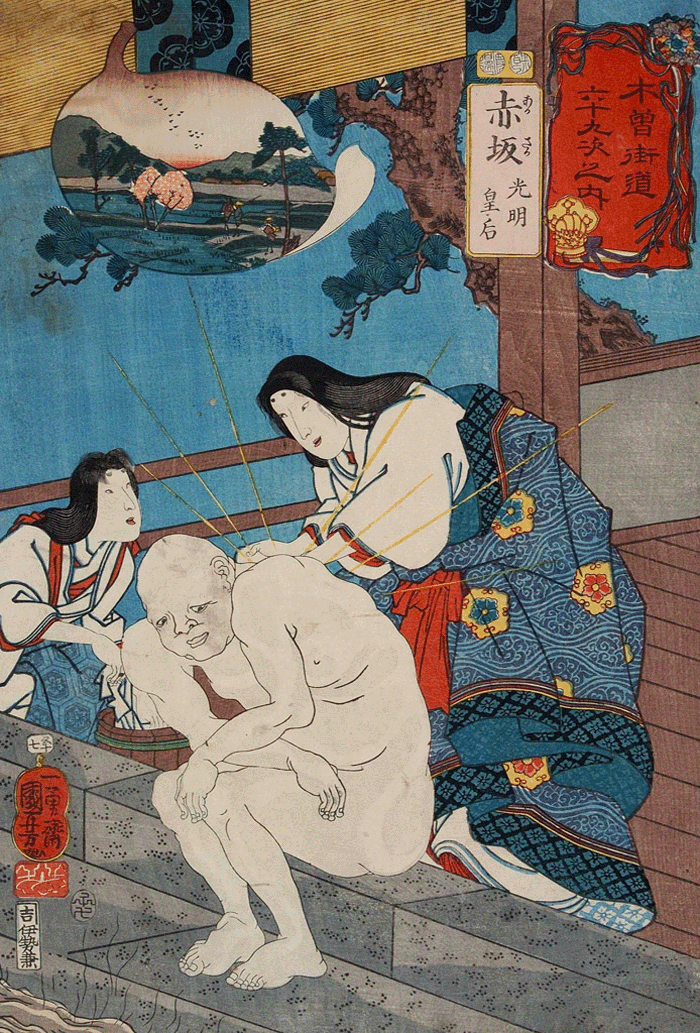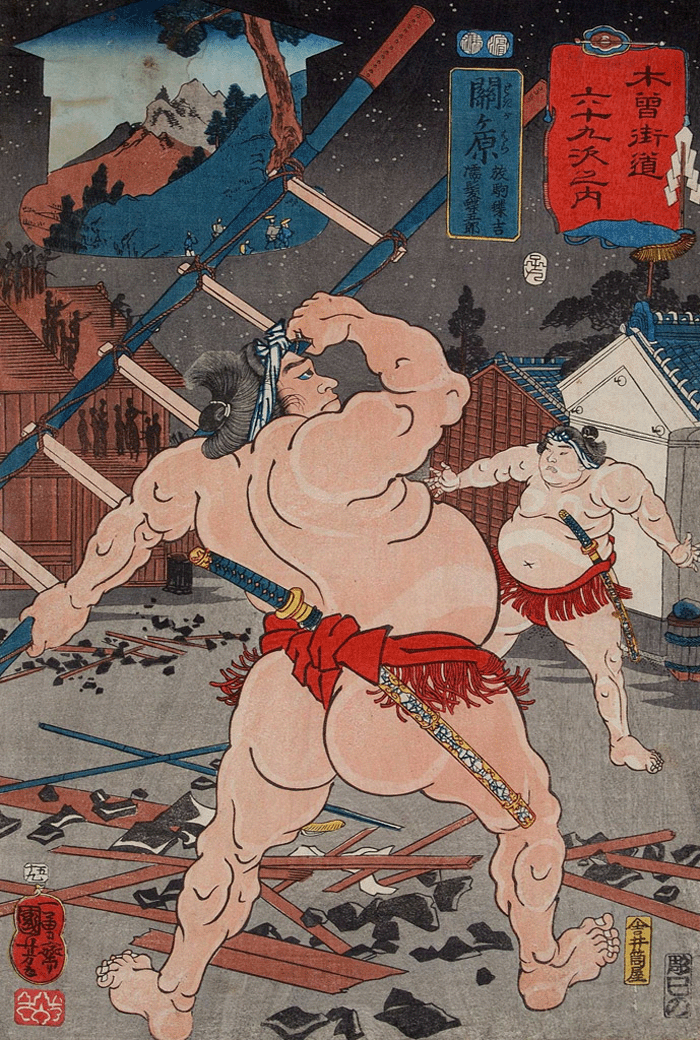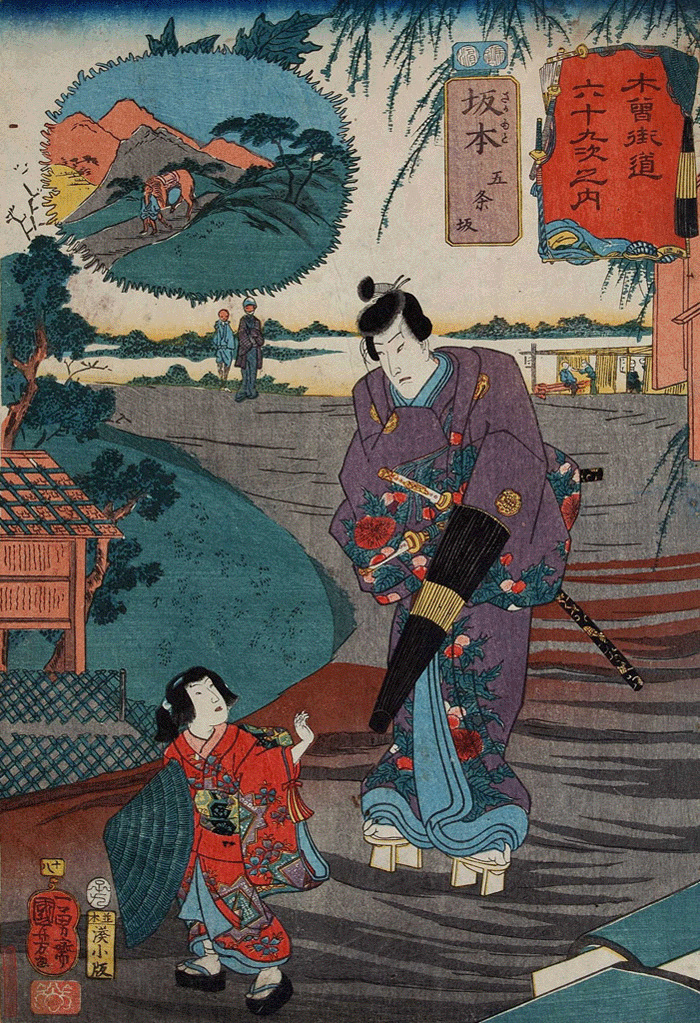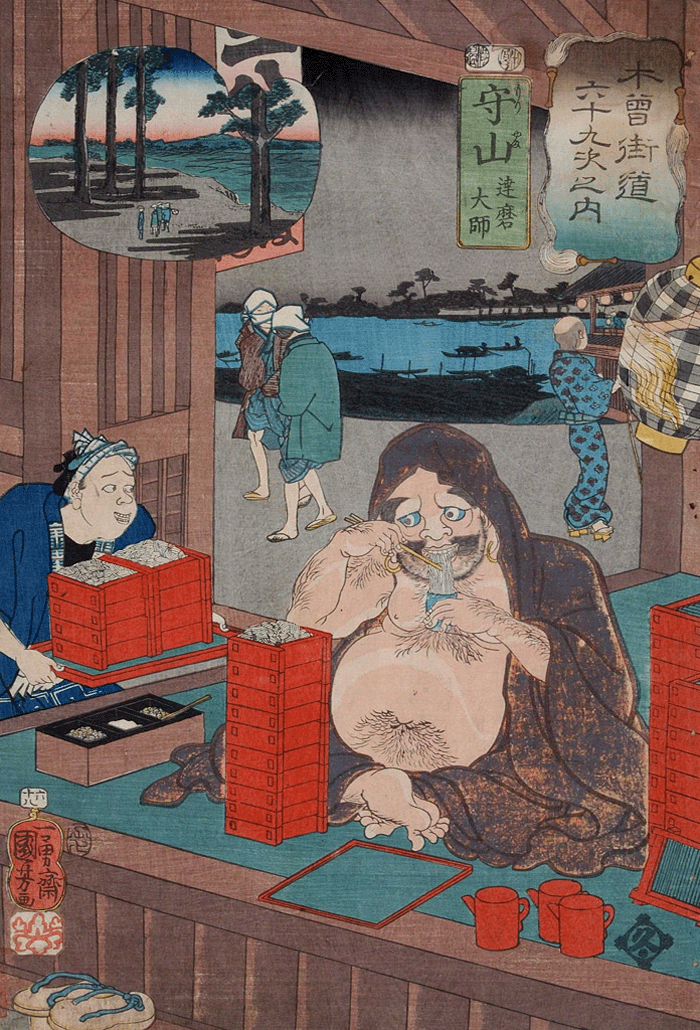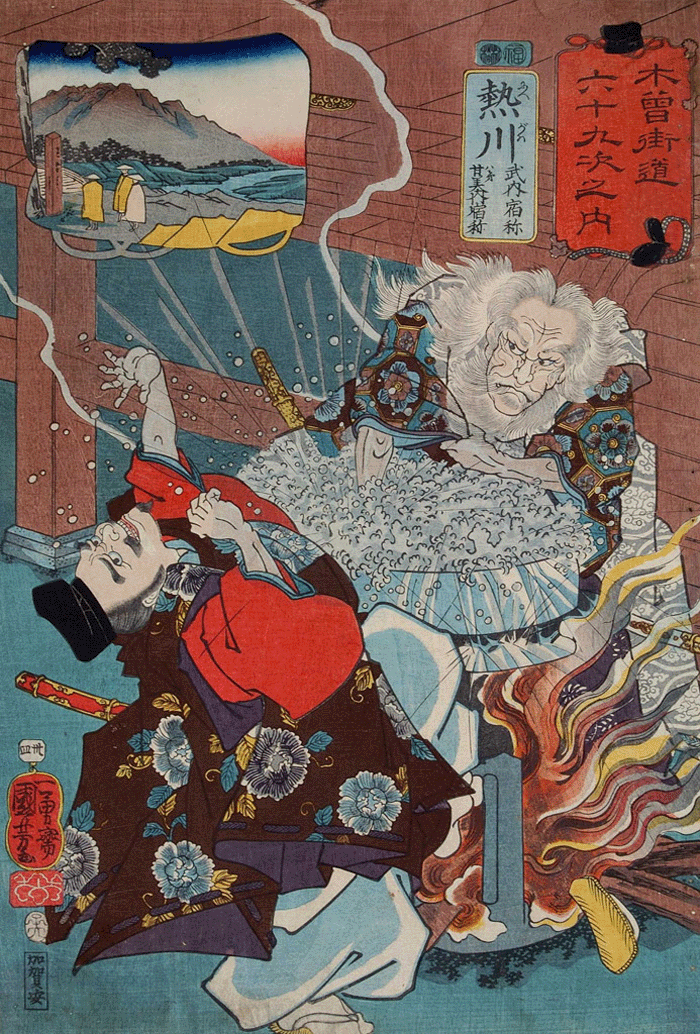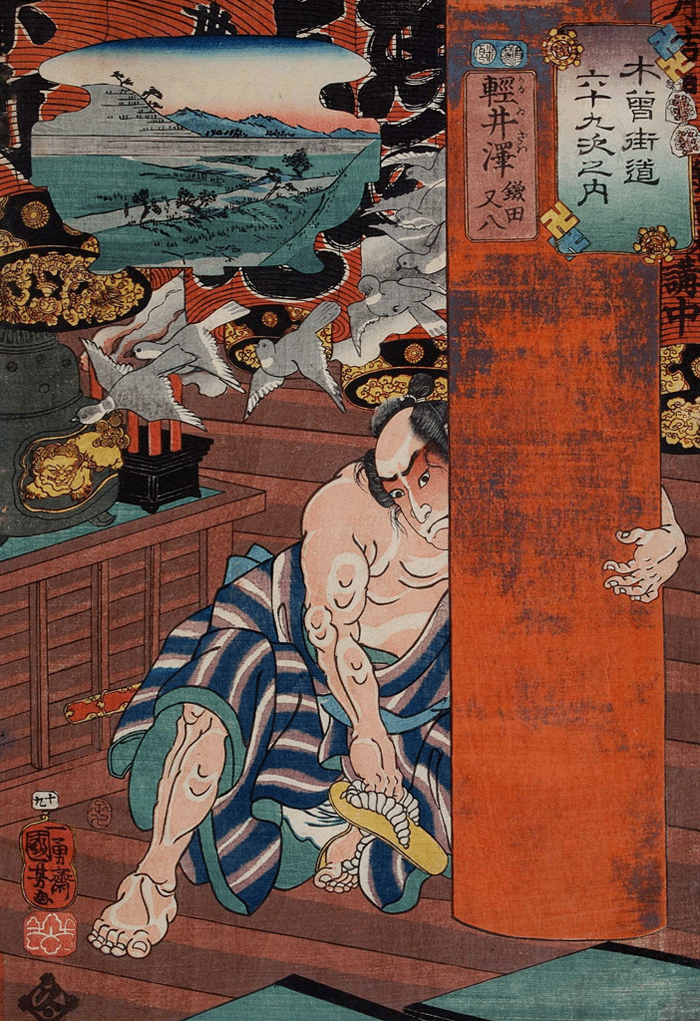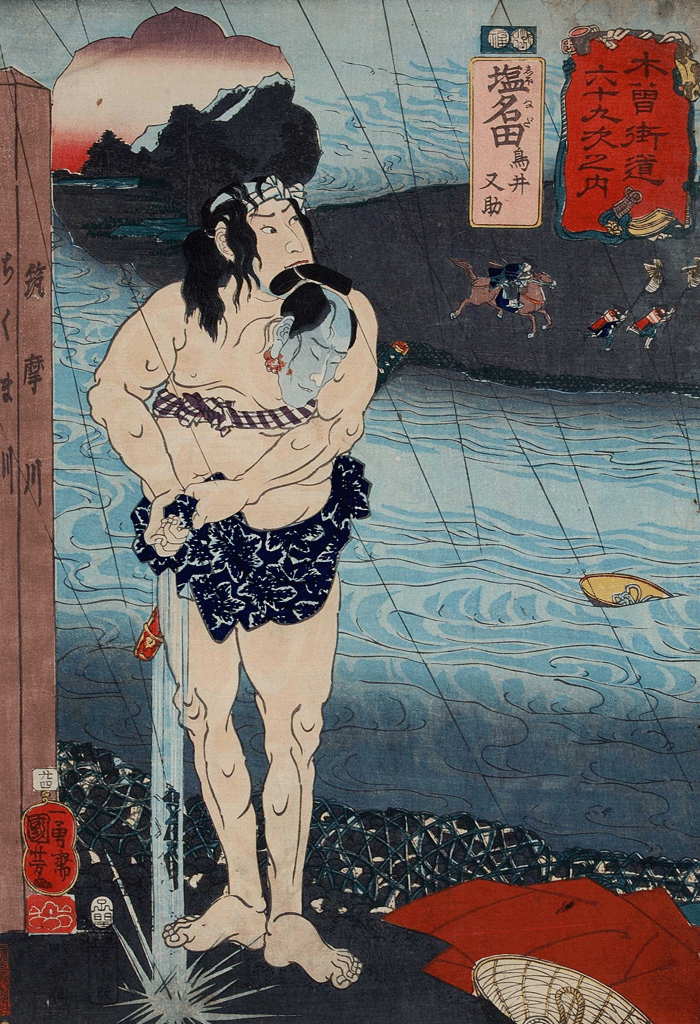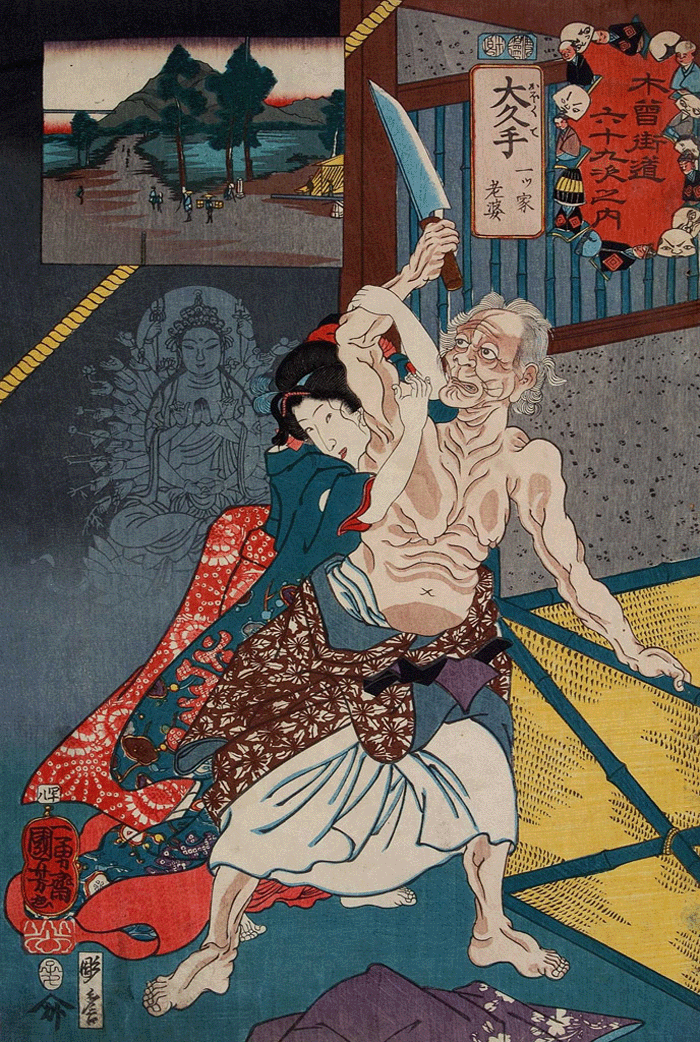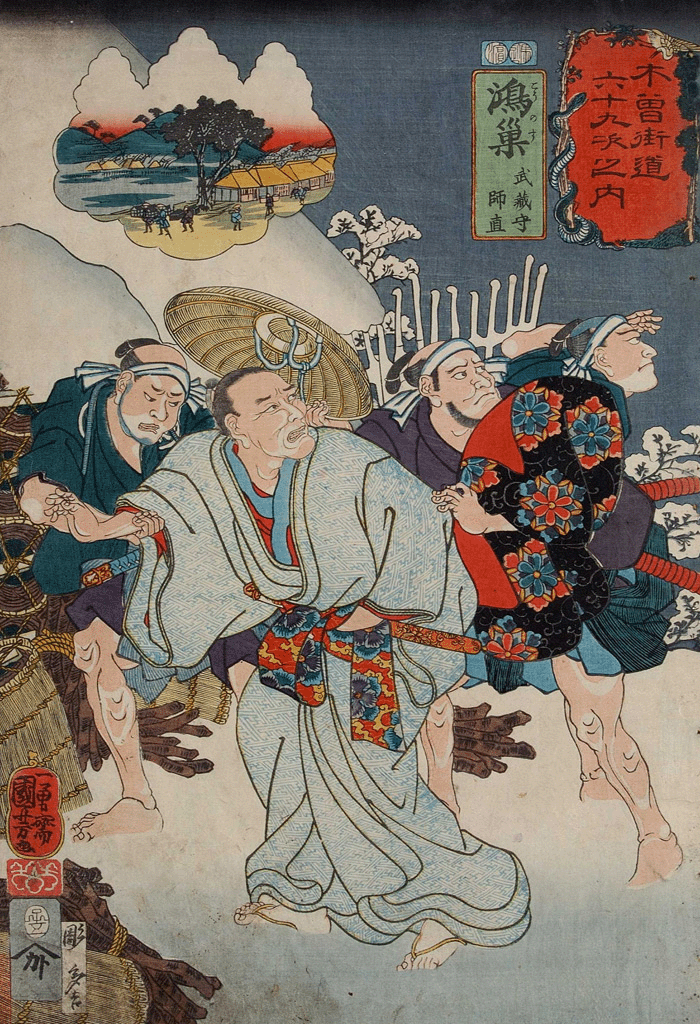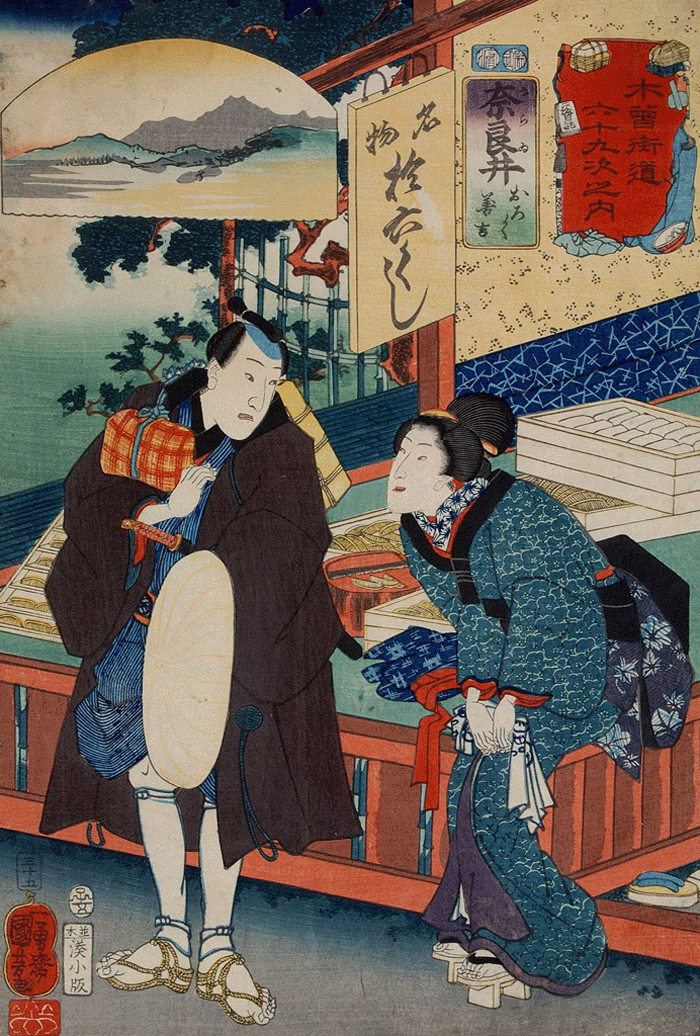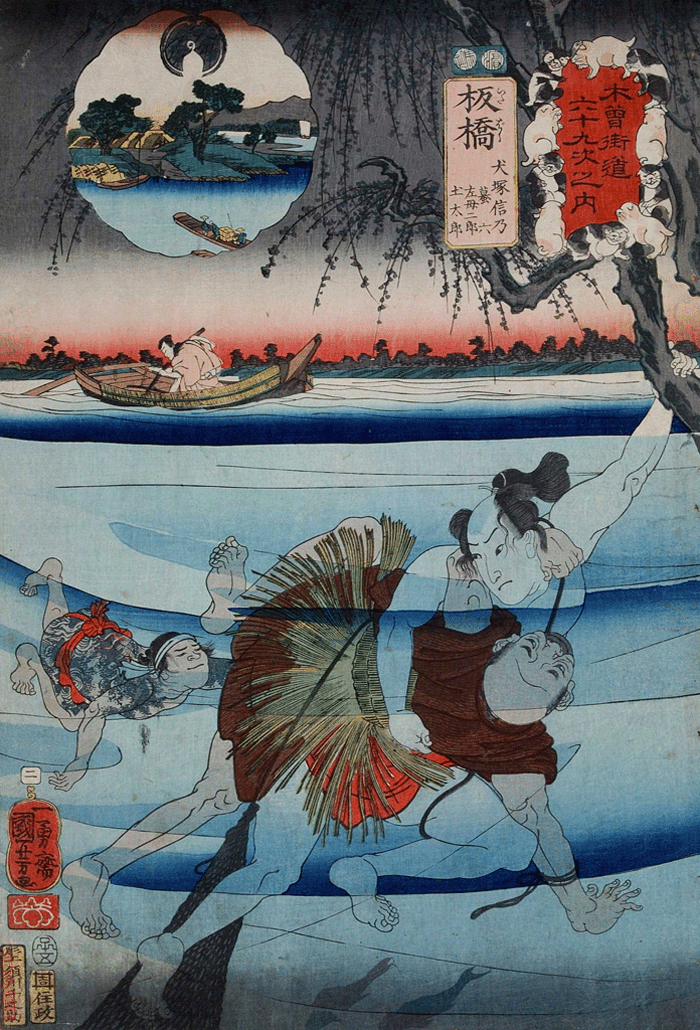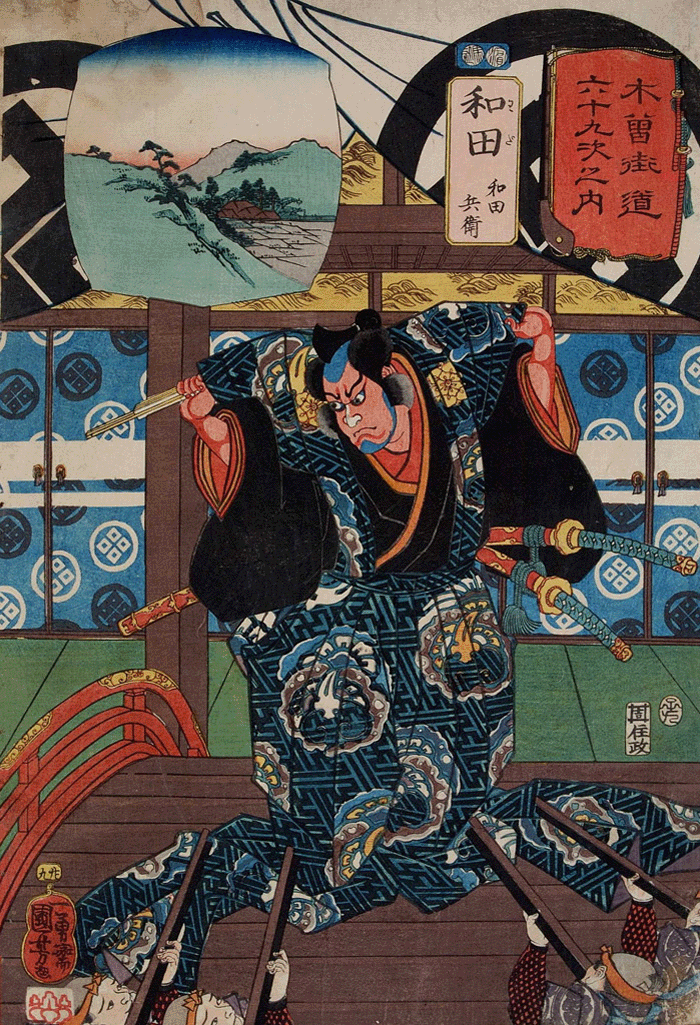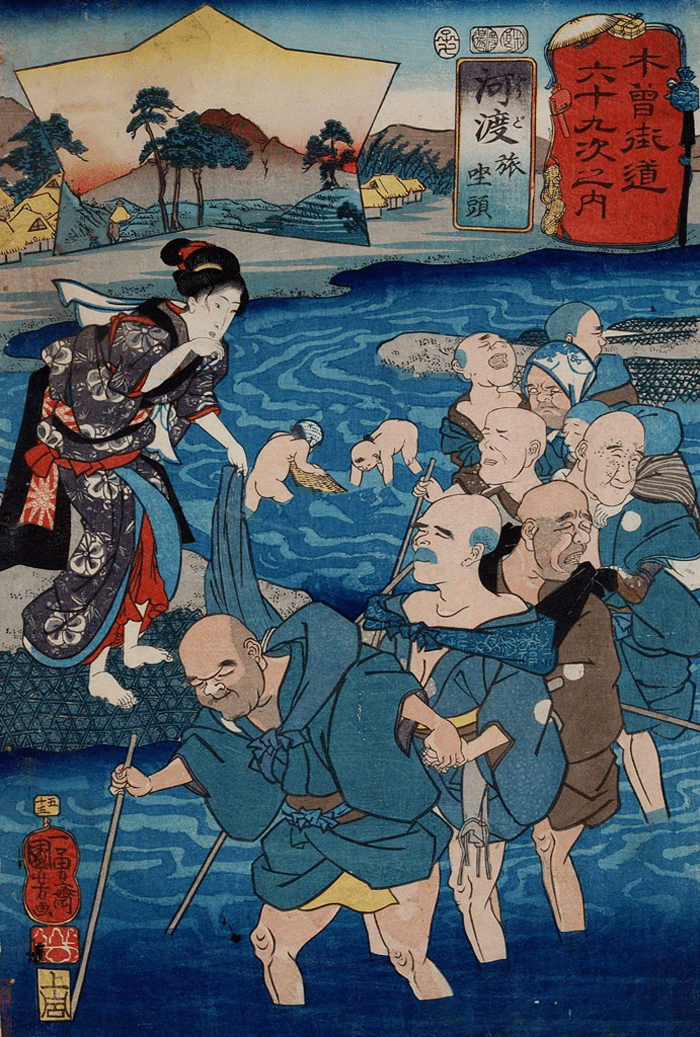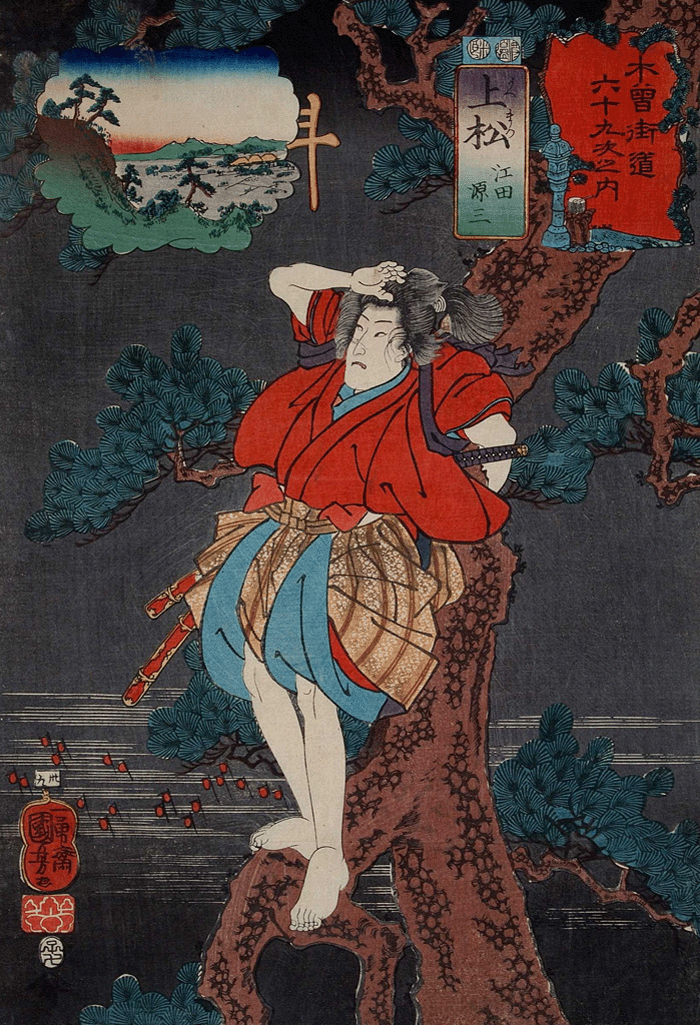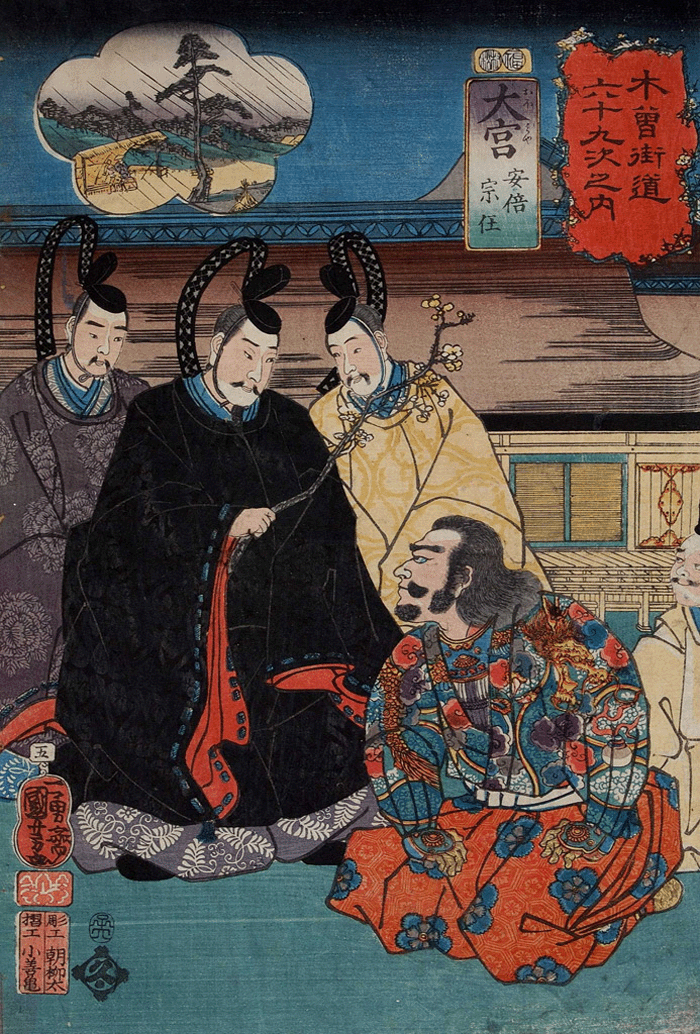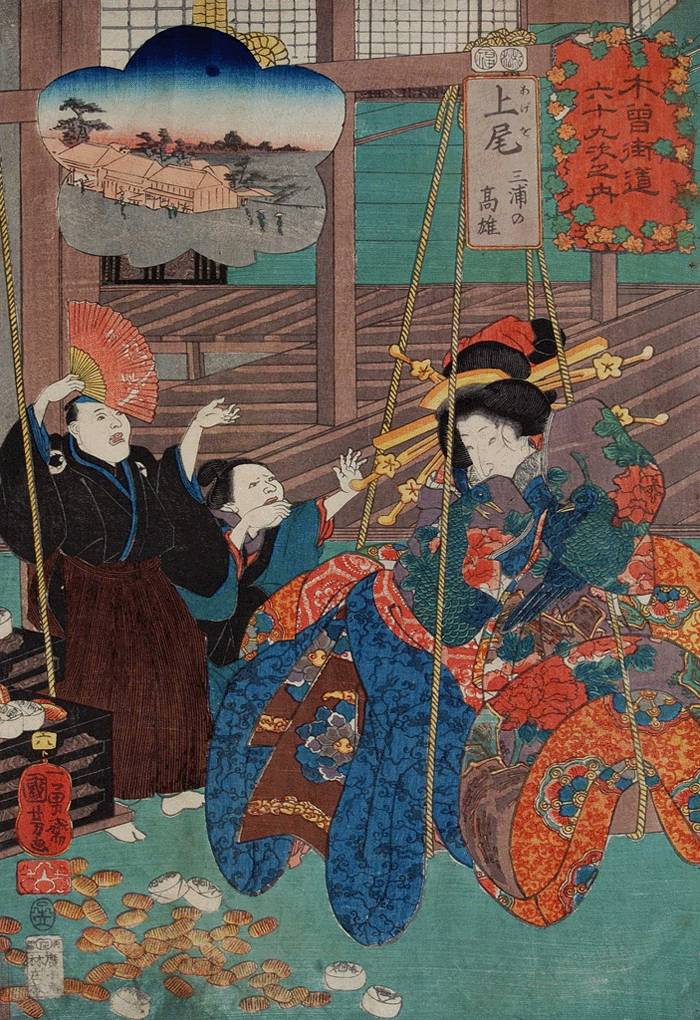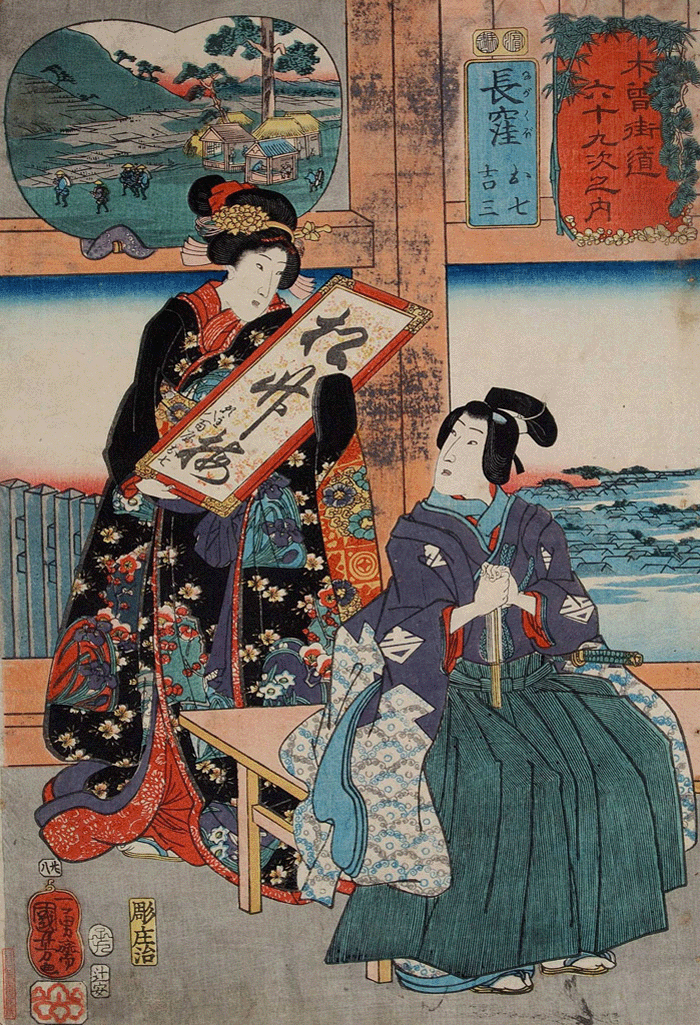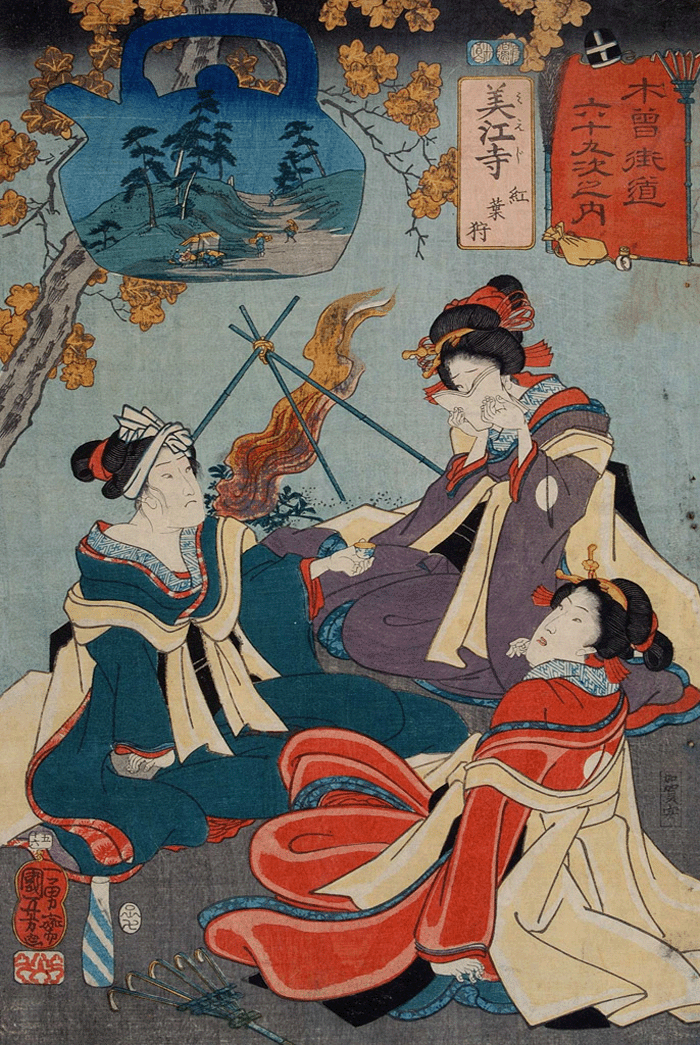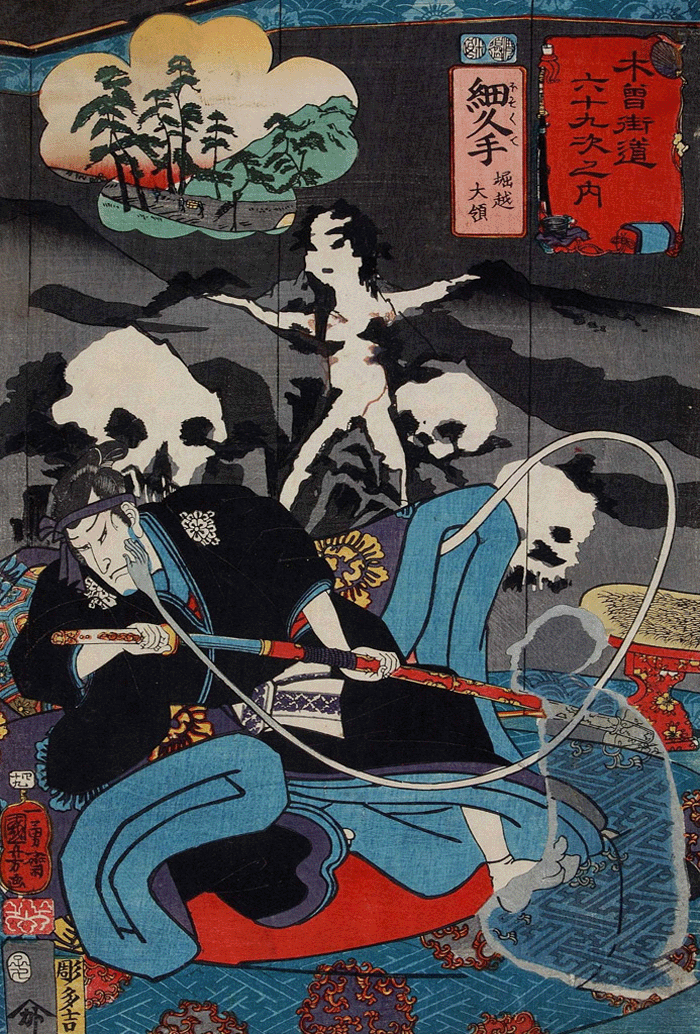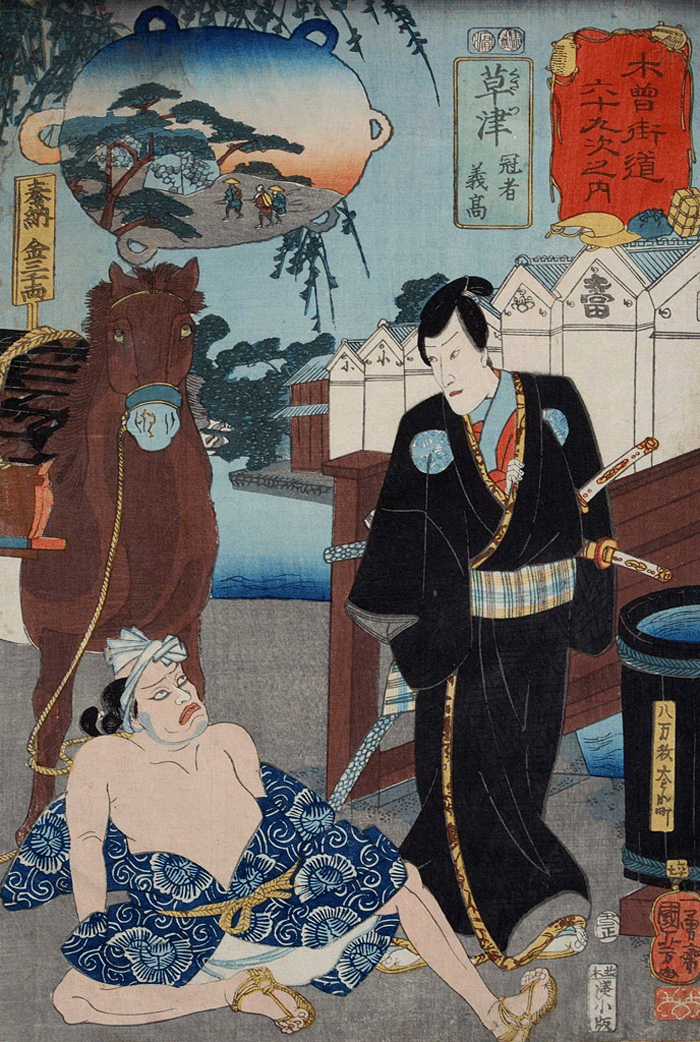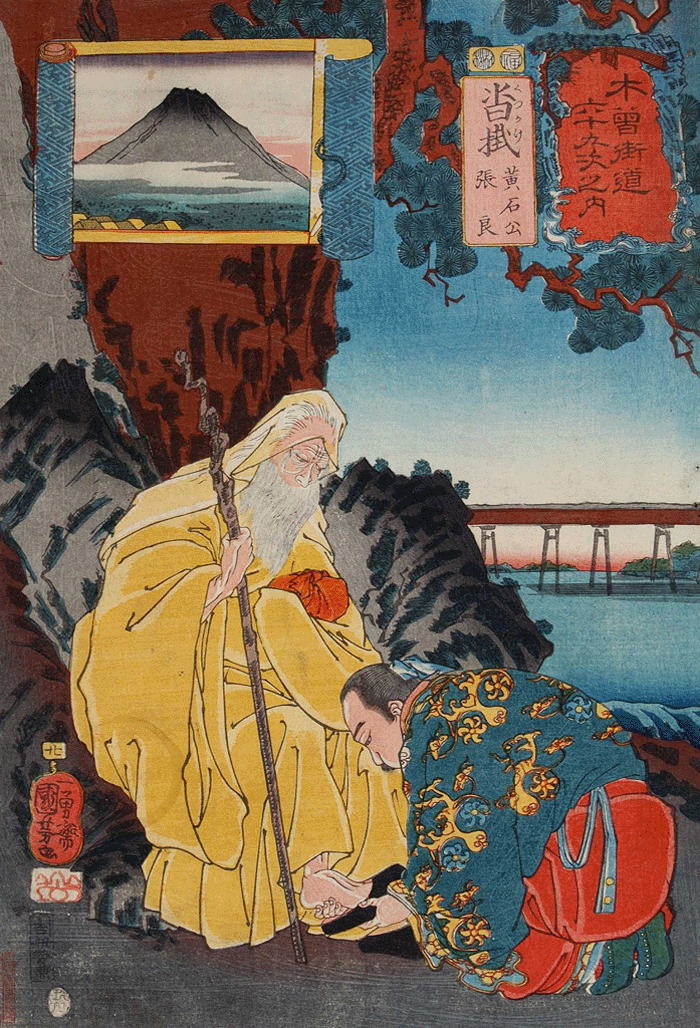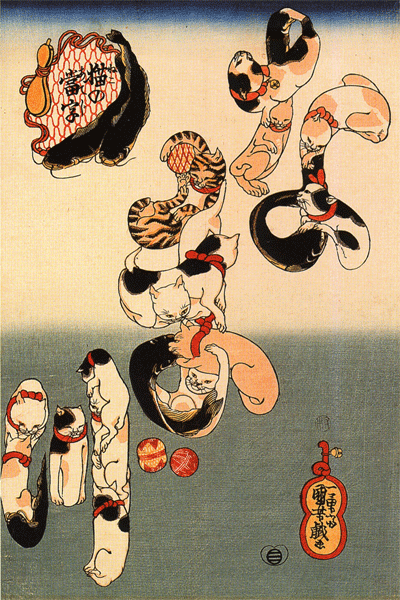大判3枚続




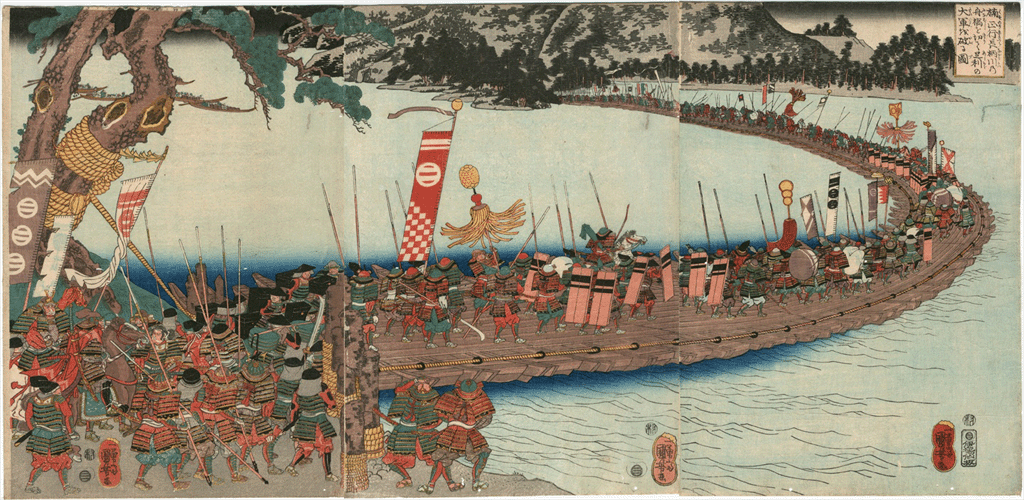



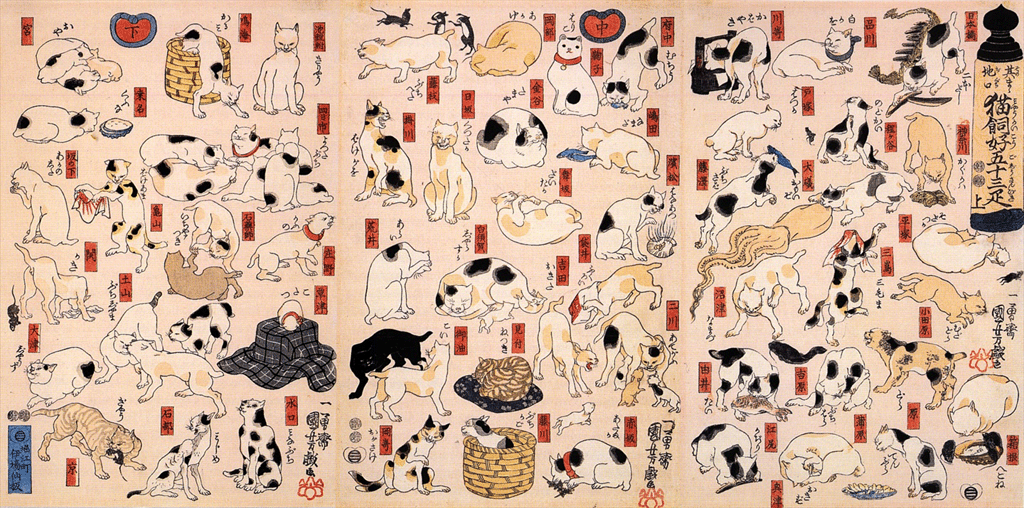
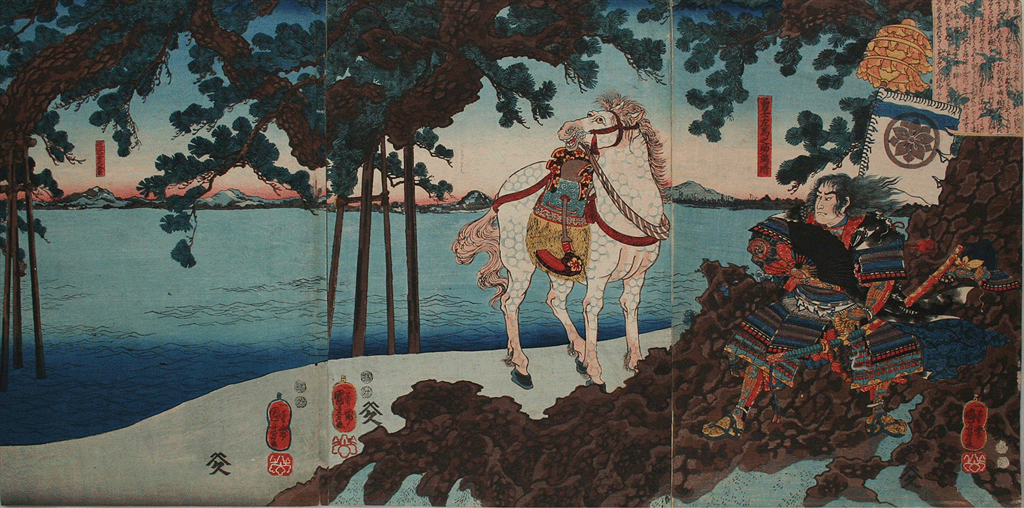




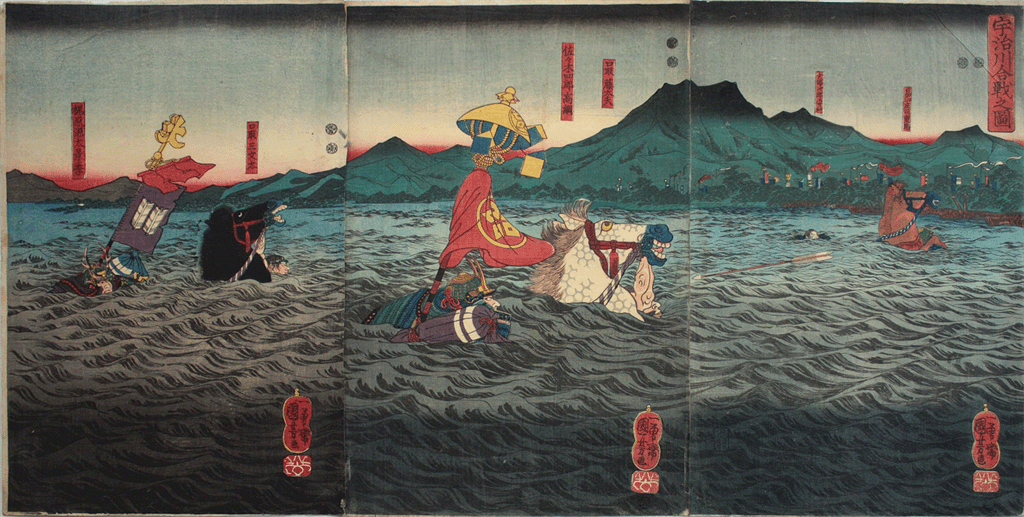


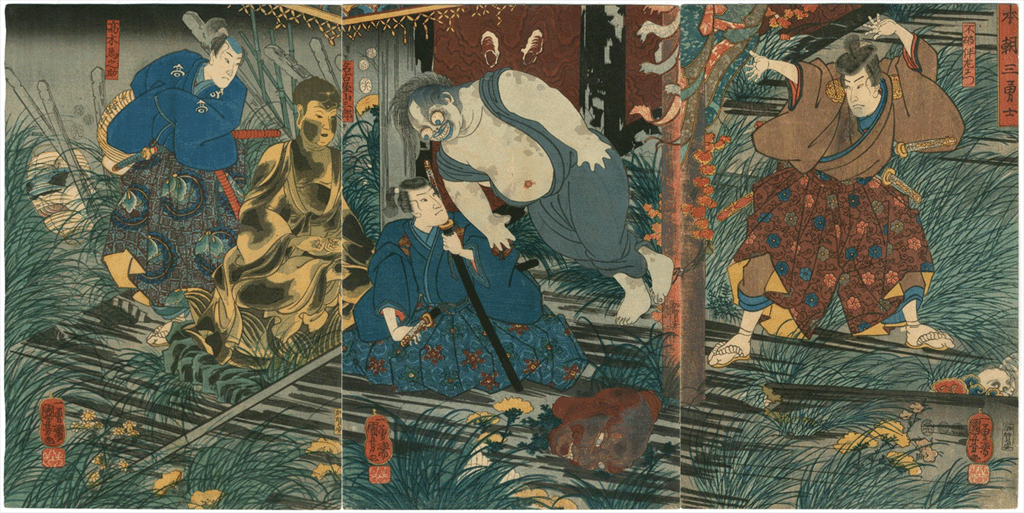


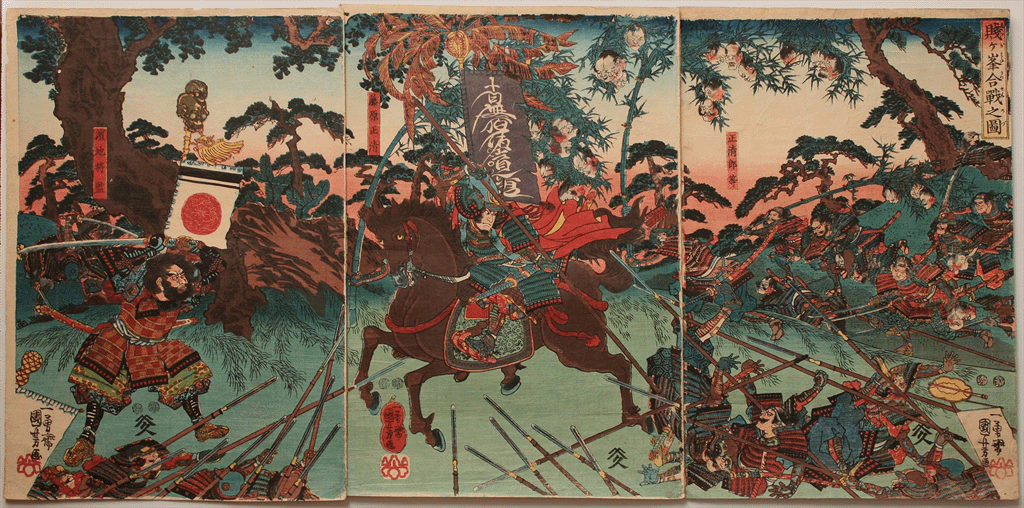
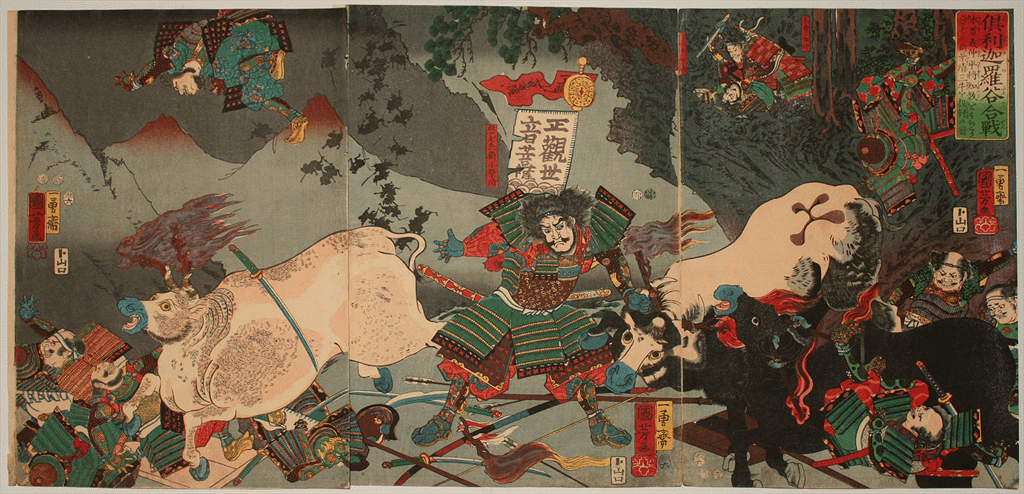
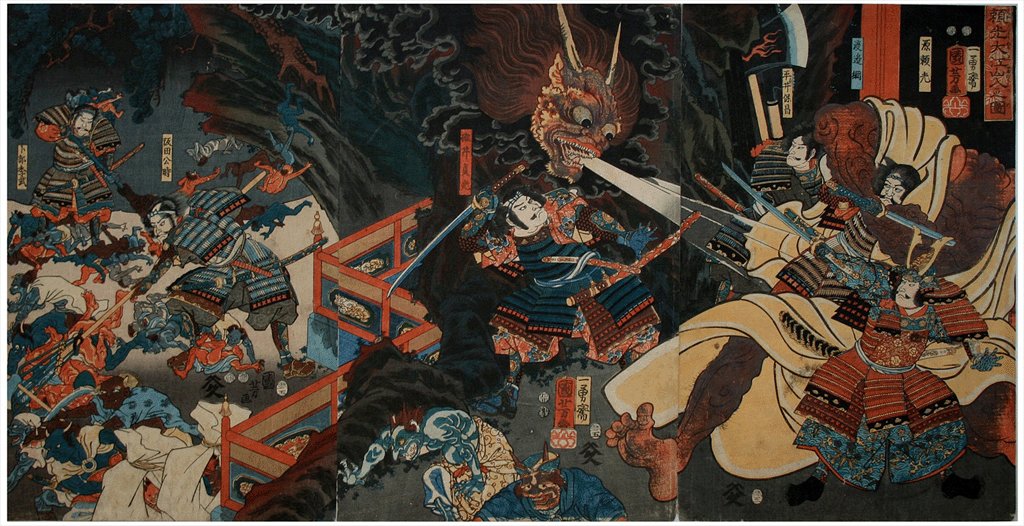
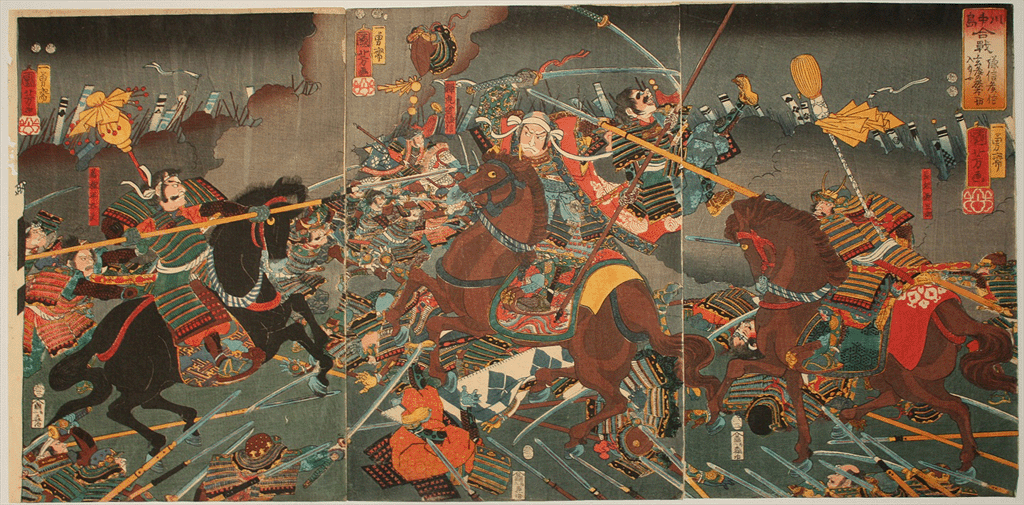
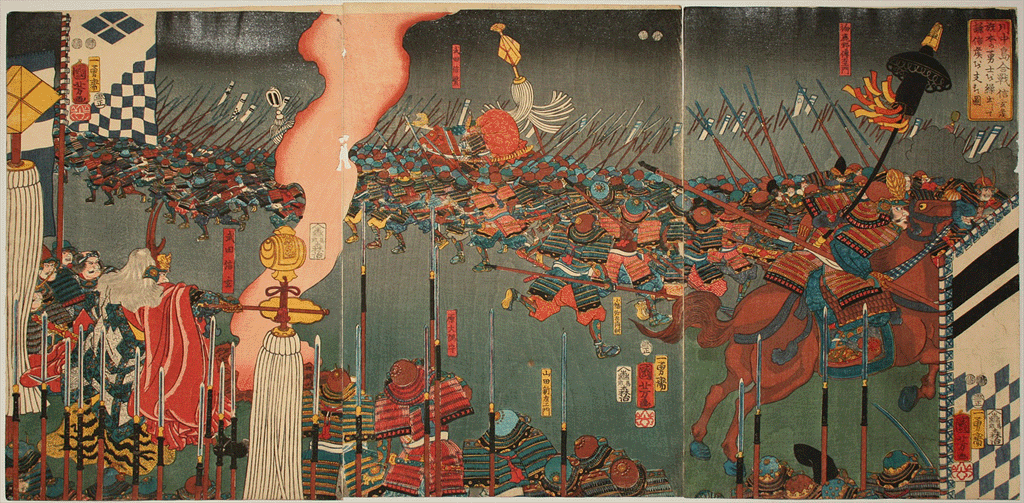

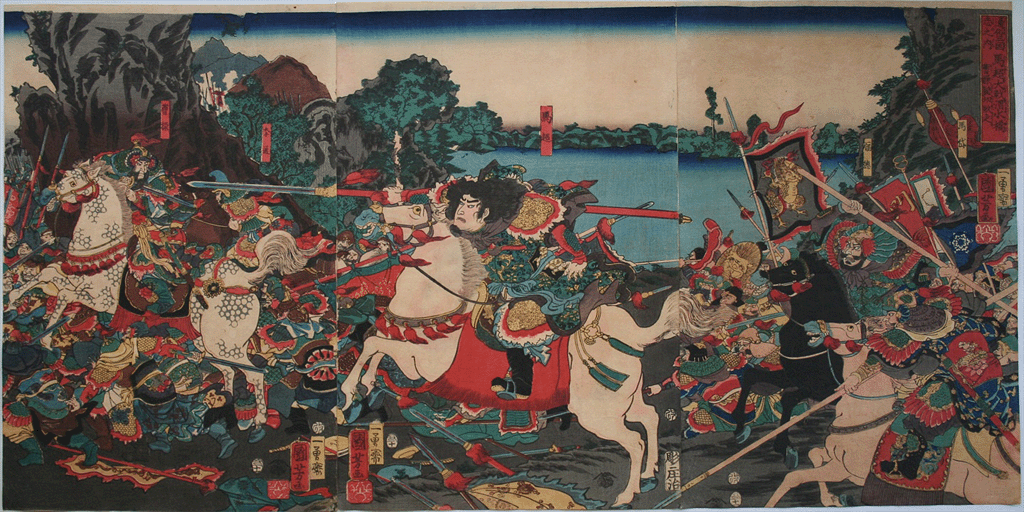
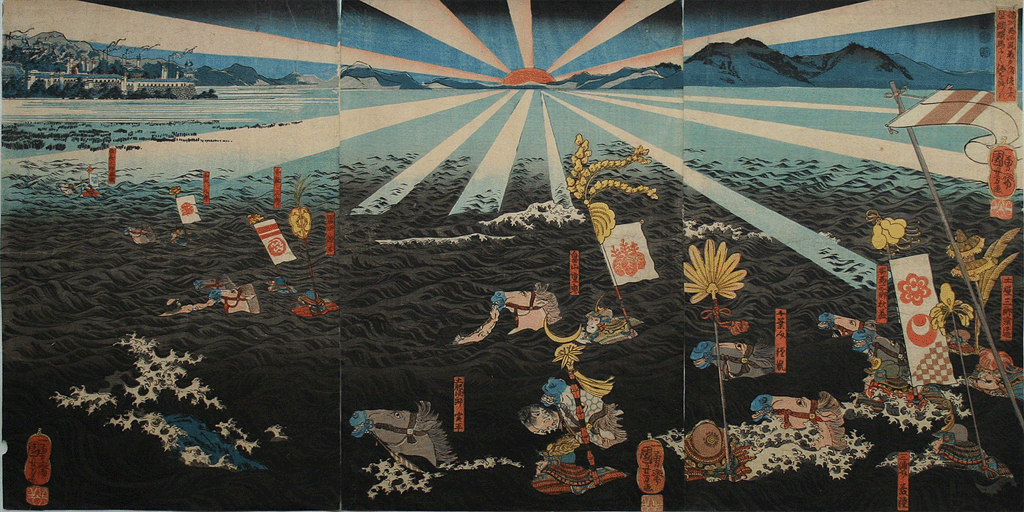

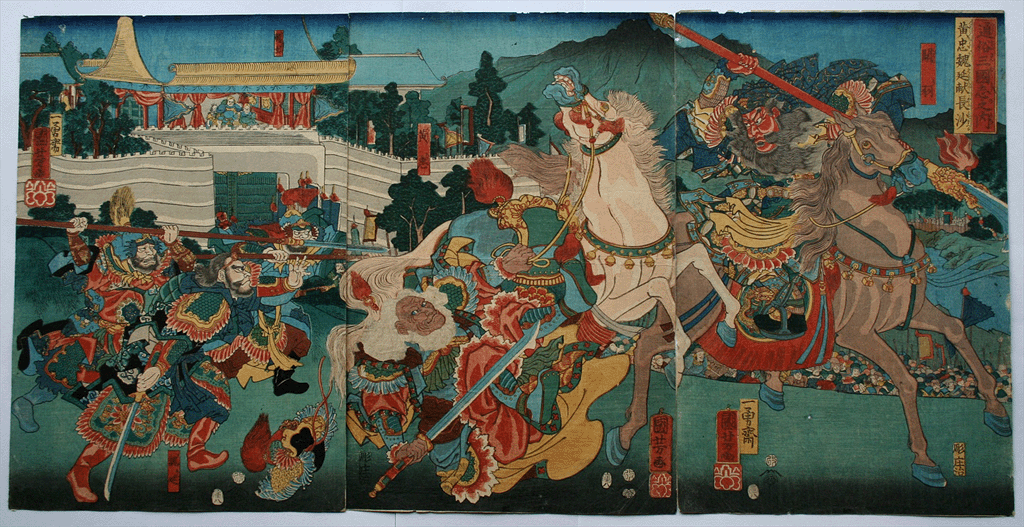
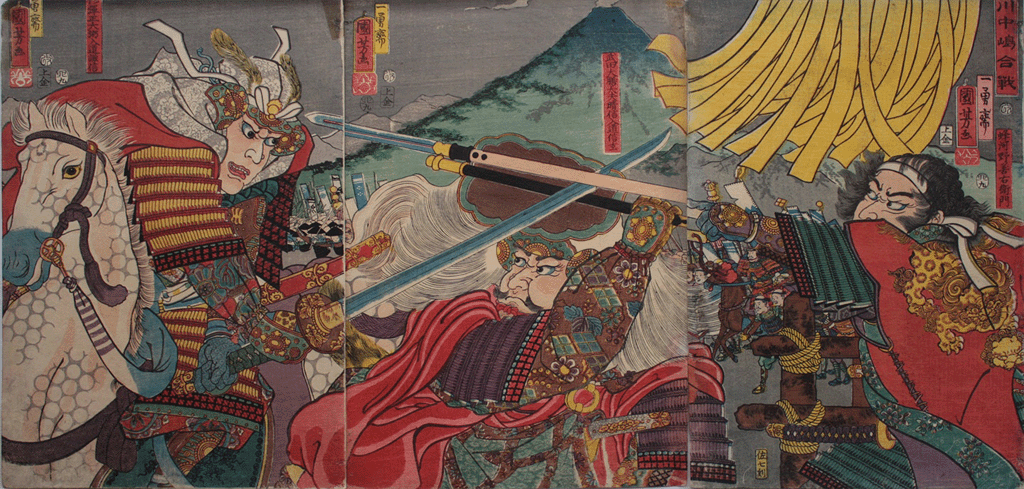
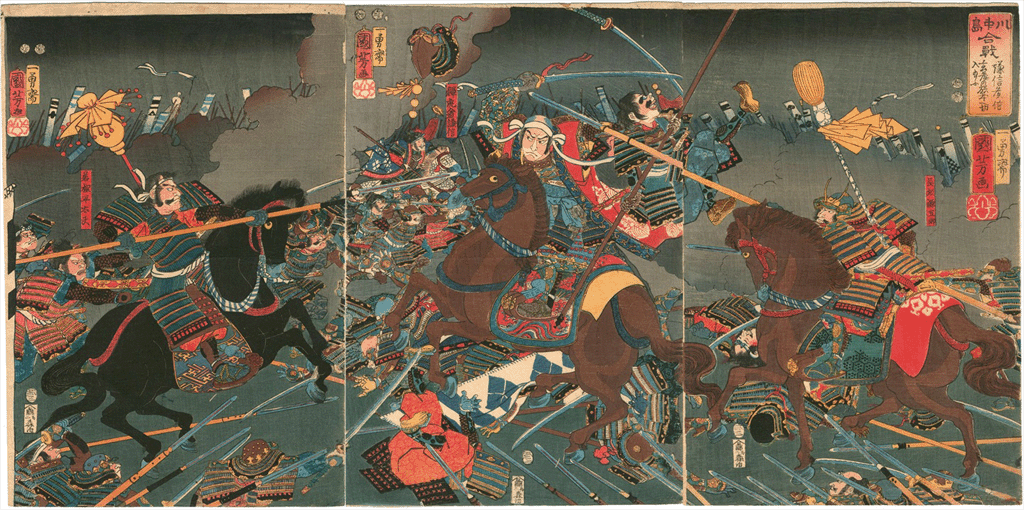



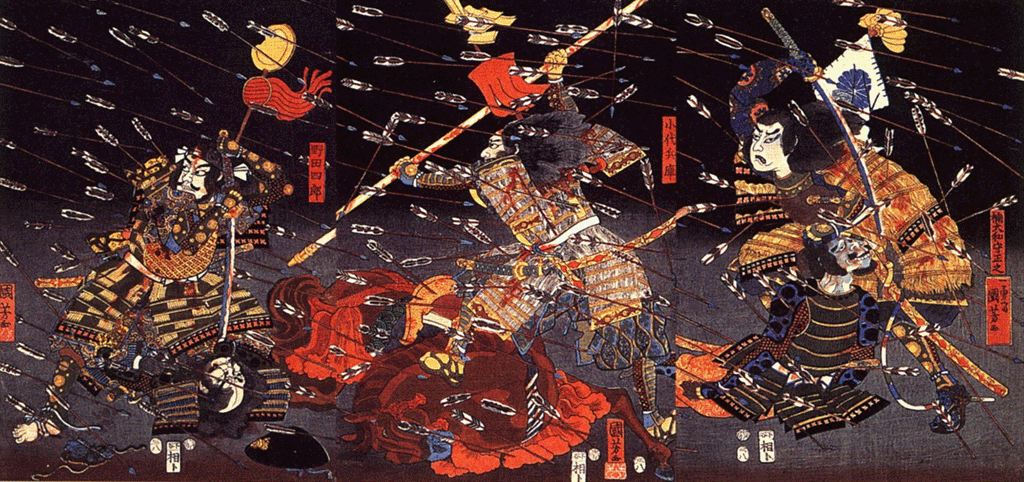







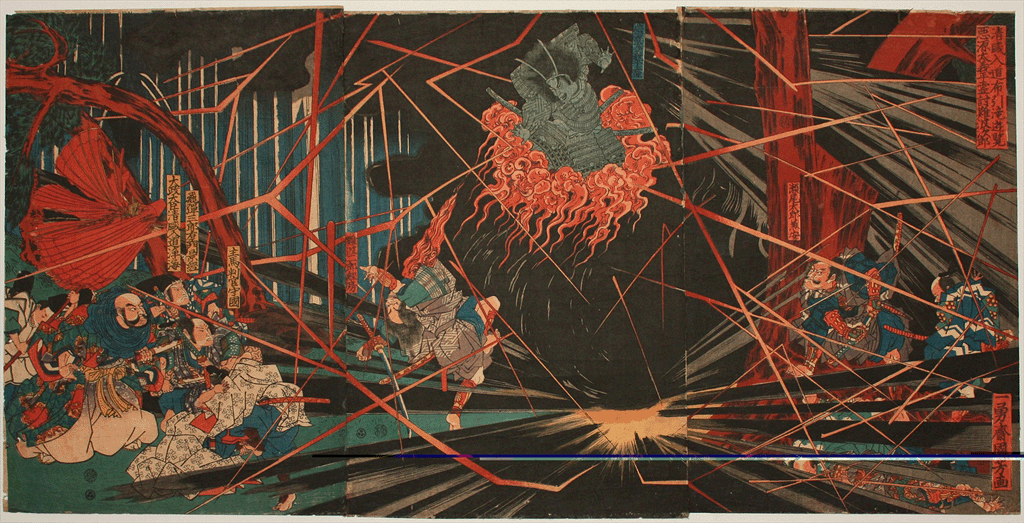

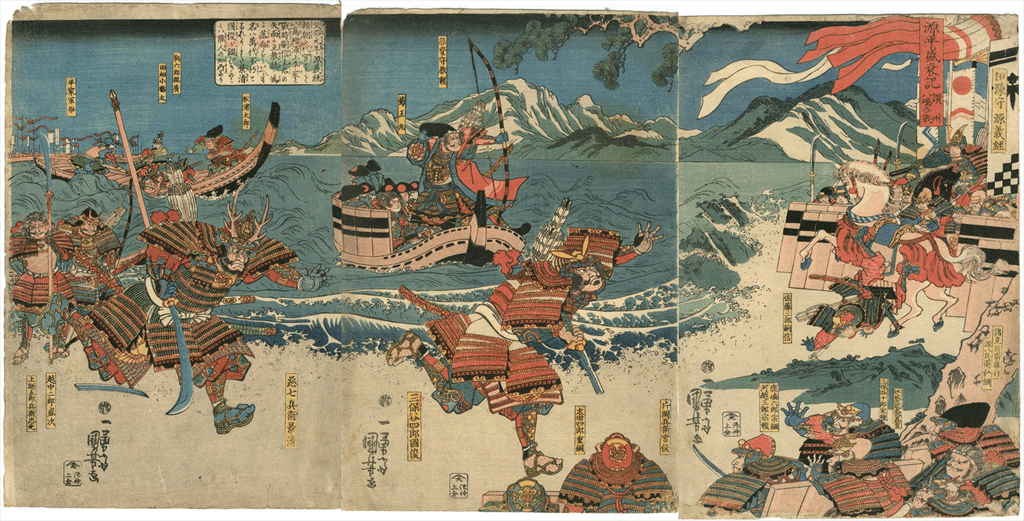
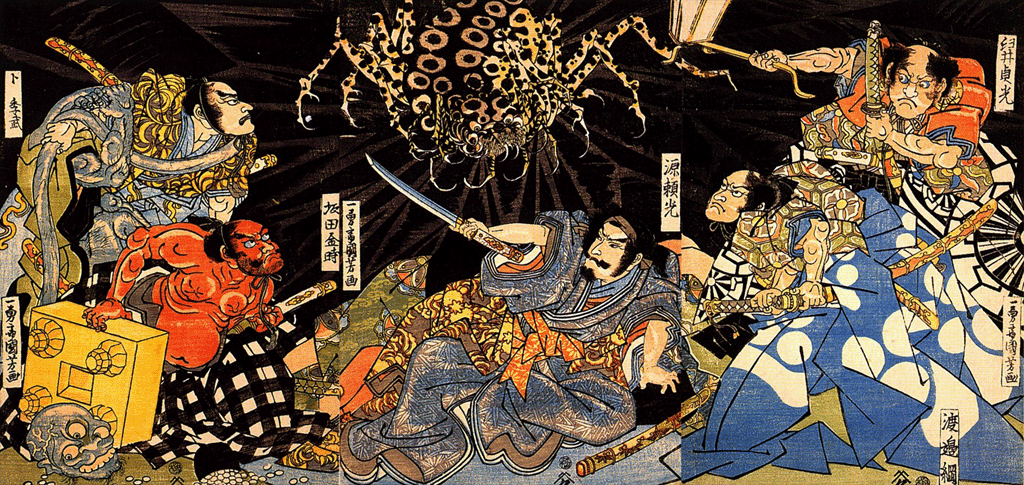
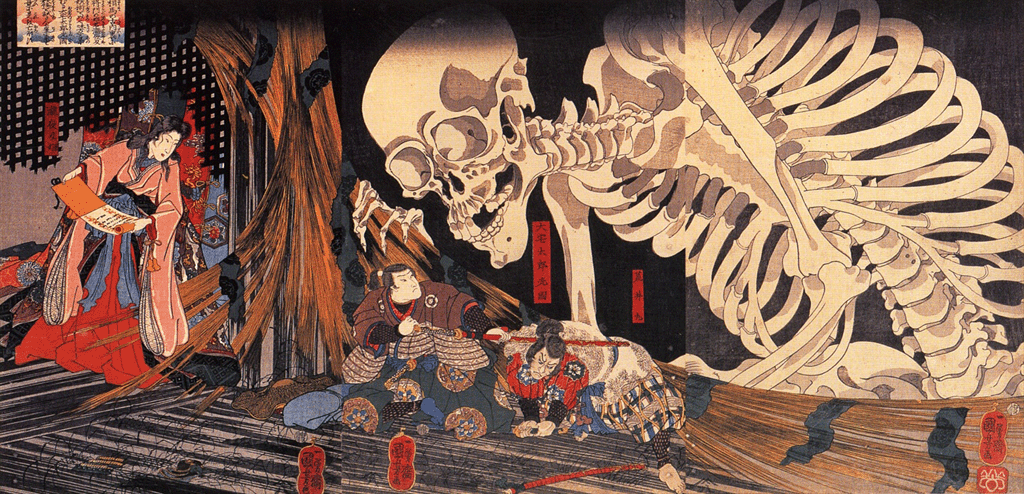


====================================================================
木曽街道六十九次之内
蕨 犬山道節

蕨 犬山道節
三 蕨 犬山道節
版元:井筒屋庄吉 年代:嘉永5(1852)年5月
Kn03 本図は、『南総里見八犬伝』第三輯巻之四に掲載される、「寂莫道人肩柳」が円塚山で火遁の術を使って自焼する場面に取材しています。「寂莫道人肩柳」とは、忠の玉を持つ「犬山道節」のことで、民衆から軍資金を集めるためにこのような荒行を行っています。八犬伝では、道節は柴を使って自焼しますが、国芳の絵では右下に藁が材料として描かれています。これは、もちろん、宿場名の「蕨」(わらび)に掛けて、「藁の火」(わらのひ)とした意からです。もとより、宿場名「蕨」の由来の中には、藁の火が元になっているという伝承もありますから、ただの地口というだけではないかもしれませんが、といって、蕨の宿場の風景ではありません。「日本橋」「板橋」の宿場名とその作品情景とが地理的に関連していたのが、「蕨」に至って言葉遊び的な繋がりになってしまっている点に注意していただきたいと思います。
標題の周りは、一つ前の「板橋」と全く同じで10匹の子犬で囲まれています。これは「板橋」と「蕨」とが見開きの一対(頁)と考えれば納得がいきます。八犬士の信乃と道節を水と火という対比をもって紹介する趣向です。以後の作品を読み解く際、見開き一対(頁)という認識は、大いに役立つものと考えられます。
Kom03 平木浮世絵美術館資料は、コマ絵の枠の形は雪輪紋で、雪の中を駆け回る犬のイメージから犬と雪とは縁のものという考えがあって、その意匠が使用されていると解しています。しかし、よく見ると、雪の六角形(雪輪)ではなく、五角形(五瓜あるいは五銀杏葉)であることに気付きます。この点は、次のように考えたいと思います。すなわち、道節の犬山家が仕えた煉馬氏は豊嶋氏とともに管領扇谷定正らに滅ぼされ、道節の父も討死にしたため、道節は扇谷定正を仇として執拗に付け狙いますが、その滅ぼされた煉馬氏、すなわち道節の家紋と推測されるのです(『南総里見八犬伝』第三輯巻之一参照)。 いずれにしろ、前の作品の「蝶」の紋が信乃にゆかりがあるように、本作品の「五角形」は道節ゆかりの紋と考えるのが筋でしょう。
コマ絵の風景は、英泉・広重版木曽街道「蕨」の背景と異なっています。おそらく、英泉・広重版木曽街道「板橋」を国芳が飛び越した影響から、ここでも一つ飛び越して、英泉・広重版木曽街道の「浦和」をモチーフに描いたものと見受けられます。土橋を過ぎ、宿場にもっと近づいた箇所からの描写で、馬子の姿を描き入れたところは同じ着想です。ただし、浅間山は省略されています。
====================================================================
越川 鷺地平九郎

越川 鷺地平九郎
六十六 越川 鷺地平九郎
版元:上総屋岩吉 年代:嘉永5(1852)年7月
Kn66 「鷺地(池)平九郎」は、太平記の世界、楠正成、楠正行(まさつら)親子の活躍を彩る人物です。山田意斎(案山子)の読本『楠正行戦功図会』(前編は文化4・1821年、後編は文化7・1824年)に登場します。富田林の農民の子ながら、足利直義の軍を討つために参集し、湊川合戦では17人の大将の首級をあげ、正成に見せたとあります。正成の家臣の鷺池九郎右衛門の養子となり、以後、鷺池平九郎と名乗ります。国芳の浮世絵にも度々描かれ、『本朝水滸傳剛勇八百人一個』などがあります。弟子の歌川芳年も『和漢百物語』で採り上げています。うわばみ、大猪などを退治する構図が多いのですが、本作品は前掲『楠正行戦功図会』を参照したのでしょうか、湊川合戦であげた首級を討った大鉞(まさかり)の血を川で洗っているところです。「血の川」→「(え)ちかわ」→「越川」という繋がりでしょう。標題は、
槍、大槌、甲冑など、鷺池平九郎の武勇に因んで戦道具で囲まれています。
Kom66 コマ絵の意匠は、鷺池平九郎の名から、
鷺鳥をかたどったものです。英泉・広重版木曽街道の「恵智川」は、宿場の南を流れる恵智(愛知)川とそこに架かる無賃橋を描いています。国芳のコマ絵は、愛知川の宿場から西国巡礼32番目の札所・観音正寺がある観音寺山を遠望している図と考えられます。
====================================================================
芦田 あらい丸 女月尼

芦田 あらい丸 女月尼
廾七 芦田 あらい丸 女月尼
版元:住吉屋政五郎 年代:嘉永5(1852)年8月
Kn27 文化3(1806)年、山東京伝の読本「善知鳥安方忠義伝」(うとうやすかたちゅうぎでん)を脚本として、天保7(1836)年7月江戸市村座「世善知鳥相馬旧殿」(よにうとうそうまのふるごしょ)に代表される、多くの浄瑠璃・歌舞伎が上演されていますが(『カブキ101物語』200頁参照)、「女(如)月尼」は、ここに登場する妖術使いで、平将門の遺児、後の瀧夜叉姫のことです。同じく将門の遺児で弟の太郎良門とともに、筑波山で蝦蟇の妖術を身につけ、亡父の遺志を継ぎ謀反を企てます。
国芳作品は、筑波山中で、鈴、鏡、刀、松明を持って蝦蟇の妖術を修行する如月尼と生首を突き立てた従者「あらい(荒井)丸」とを描いています。この後、如月尼は将門が築いた相馬の御所に行くこととなります。したがって、標題の周りは、相馬に因んで
馬で覆われています。そこで起こった事件が、有名な国芳作品『相馬の古内裏』大判三枚続作品に示されています。なお、宿場名「芦田」との関連は、如月尼の足下の、雨中や雪中に履く「足駄」(あしだ)の地口です。
Kom27 さて、コマ絵は、善知鳥(うとう)物語に因んで、海鳥の善知鳥の形です。コマ絵内の風景ですが、英泉・広重版木曽街道の「あし田」と同じく、西方から見た「笠取峠」と思われます。ただし、英泉・広重版では杉であったものがコマ絵では
松になっている点で、有名な「笠取峠の松並木」それ自体が画題となっているのかも知れません。背景は、浅間山となります。
八幡 近江小藤太 八幡三郎
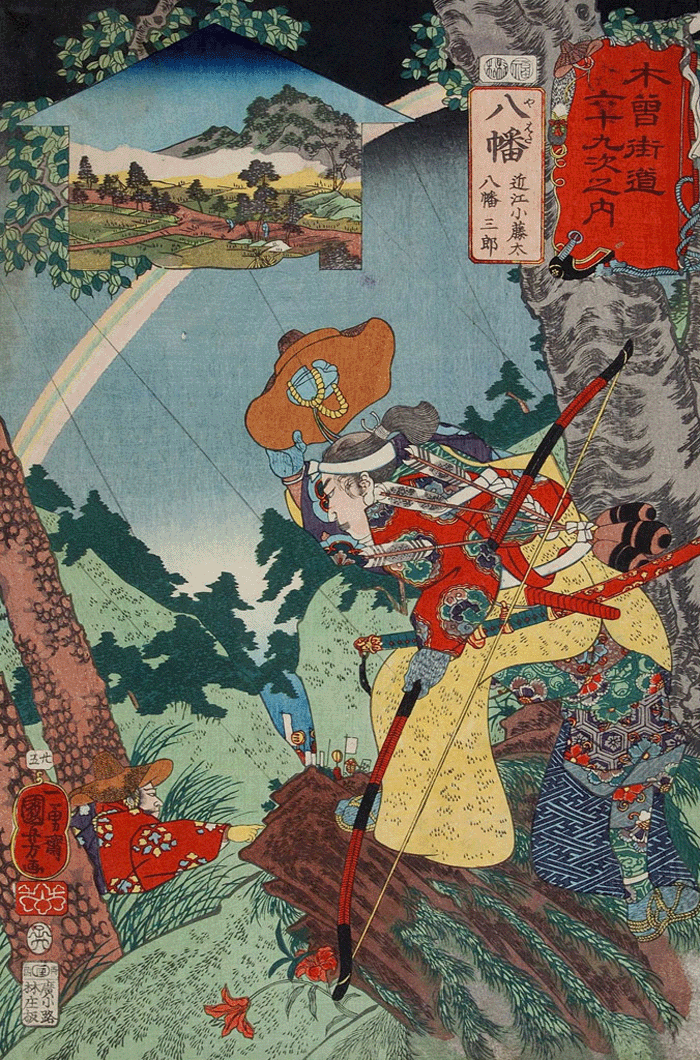
廾五 八幡 近江小藤太 八幡三郎
版元:林屋庄五郎 年代:嘉永5(1852)年6月
Kn25 当作品を見ると、二人の武将が谷間を進む一行を狙っていますが、これが後の曽我兄弟の仇討ちへと至る発端となった出来事です。すなわち、工藤祐経の家臣、「近江小藤太」と「八幡三郎」が牧狩りに乗じて、所領を横領した工藤祐親を弓矢で射ったところ、誤って、その婿で、曽我兄弟の父親、河津三郎祐泰を射殺してしまったというものです。祐泰の遺児は、その妻が曽我裕信に再嫁したことから、元服して、曽我十郎、五郎と名乗ります。
祐泰が落命したとき、山めぐりの村時雨が降っていたということで、背後に虹が見える雨模様の天気として描かれています。画中の虹は、後の、お目出度い曽我の仇討ちの前祝いというのは考えすぎでしょうか(後述作品六十参照)。宿場名「八幡」から「八幡三郎」を連想し、仇討ちの発端となった事件を画題としました。標題の周りは、
牧狩り装束や道具で囲まれています。
Kom25 コマ絵の形は、小藤太、三郎の主、工藤家の
「庵木瓜」(いおりもっこう)です。中の風景は、英泉・広重版木曽街道の「八幡」作品の背景と同様と思われます。やはり、流れ山もしくは浅間山外輪山が見えます。『木曽路名所図会』巻之四の図版「望月駅」に描かれる「八幡宿」とよく似ています。
作品の「廾四 塩名田」と「廾五 八幡」は、見開きの一対となっていて、ともに雨模様であることに気付きます。もちろん、これは、意図的なもので、多賀大領および河津三郎祐泰の暗殺事件を象徴するものです。浮世絵における雨は、歌舞伎などの演出効果の影響を受けて、実際に雨であったかどうかは別として、事件や事故などによる死を暗示・装飾するものとして使われることが多いということに注意が必要です。
大津 小万
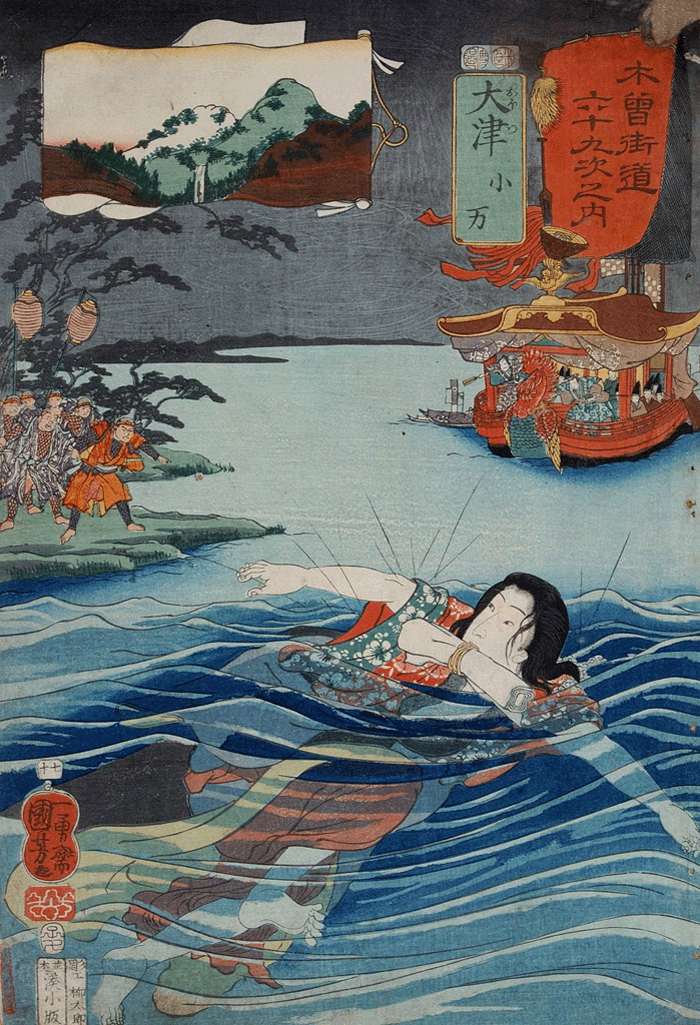
七十 大津 小万
版元:湊屋小兵衛 年代:嘉永5(1852)年7月 彫師:柳太郎
Kn70 国芳作品は、寛延2(1749)年大坂竹本座初演の浄瑠璃『源平布引瀧』の第三段、別名「実盛物語」から構成されています。源義朝亡き後、源氏の白旗は、義朝の弟義賢、奴折平(源氏の侍多田行綱)、そしてその妻「小万」へと託されます。しかしながら、追っ手に迫られ、小万は源氏の白旗を口にくわえて琵琶湖に飛び込み逃げます。その場面を絵にしたのが本作品で、左岸には捕り手の一団が見えています。なお、小万の背後に壮麗な船がありますが、これは竹生島詣の平宗盛の御座船で、一旦はこの船に小万は助けられるのですが、乗り合わせていた斎藤別当実盛に、小万の片腕は白旗もろとも斬られてしまいます。密かに源氏に加担する実盛が白旗を平家に捕られるのを避けるためのことです(詳細は、『カブキ101物語』90頁参照)。
水の流れと水中での人物表現は、国芳の真骨頂です(作品二「板橋」参照)。「大津」の宿場が琵琶湖に面していることから、琵琶湖に飛び込んだ烈女「小万」が主役とされています。標題は、小万の父と子が琵琶湖で漁をすること、また刀は小万の形見であることに因んで、それぞれ周りに描かれているのだと思われます。
Kom70 コマ絵は明らかに源氏の白旗です。英泉・広重版木曽街道の「大津」は、宿場町から琵琶湖を望む風景となっています。国芳のコマ絵は、従来の作品を見てくるとこの水の流れは清水を表現していると推測され、しかも、山並が描かれていることを勘案すると、英泉・広重版とは視線を反対に向けて、逢坂山(逢坂の関)付近にあった関の清水をイメージするものではないでしょうか。保永堂版東海道の「大津」は「走井」を題材としていたので、それとの重複を避けたという見解です。
赤坂 光明皇后
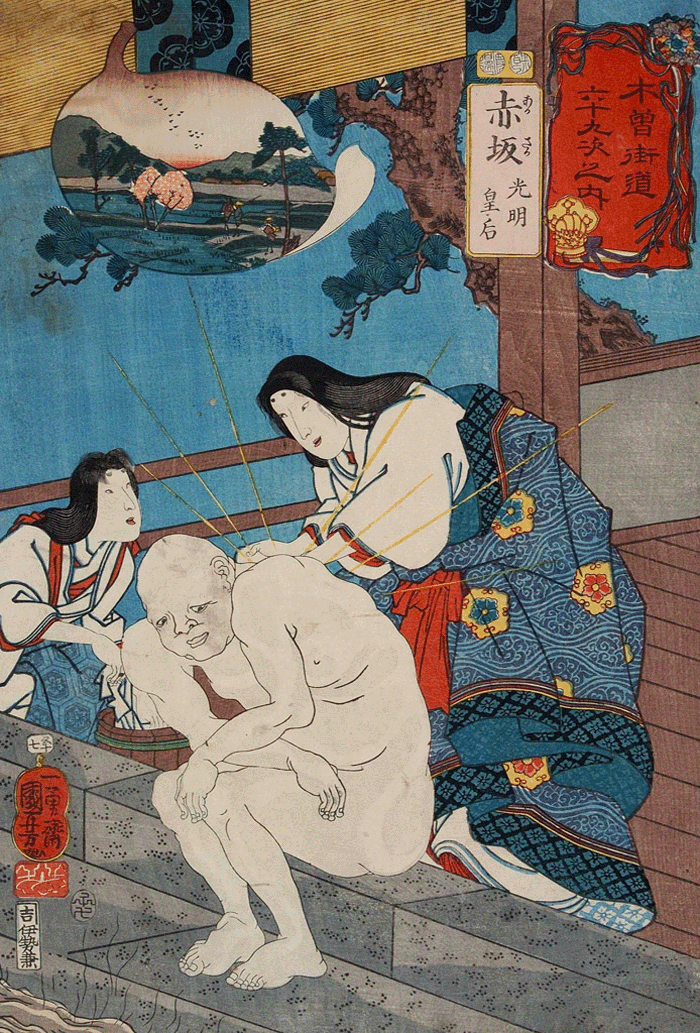
五十七 赤坂 光明皇后
版元:伊勢屋兼吉 年代:嘉永5(1852)年7月
Kn57 光明皇后は、奈良時代、聖武天皇の皇后。藤原不比等と県犬養三千代(橘三千代)の娘で、名は安宿媛(あすかべひめ)。光明子、藤三娘(とうさんじょう)とも呼ばれます。天平元(729)年、皇族以外から初めて皇后となり、以後、藤原氏の子女が皇后になる先例となりました。作品四十五の久米仙人の逸話が同じ時代です。光明皇后は仏教に篤く帰依し、作品五十と係わってきますが、東大寺、国分寺の設立を夫に進言したと伝えられています。また貧しい人に施しをするための施設「悲田院」、医療施設である「施薬院」を設置して慈善を行いました。夫の死後遺品などを東大寺に寄進し、その宝物を収めるために正倉院が創設された外、興福寺、法華寺、新薬師寺など多くの寺院の創建や整備に関わっています。仏教擁護の姿勢は、実は藤原四兄弟等の死を招いた長屋王の怨霊を鎮め、皇位後継の男子を得るためであったとも言われています(井沢元彦『逆説の日本史』二巻413頁以下参照)。
作品は、施薬院で千人の垢を洗うことを誓願し、その丁度千人目、重症の癩病(ハンセン病)患者の膿を自ら吸ったところ、その病人が阿閦如来(あしゅくにょらい)であったという光明皇后の伝説を画題としています。「垢をする」に掛けて、「赤坂」と関連付けたと考えられます。患者の背中から光が発し、如来であることを示しています。先の「美江寺」の美人が今様であったのに対して、こちらは往時の美人に描かれています。
なお、阿閦如来は、大日如来が説法をするのを聞き、仏道を求める誓願をし、永遠の修行の後、仏になった金剛界曼陀羅の五仏のうち、東方の如来に当たります。東大寺の大仏が毘盧遮那仏(ビルシャナブツ)、つまり大日如来であるので、聖武天皇を大日如来に、光明皇后を阿閦如来に擬らえられたとも考えられる伝説です。標題は、
薬玉と宝冠で、光明皇后を指し示しています。
Kom57 コマ絵は、仏教に帰依した光明皇后に因んで、
蓮弁の形です。英泉・広重版木曽街道の「赤坂」は、宿場の東を流れる杭瀬川に架かる土橋から宿場を眺める景色です。一方、コマ絵は田園風景の中を竿を担いだ農民と旅人が歩み、桜の花も咲いています。土橋を渡る前の条里が残る地点か、あるいは宿場を越えて兜(甲)塚辺りからの風景でしょうか。『木曽路名所図会』巻之二の図版「赤坂」の遠景がそれに似ています。観光スポットを考えるならば、やはり同「赤坂」に描かれる観音霊場の谷汲街道辺りからの風光という視点もありえます。もしそうならば、全体図、コマ絵とも仏教繋がりとなるのですが…。
関ヶ原 放駒蝶吉 濡髪蝶五郎
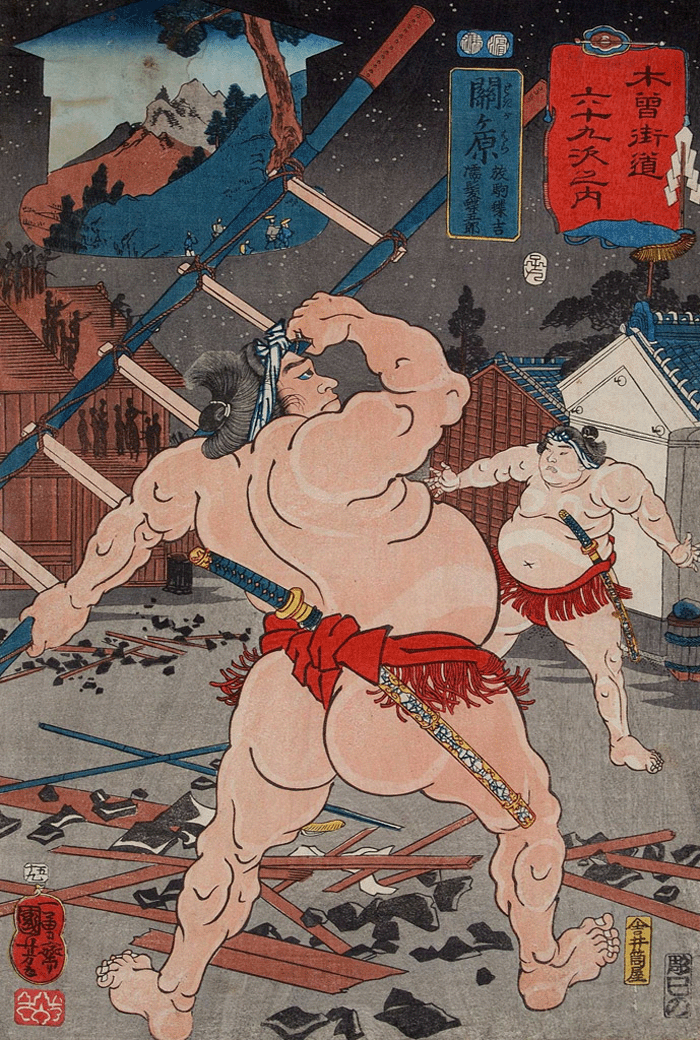
五十九 関ヶ原 放駒蝶吉 濡髪蝶五郎
版元:井筒屋庄吉 年代:嘉永5(1852)年9月 彫師:彫巳の
Kn59 「放駒蝶(長)吉 濡髪蝶(長)五郎」とくれば、人形浄瑠璃および歌舞伎の演目『双蝶々曲輪日記』(ふたつちょうちょうくるわにっき)の登場人物であることが判ります。寛延2(1749)年7月に大坂竹本座で初演され、翌8月に京都嵐三右衛門座で歌舞伎として初演されました。作者は竹田出雲、三好松洛、並木千柳。全九段のうち、有名なのは二段目「角力場」(すもうば)と八段目「引窓」(ひきまど)で、歌舞伎でもしばしば上演されています(『カブキ101物語』190頁)。概要は、大坂名代の力士濡髪長五郎が恩人の子山崎与五郎とその恋人の吾妻(あづま)のために奔走する話です。これに米屋の息子の力士放駒長吉とその姉おせき、山崎の家来筋の南与兵衛とその愛人遊女都(女房お早)などが絡む筋立てです。
国芳の本作品が、長五郎と長吉(いわば、二つの蝶々)が土俵の外で対立する場面を描いているとするならば、四段目の「米屋」の場面に当たります。すなわち、吾妻の一件の決着をつけようとやって来た長五郎と長吉とが喧嘩となるのですが、喧嘩っ早い長吉を何とかしようと一計を案じた姉の思いから、長五郎と長吉とは義兄弟の盃を交わすまでになります。したがって、その前段の喧嘩の場面と見るのが普通でしょう。そして、関取がそれぞれ腹を見せ合うということから、「関(取)の腹」→「関ヶ原」と洒落たと考えられます。標題の周りを飾るのは、
軍配、御幣、化粧舞わしなど角力に係わる道具です。
ところが、作品背景には多くの人々が二階や屋根に上がったりして、遠くを見やっている情景が描かれています。遠くに火の手が上がっているのではないでしょうか。また、手前の長五郎が手にするのは、火消し梯子では?また、夜空に輝くのは、星ではなくて、火の粉では?とすると、文化2(1805)年、江戸の芝神明の境内で相撲取りと火消し(鳶)との間で喧嘩があった、いわゆる『めぐみの喧嘩』(『カブキ101物語』204頁)を翻案しているとも考えられます。長五郎と長吉、あるいは相撲取りと火消し、いずれにしても喧嘩を画題としているのは、「関ヶ原」が天下分け目の戦があった合戦場だからです。その上で、作品が何か火事場の雰囲気になっているのは、大坂夏の陣での大坂城炎上を暗示しているようにも感じられます。ちなみに、『双蝶々曲輪日記』の舞台は大坂です。このように推理するのには、理由があって、先の「埀井」が豊臣秀吉の天下取りを主題にする『絵本太閤記』から画題を採っていることがあります。両作品を一対と考えるならば、「関ヶ原」もやはり豊臣家に係わる事案を題材としていると推理しうるのであって、「埀井」での井戸は水、そして豊臣の天下への出発点、「関ヶ原」での火事場(の喧嘩)は火、そして豊臣の天下の終焉をそれぞれ寓意すると読みとることができるのです。
Kom59 コマ絵の形は、
四神相応の土俵場の意匠ですが、(大坂)城のように見える工夫もあるのではないでしょうか!英泉・広重版木曽街道の「関ヶ原」は牧歌的な宿場風景です。コマ絵の情景は、山近くを旅人が歩いている様子で、おそらく宿場西方の不破の関(古蹟)辺りからの風景でしょう。
坂本 五条坂
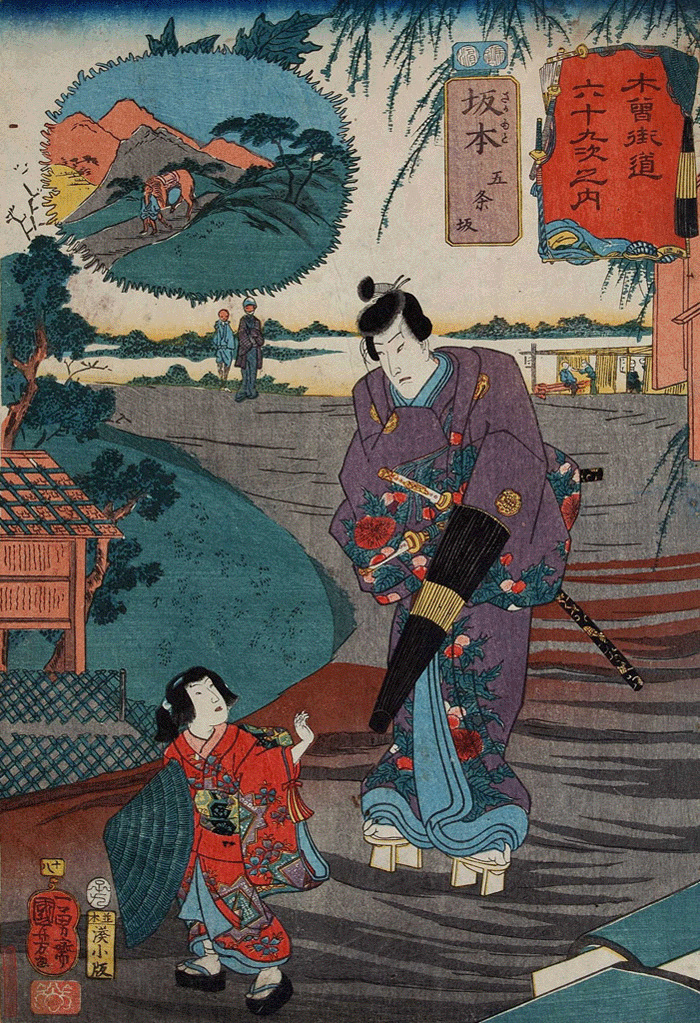
十八 坂本 五条坂
版元:湊屋小兵衛 年代:嘉永5(1852)年9月
Kn18 宿場名と人物名との組み合わせが原則の本シリーズ中、唯一、宿場名と地名の組み合わせになっていますが、「五条坂(の景清)」という意味だと思われます。つまり、平家の残党悪七兵衛景清ではなくて(後述作品五十番)、歌舞伎の所作事(舞踊)としての景清ですよという注意喚起と考えられます。天保10(1839)年3月、江戸中村座、中村歌右衛門の『花翫暦色所八景』(はなごよみいろのしょわけ)が初演です。丹前風の景清が蛇の目傘を持って、文使いの禿に頼んで京清水寺近くの五条坂の遊女阿古屋と馴れ染める所作の場面があり、国芳作品は、まさにそこを描いています(阿古屋については、『カブキ101物語』12頁参照)。ただし、一工夫があって、背景は、日本堤から吉原大門に続く衣紋坂の入り口にあった見返り柳に変えられています。江戸庶民には馴染みの風景です。したがって、ここが五条(衣紋)「坂の本」であることがよく判ったことでしょう。標題は、景清の衣装や脇差しなどで囲まれています。
Kom18 コマ絵の形は、景清の着物の模様ともなっている薊(あざみ)の花です。描かれる風景は、英泉・広重版木曽街道の「坂本」が刎石山と坂本宿を画題としているのに対して、さらにその先の碓氷峠越を『木曽路名所図会 巻之四』「碓日峠 熊野社」の図版を参照して描いているように思われます。
追分 おいは 宅悦

廾一 追分 おいは 宅悦
版元:高田屋竹蔵 年代:嘉永5(1852)年6月 彫師:朝仙 摺師:小善亀
Kn21 「おいは(お岩)」とくれば、四世鶴屋南北の『東海道四谷怪談』に登場する人物で、文政8(1825)年7月に江戸中村座で初演されています。実は、四谷怪談が忠臣蔵をその世界とする物語であるということはあまり知られていません。お岩に呪われる民谷伊右衛門は赤穂浪士でありながら仇討ちに加わらず、吉良縁者の婿になるため、按摩「宅悦」が妻お岩に毒を盛ることを承知するという設定で、まさに不忠不義士です。『仮名手本忠臣蔵』では、雪の中で吉良は首を討たれますが、伊右衛門も雪の中で討たれて血を流すことになり、結末は、怨霊信仰に基づいた同じ趣向となっています。後述作品六十五で再び触れます(詳細は、『カブキ101物語』216頁以下参照)。
作品は、宅悦の毒によって形相が変じたお岩が、隣家に行くため身だしなみを整えようと、鉄漿(おはぐろ)をつけ、鼈甲の櫛で髪を梳くと、髪が抜け落ち、その髪から衝立に血が滴り落ちるという壮絶な場面です。この後、お岩の赤ん坊を大鼠がくわえ去る段があり、それ故、標題の周りは、櫛、掛守り、そして鼠が囲んでいます。「お岩」が「毛」を掴んでいるので、「追分」となります。
Kom21 コマ絵は、やはり、お岩もしくはその恨みのシンボルである鼠をかたどっています。そこに描かれるのは、作品の凄惨な情景とは打って変わって、明月の風景です。ただし、鼠の目のようにも見えますが…。英泉・広重版木曽街道の「追分」は「浅間山眺望」でしたが、すでに「沓掛」で浅間山を描いた当シリーズは、視点を逆方向に取って、東山道と北陸道の別れ道辺りでしょうか、更級(信州)を代表する明月を描いたものと思われます。そのコマ絵と全体図とは、両方とも秋の季節で統一されています。
高﨑 此村大炊之介

十四 高﨑 此村大炊之介
版元:八幡屋作次郎 年代:嘉永5(1852)年5月 彫師:多吉
Kn14 此村大炊之介という人物は、寛政12(1800)年2月、江戸市村座上演、歌舞伎『楼門五三桐』(さんもんごさんのきり)に登場し、真柴久吉(豊臣秀吉)の重臣、実は明の宗蘇卿(そうそけい)と設定されています。真柴家の天下を覆し、日本を乗っ取ろうとする奸計を見破られたため、大炊之介は、自害する直前に、自らの血で記した遺書を掛け軸に描かれた白鷹に託し、一子・石川五右衛門に届けさせます。その遺書によって、五右衛門は自身が大炊之介の実子であることを知り、久吉への復讐を誓い、話は有名な「南禅寺山門」の場へと進行します(詳細は、『カブキ101物語』118頁参照)。
本図は、まさに軸から抜け出た鷹が飛び去ろうとする場面で、大炊之介は唐人服を着た異国風の風俗で描かれています。標題も、大炊之介の異国の持ち物で囲まれています。「高崎」との関係は、「鷹」が「先」に飛ぶという地口のようです。
Kom14 コマ絵の枠は、鳥(鷹)が飛ぶ姿を上方から見た意匠です。コマ絵内の風景は、英泉・広重版木曽街道の「高崎」と照らし合わせると、榛名山を背景とする高崎宿の情景と考えられます。
桶川 玉屋新兵衛 小女郎

七 桶川 玉屋新兵衛 小女郎
版元:住吉屋政五郎 年代:嘉永5(1852)年6月 彫師:須川千之助
Kn07 「玉屋新兵衛 小女郎」は、享保17(1732)年刊、八文字屋自笑・江島其磧(えじまきせき)合作の浮世草子『傾城歌三味線』全五巻に収められる、恋物語の主人公達です。元々は、元禄時代(1688‐1704年)頃からの古い俗謡に歌われた越前三国の湊の遊女小女郎と玉屋新兵衛の情話に取材されています。後に、初代並木五瓶作の歌舞伎『富岡恋山開』(とみがおかこいのやまびらき)として、寛政10(1798)年正月、江戸桐座で初演されています。
画題となっているのは、京の三国出村の太夫小女郎と出会った玉屋新兵衛が「桶伏」にされている様です。「桶伏」とは、遊興費が払えなくなった客に窓を開けた桶を被せ、金策が整うまで路傍に晒す私刑の一種です。どうやら、小女郎は見回りの二人組を気にしながら、こっそりと新兵衛に食べ物・水などを差し入れしているようです。深い仲になったからこその仕草ですね。手前の子犬も、子を成す二人の将来を暗示しているかのようです。「桶」の内「側」にいるあるいは「桶」から「顔」を出す新兵衛ということで、「桶川」に当てはめたということです。標題を囲む酒器・食器は、遊興三昧の新兵衛を象徴するものです。
Kom07 またコマ絵は文と思ぼしきものの上に描かれていますが、新兵衛と小女郎の恋文仕立てと考えればよいでしょう。ところで、コマ絵の中の風景はどこでしょうか。英泉・広重版木曽街道の「桶川」は、「曠原之景」と題して、加納天神へ行く道との分岐点辺りの大宮台地の情景を描いています。英泉・広重版と国芳作品の対応を考慮すると、国芳も同じくその辺りを描いているものと推測されましょう。農家と旅人とのやりとりは削除されていますが、馬子のモチーフは共通しています。
野尻 平井保昌 袴埀保輔

四十一 野尻 平井保昌 袴埀保輔
版元:井筒屋庄吉 年代:嘉永5(1852)年5月
Kn41 「平井保昌(やすまさ)」とは、平安時代中期の貴族、藤原保昌のこと。弟に盗賊として知られる藤原保輔がいます。摂津守となり同国平井に住したことから平井保昌とも呼ばれ、また、武勇に秀で一人武者とも言われ、源頼光と配下の四天王とともに、大江山の酒呑童子退治に加わりました。後に藤原道長の薦めで、女流歌人和泉式部と結婚しています。
『今昔物語』『宇治拾遺物語』によれば、神無月の朧月夜に、平井保昌が一人で笛を吹いて道を行くと、袴垂(はかまだれ)という盗賊の首領が装束を奪おうとその後をつけますが、隙がなく、恐ろしく手を出すことができませんでした。逆に、保昌は袴垂を自らの館に連れ込んで衣を与えたところ、袴垂は慌てて逃げ帰ったと言います。この袴垂と盗賊でもある保昌の弟保輔とが混同され、本作品のように「袴埀保輔」と呼ばれることがありますが、別人です。「野で尻(後)から付いて行く」→「野尻」という理解にしたがって、野で笛を吹く保昌と、木陰から狙う不動明王模様の上着の袴垂とが画題となっています。前述「須原」と一対と考えると、ともに月夜の野原という設定だと思われます。標題は、保昌の笛、袴垂に渡した装束、すすきに囲まれています。
国芳作品のインスピレーションは、『今昔物語』『宇治拾遺物語』から直接導かれたというのではなくて、歌舞伎の『四天王物』(「茨木」『カブキ101物語』28頁)や『土蜘物』(「土蜘」『カブキ101物語』164頁)などを介して考案されたと想像され、たとえば、本作品の場合は「市原野のだんまり」と言われる場面が思い浮かんできます。
Kom41 コマ絵は、保昌の笛二本の間に情景を描く手法です。同時にそれは、朧月のイメージとも感じられます。英泉・広重版木曽街道の「野尻」は「伊奈川橋遠景」です。同じく、国芳のコマ絵も、『木曽路名所図会』巻之三も併せて参照し、その崖部分を描いていると思われます。
守山 達磨大師
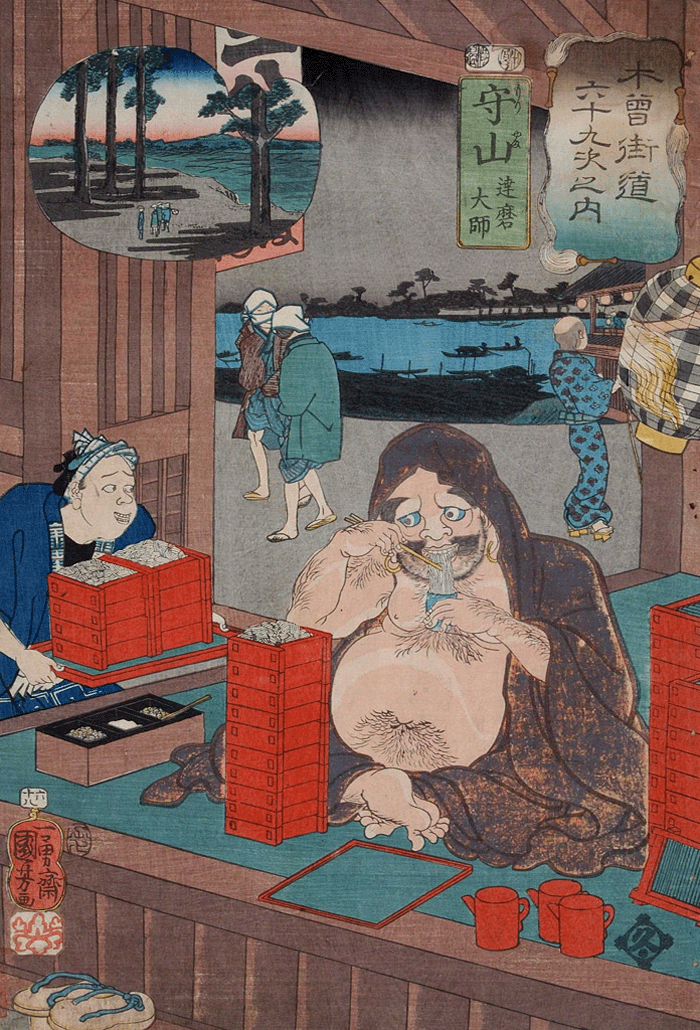
六十八 守山 達磨大師
版元:高田屋竹蔵 年代:嘉永5(1852)年7月
Kn68 「達磨大師」は、5世紀後半から6世紀前半の人。インドから中国に来て、中国禅宗の開祖となりました。なお、その容貌に特徴があって、眼光鋭く髭を生やし耳輪を付けた姿で描かれることが多いです。また、達磨が嵩山少林寺において壁に向かって9年坐禅を続けたとされる「面壁九年」の伝説が有名です。ここから、その修行によって、達磨の手足が腐ってしまったという逸話が起こりました。これが、玩具としてのだるまさんの由来で、縁起物として現在でも広く親しまれています。
宿場名「守山」から、山盛りの蕎麦を発想し、これに「面壁」=「麺へぎ(盆)」の修行で有名な「達磨大師」を当てるという、俗雅一体となった作品となっています。麺を食べる達磨のアイデア自体は、本作品の前に複数存在し、横大判『流行達磨遊び』や平木浮世絵美術館によると読本『風俗大雑書』などにその例があります。弟子の芳年の『月百姿』にも、典型的な達磨の姿を見ることができます。画中の二八蕎麦屋の背後に見えるのは大川で、ひょっとすると、柳橋から猪牙船に乗って吉原に出かけようというのかもしれませんし、店の手前に揃えられた下駄も、座禅を組む達磨には滑稽な履き物と映ります。標題は、画中の提灯の絵にも描かれる、達磨の払子(ほっす)で囲まれています。
Kom68 コマ絵は、頭を右にして寝ている、玩具のだるまさんの意匠です。英泉・広重版木曽街道の「守山」は、三上山を望む守山宿の風景です。国芳のコマ絵は、順当ならば同じく三上山の方向を見るものでしょうが、全体図の達磨大師を勘案すると、視点を反対方向にとって遠く比叡山の方向を見るものではないでしょうか。
御嶽 悪七兵衛景清

五十 御嶽 悪七兵衛景清
版元:住吉屋政五郎 年代:嘉永5(1852)年6月 彫師:須川千之助
Kn50 作品「十八 坂本 五条坂」では、歌舞伎の所作事(舞踊)として『五条坂の景清』を紹介しましたが、 ここでは平家方の侍大将(武将)としての景清が画題となります。「景清」は、平家に仕えて戦い、都落ちに従ったため、俗に平姓で呼ばれていますが、藤原秀郷の子孫の伊勢藤原氏(伊藤氏)です。上総介忠清の七男であり、戦において勇猛果敢だったので、通称として「悪七兵衛景清」の異名で呼ばれました。能・謡曲、幸若舞、浄瑠璃、歌舞伎など多くの作品の題材となっていて、『景清物』と呼ばれる一群を形成しています。国芳の本作品の画題は、謡曲などの『大仏供養』と言われるものです。
すなわち、源頼朝の命を狙って、僧兵姿で東大寺の大仏供養の場に紛れ込んだ景清でしたが、見つかってします。そこで、大仏の肩に飛び乗り難を避け、下方の追っ手を見やります。国芳作品は、この古典的絵画構成を浮世絵に導入したものです。平重衡の南都焼討の際に延焼した大仏殿を、頼朝が再建するという事跡が背景にあります。景清と大仏の背後に、興福寺の五重塔が描かれています。ところで、奈良の大仏は、景清が肩に乗ることができるほどの身丈ということでしょうか、「身丈」→「御嶽」となったようです。標題の周りは、「坂本 五条坂」で確認したように、景清を象徴する薊で囲まれています。
Kom50 コマ絵の形は、景清が平家ゆかりの武将であることから、平家の紋、浮線蝶(揚羽蝶)となっています。蝶の紋は、「二 板橋 犬塚信乃」のところでも一度出てきています。英泉・広重版木曽街道の「御獄」は、宿場の東方山中にあった謡坂村の立場風景でした。国芳作品のコマ絵も、同じ場所を視点を遠ざけて描いたものと推測されます。
なお、歌舞伎の『景清』は、歌舞伎十八番の一つで、市川家を代表する荒事演目です。七代目市川團十郎は、天保の改革による質素倹約令に違反し、天保13(1842)年4月に検挙されますが、その時演じていたのが『景清』でした。その後、江戸十里四方追放が解かれて、最初に江戸で演じたのが、やはり『岩戸の景清』といった具合です。つまり、国芳の本作品の背後にあるのは、團十郎の景清であり、それは幕府の規制に反発する気持ちであると見なければならないと思われます。したがって、頼朝の大仏供養に乗り込んだ景清は、徳川幕府の規制に挑戦した英雄(團十郎)を待望する気持ちを仮託した作品と理解されるべきです。当該作品の版元と彫師の組み合わせが、すでに紹介した作品三十六、三十七の光秀と信長に見立てた作品と同じく、版元は住吉屋政五郎、彫師は須川千之助の組み合わせであることにも注意が必要です。
熱川 武内宿祢 弟甘美内宿祢
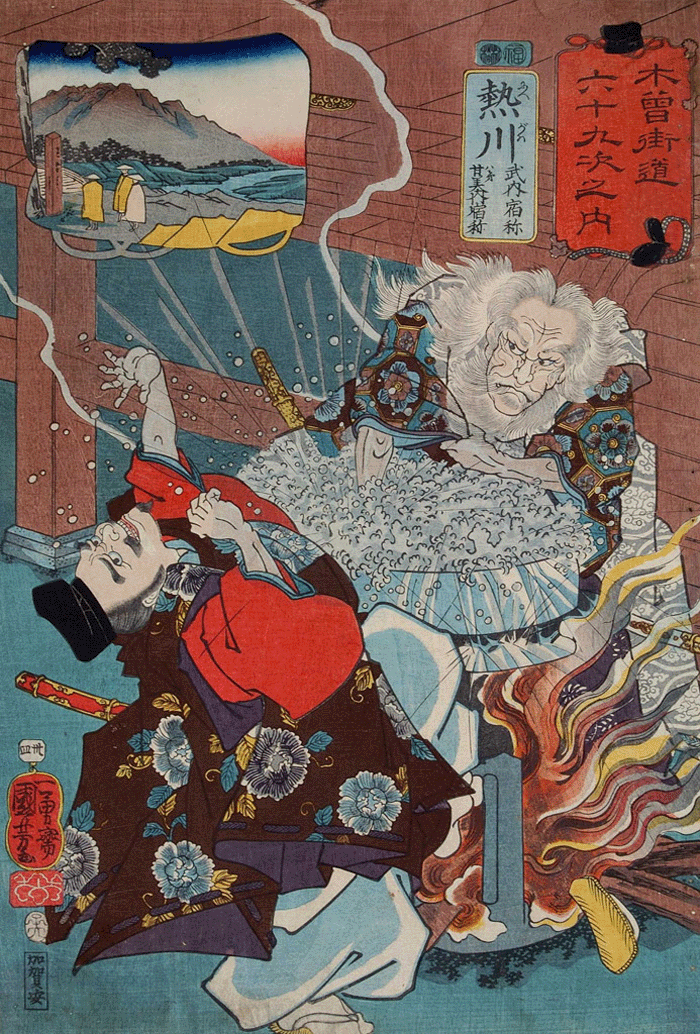
卅四 熱川 武内宿祢 弟甘美内宿祢
版元:加賀屋安兵衛 年代:嘉永5(1852)年6月
Kn34 「武内宿祢」(たけしうちのすくね)は、『古事記』『日本書紀』で大和朝廷初期(景行・成務・仲哀・応神・仁徳天皇の5代の天皇の時期)に大臣として仕え、国政を補佐したとされる伝説的人物です。『日本書紀』によれば、異母弟の「甘美内宿祢」(うましうちのすくね)から謀反の讒言を受けましたが、熱湯に手を入れて正邪を決める探湯(くかだち)を行って濡れ衣を晴らしたとあります。国芳作品は、この探湯の場面を描いています。それは、「煮えた釜」→「熱(贄)川」という地口です。
五月人形では、神功皇后の隣に赤子(応神天皇)を抱いた烏帽子姿の翁が立っていますが、これが武内宿祢で、そのため、標題の周りはその烏帽子で囲まれています。にもかかわらず、当作品で、武内宿祢が烏帽子を被っていないのは不思議ではありませんか。
Kom34 さて、その答えは、コマ絵の形を見れば得心が行くはずです。コマ絵の形が烏帽子となっているのです。そのコマ絵に描かれているのは、「本山」から「熱(贄)川」へ向かう途中にあった、松本藩と尾張藩の境に掛かっていた「境橋」で、木曽の山並みが背後に描かれています。一方、英泉・広重版木曽街道の「贄川」は、『木曽路名所図会』巻之三に図版で紹介されている宿場の旅籠風景です。
なお、武内宿祢が、異母弟の甘美内宿祢から謀反の讒言を受け、探湯を行って濡れ衣を晴らした話が、後世、本シリーズ「十 深谷」に登場した「百合若大臣」(幸若舞い)に変じたという説があります。確かに、大臣として最初に浮かぶのは、武内宿祢です。百合若は、九州、朝鮮半島など海外で武功を挙げた後、島に置き去りにされました。これは、神功皇后の三韓征伐と異母弟による謀反の讒言を想起します。ちなみに、武内宿祢は、「武」(たけし)=筑紫の内宿祢という意味に、甘美内宿祢は、「甘美」(あまみ)=奄美の内宿祢という意味に解され、いずれも、九州ゆかりの名前というのが個人的感想です。
鳥居本 平忠盛 油坊主

六十四 鳥居本 平忠盛 油坊主
版元:高田屋竹蔵 年代:嘉永5(1852)年6月 彫師:朝仙
Kn64 「平忠盛」と「油坊主」の話は、元は『平家物語 巻第六』「祇園女御」に語られていて、白河上皇と忠盛との緊密な関係を示す逸話として知られています。そして、同時に多くの絵師が描く古典的画題でもあります。歌舞伎では、「だんまり」に取り入れられる場面です。
平忠盛は、父親の代から白河院に仕え、荘園の取り立てや瀬戸内の海賊平定などによって、院から篤い信頼を得ていた人物です。平清盛の父と言った方が判りやすいかもしれません…。『平家物語』に紹介される話によると、白河院には祇園社(現在の八坂神社)の近くに祇園女御という側室がおり、ある雨の降る夜、院が祇園社の境内を通ると、青白く光るものがあり、院は鬼か、怪物かと思い、御供の忠盛に斬るように命じました。ところが、忠盛が斬らずに正体を確かめると、社の灯籠の灯に油を注いで歩く承仕法師(じょうじぼうし)でした。この坊主の被っていた藁笠に灯籠の灯が映えて、青白く光って見えただけのことでした。そこで、院は忠盛の沈着さを褒め、褒美に祇園女御を下賜されたという事です。そして、生まれたのが清盛ということで、「清盛は白河院の皇子か?」という伝説が生まれます。祇園社の「鳥居の本」での事件ということで、宿場名「鳥居本」に掛けられました。標題は、灯籠とこぼれた油の間に油坊主が身につけていた藁笠と下駄で囲まれています。
Kom64 コマ絵の意匠は、作品五十「御嶽」の悪七兵衛と同じく、平家の「浮線蝶」紋かとも思えるのですが、ヒゲの数からすると、「対の揚羽蝶」紋ではないでしょうか。英泉・広重版木曽街道の「鳥居本」は、摺針峠の「望湖堂」からの琵琶湖の眺めを描いています。『木曽路名所図会』巻之一にも「磨針峠」の図版がありますが、いずれも、国芳のコマ絵とは異なっているようです。コマ絵は、摺針峠を離れて「鳥居本」の宿場を見遣っているように思われます。
埀井 猿之助

五十八 埀井 猿之助
版元:八幡屋作次郎 年代:嘉永5(1852)年7月 彫師:多吉
Kn58 「埀井 猿之助」とあり、子供が井戸に紐で括り付けられている絵をみると、これは、『繪本太閤記』からの逸話であることがわかります。『繪本太閤記』は、江戸時代中期に書かれた読本で、豊臣秀吉の生涯を描いた『川角太閤記』をもとに、武内確斎が文を著し、岡田玉山が挿絵を入れた全7編84冊の作品です。なお、幕府の禁令に触れ、文化元(1804)年に絶版を命ぜられています。このような作品を題材とするのが、国芳の真骨頂です。
『繪本太閤記』によれば、「日吉丸と号(なづ)けれど猿によく似たりとて人みな猿之助(さるのすけ)とよび習はせり」とあります。その後、尾張国長松の陶器屋(ちゃわんや)に奉公に出、主人の三歳の子供を抱き遊んでいた際、「かかる賤しき業をなし何日まで人に恥かしめられんや」とその子を井の元に連れて行って、井筒の枠に結びつけ、「やがて助る人有るべし暫く其所に辛抱せよ」と言って、三河路を目差して出ていってしまったとあります。作品は、まさに井筒の枠に子どもを結びつけている場面です。木の樽でできた井戸ということから、「樽の井」→「垂井」となっています。この後、日吉丸は、三河国矢矧橋で蜂須賀小六と出会い、天下への道を歩むこととなります。標題は、秀吉を象徴する千生瓢箪で囲まれています。
Kom58 コマ絵は、同様に、瓢箪の意匠です。英泉・広重版木曽街道の「垂井」は、雨の「垂井」宿で、背景は関ヶ原、手前は南宮大社の大鳥居という位置関係が想像されます。コマ絵は、垂井宿から美濃の山々を眺望する図と思われます。『木曽路名所図会 巻之二』の図版「青墓里、長範物見松」に「たるい」が描かれ、参考にされたかもしれません。
妻籠 安倍保名 葛葉狐

四十三 妻籠 安倍保名 葛葉狐
版元:湊屋小兵衛 年代:嘉永5(1852)年6月 彫師:多吉
Kn43 「安倍保名」と「葛葉狐」とくれば、享保19(1734)年10月大坂竹本座初演の人形浄瑠璃『芦屋道満大内鑑』の主人公で、とくに四段目口の「葛の葉子別れ」がよく知られています(『歌舞伎101物語』82頁)。本作品もその場面を画題とし、番付目録『これが江戸錦繪合』では、「大當 朧画大極上無類」と評価され、制作者側の評価として、当シリーズ中の代表作に挙げられています。江戸錦絵合の詳細は、『浮世絵芸術』(163号・2012年)、52頁以下を参照。
話の骨子は次のとおりです。すなわち、安倍保名に助けられた白狐が、自害した保名の恋人榊の前に瓜二つな妹、葛の葉の姿で現れたのが機縁で、二人は阿部野に引き籠もり、子までなします。ところが、ある日、本物の葛の葉が訪れ、白狐はここにとどまれないことを悟り、我が子を残して信太の森へ帰る決意をします。その際、障子に「恋しくば尋ね来て見よ いづみなる信田の もりのうらみ くづの葉」の一首を残して去っていきます。この子こそ、後の陰陽師安倍清明となります。なお、「妻が森に籠もる」→「妻籠」(つまごめ・つまご)と考えられます。
悲しげな人の姿の葛の葉が薄く透けるように描かれ、二重写しで、涙拭く狐の実体が見える表現は、版元側としては自慢の技法だったと思われます。標題の周りは、ススキ、(葛)蔓、桔梗の花で囲まれ、信太の森のイメージです。
Kom43 コマ絵は、葛の葉の形です。中に描かれているのは、英泉・広重版の「妻籠」とほぼ同じ風景です。妻籠宿の手前の峠から、北に見返す視点のはずです。
ちなみに、作品四十一に登場する「平井保昌」の妻・「和泉式部」が前夫・和泉守と別れた後の歌に「あき風はすごくふくとも葛の葉の うらみがほにはみえじとぞ思ふ」とあって、これが上述の歌に影響を与えたという見解もあります。また、安倍晴明の母が橘(たちばな)氏であったことが、橘(きつ)→狐(きつね)となって、晴明の母・狐伝説が生まれたという推理もあるようです。
軽井澤 鎌田又八
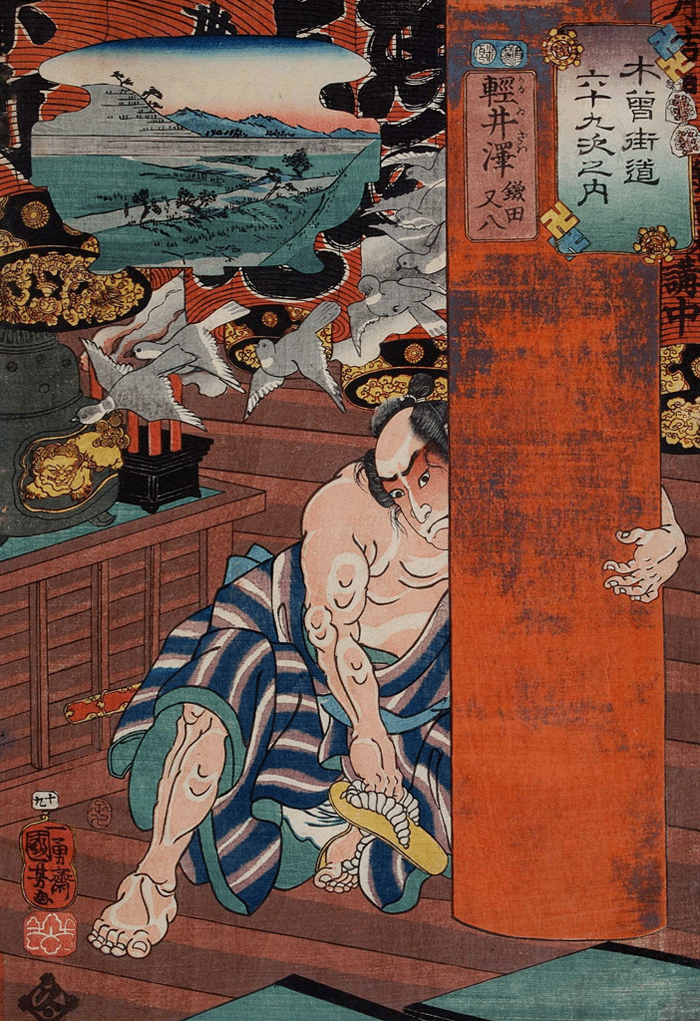
十九 軽井澤 鎌田又八
版元:高田屋竹蔵 年代:嘉永5(1852)年7月
Kn19 鎌田又八は伊勢松坂の出身で、無双の怪力の人物。伊勢鈴鹿に棲む大猫を退治したなどの伝説があります。国芳作品は、文化4年刊の合巻『於六櫛木曽仇討』(山東京伝作・歌川豊国画)の口絵が元になっていて、そこには浅草観音堂の西の柱に又八の指の跡があるとの話が記されています。国芳作品には、又八の怪力によって柱が揺れ、それに驚いた鳩が飛び逃げていく様が描かれています。怪力の又八にとっては、観音堂の柱を揺らすことなど「軽いわざ」→「軽井澤」とでも言うのでしょうか。標題は、寺にちなんで、卍や輪宝で囲まれています。
Kom19 コマ絵の枠は、観音堂内にも置かれている香炉の形です。描かれるのは、英泉・広重版木曽街道の「軽井澤」の夜景を昼間に仕立て直したものと思われます。
なお、先の「坂本」と「軽井澤」とを一体的に鑑賞すると、吉原の見返り柳と浅草の観音堂という江戸っ子にはお馴染みの情景がともに利用されていて、これは明らかに意識的な題材選択と考えられます。つまり、国芳の木曽街道は、多くの場合、見開き一対の作品として、主題や情景などが意図的に関連付けられているということを意味します。ちなみに、江戸で於六櫛が有名になったのは、山東京伝の先の合巻のヒットによるものです(後述作品三十五参照)。合巻や浮世絵などが宣伝広告の役割を果たした好例です。
本庄 白井權八

十一 本庄 白井權八
版元:湊屋小兵衛 年代:嘉永5(1852)年5月 彫師:多吉
Kn11 「本庄」と「白井権八」との関連は、江戸の人々にはすぐに理解できたと思われます。四世鶴屋南北作の歌舞伎『浮世柄比翼稲妻』(うきよづかひよくのいなづま)の序幕で、権八は国許鳥取の奸臣・本庄助太夫を斬って江戸へ出奔するからです。いわゆる「助太夫邸の堀外」の場面です。その場面では、助太夫を斬った権八が白刃を持って堀外に出るとちょうど雨が降っており、権八は家人を白刃で威嚇しながら、下駄を揃えそして履き、蛇の目の傘を奪って、悠々と消えて行きます。国芳の作品が、この場面を念頭においていることが判ります。また、国芳の作品のベースは、やはり、役者絵にあるのではないかと感じられます。なお、直前の斬り合いについては暗示するに止めていますが、このシリーズではよく見られる手法です。標題の周りは、ここに登場する、合羽、竹の子笠、蛇の目傘、刀などの道具で囲まれています。
Kom11 コマ絵の枠は、全体作品の権八の着物に描かれる井桁紋になっています。これは、歌舞伎などで権八を特徴づける記号です。英泉・広重版木曽街道の「本庄」は「新町」に近い「神流川渡場」を主題としていて、宿場風景を描くコマ絵の情景とは全く違うようです。おそらく、コマ絵は、英泉・広重版が通り過ぎてしまった「本庄」の宿場を描いているものと考えられます。地理的に修正したようです。
塩名田 鳥井又助
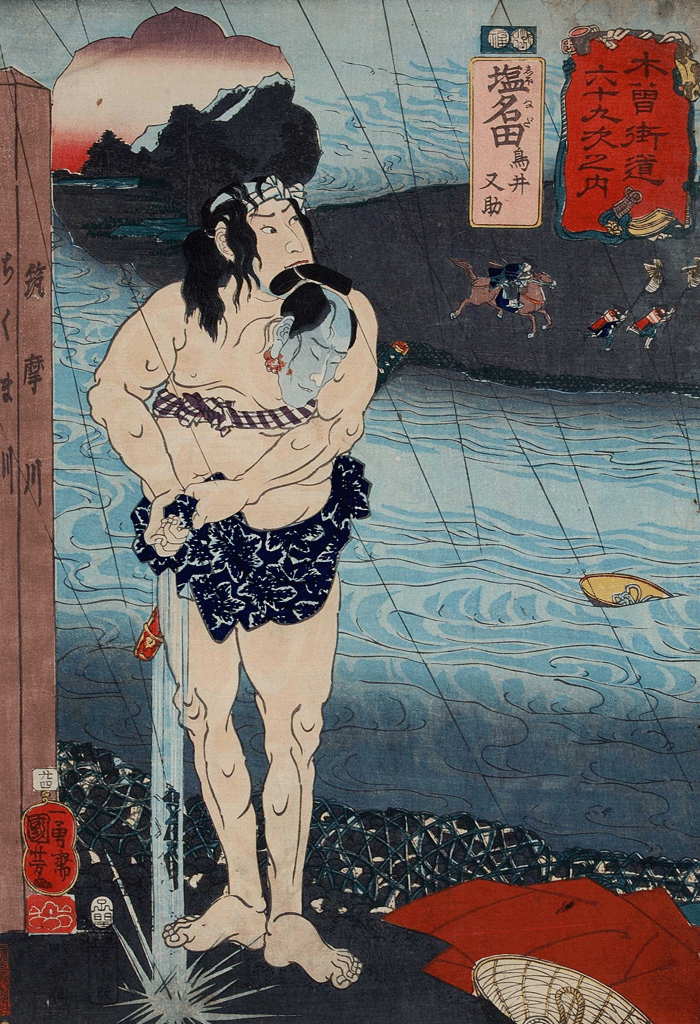
廾四 塩名田 鳥井又助
版元:湊屋小兵衛 年代:嘉永5(1852)年6月 彫師:朝仙
Kn24 「鳥井又助」が登場するのは、『加賀騒動物』と呼ばれる、加賀藩主前田吉徳の死後起こったお家騒動を材料とする人形浄瑠璃・歌舞伎の中です。安永9(1780)年9月京都布袋座『加賀見山廓写本』(かがみやまさとのききがき)に始まります。また、岩藤、尾上、お初など、腰元の世界が仮託されたものに、『加賀見山旧錦絵』(かがみやまこきょうのにしきえ)があります(『カブキ101物語』52頁参照)。
国芳の作品は、多賀大領が、雨中の筑摩川での水馬に際して、多賀家の横領を企てる望月源蔵にそそのかされた鳥井又助によって斬殺される場面です。又助が口にくわえるのが大領の首というわけです。川に流れる笠が殺害がなされた事後を物語っています。標題の鐙(あぶみ)、轡(くつわ)、手綱、馬柄杓は、大領が騎乗していたことの象徴です。「塩名田」が「鳥井又助」になっているのは、地口というよりは、英泉・広重版木曽街道の「塩なた」を見れば判るように、「塩名田」の西側を流れる千曲川と又助の斬殺の舞台・筑摩川とが同名の「ちくまがわ」であるからです。
Kom24 さて、コマ絵の形については、又助の着物の文様にも示される八稜の菱花の意匠もしくはその鏡紋(八稜鏡紋)から来ているのだと思われます。又助が、加賀騒動あるいは加賀見山などの狂言に登上する人物であることから、「加賀」あるいは「加賀見」→「かが(み)」→「鏡紋」と繋がっています。描かれるのは、同木曽街道「塩なた」の風景の手前、宿場に至る駒形坂周辺(駒形神社)の眺めでしょうか。見返せば、流れ山もしくは浅間山外輪山が見えます。
馬籠 竹林定七

四十四 馬籠 竹林定七
版元:住吉屋政五郎 年代:嘉永5(1852)年6月 彫師:大久
Kn44 「竹林定七」は、『仮名手本忠臣蔵』に登場する四十七士の一人。実録では、祖父は中国人で、浙江省杭州武林出身ということから、武林唯七(隆重)と名乗りました。討ち入りに際しては、炭小屋に隠れていた吉良上野介(義央)を間光興が初槍をつけ、唯七が斬り捨てての二番太刀と言われています。『義士銘々伝』の一つに、江戸に下って来る途中、馬子が「馬に乗れ」とからみ、それを断ると、腰抜け侍と見て調子に乗って「詫び証文を書け」と無理難題を言いますが、騒動になることを懸念して、おとなしくその証文を書いたという話があります。この逸話は、大高源五、神崎与五郎のものともされていますが、国芳は、武林唯七(竹林定七)を当てています。なお、作品番号四十五は、四十四の誤りです。
当画中では、馬子は自分の背に乗れと言わんばかりで、対して、竹林定七は刀の柄に手をあて、今にも抜かんばかりの様子です。おそらく、「この馬子め!」→「馬籠」と内心怒っているのかもしれません。義士の中で定七(唯七)をこの絵の主人公にしたのは、赤穂藩馬廻(中小姓)の人物だったから馬に絡めたのでしょうか。標題の周りは、討ち入り装束とその道具で囲まれています。
Kom44 コマ絵の形は、討ち入り道具の一つ、「いろは札」です。各々義士がいろは47文字をそれぞれ一文字づつ付けていました。認識票の役割を果たしています。そこに描かれる風景ですが、英泉・広重版木曽街道の「馬籠」は「峠ヨリ遠望之図」とあり、馬籠峠より、馬籠宿、恵那山を眺望するイメージです。コマ絵はそれをより実景に近い構成に修正して描いています。
大久手 一ツ家老婆
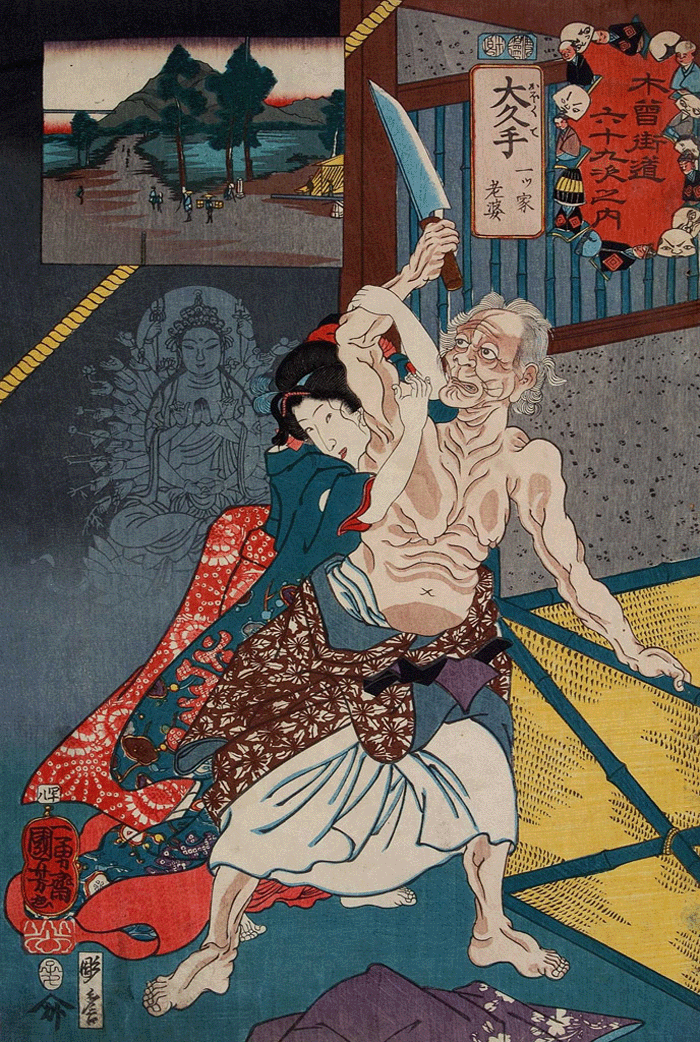
四十八 大久手 一ツ家老婆
版元:八幡屋作次郎 年代:嘉永5(1852)年7月 彫師:多吉
Kn48 「一ツ家」の話は、以下のとおりです。すなわち、用明天皇の時代、浅草浅茅ヶ原と呼ばれる地に、旅人達を泊める一軒のあばら家があったそうです。じつは、この家の老婆は旅人を泊め、石枕で殺害し、金品を奪っていました。千人目の旅人は稚児で、その稚児を殺したところ、その老婆の娘が身代わりとなっていたそうです。老婆は、悲嘆して「姥が池」に身を投げました。以上は、稚児が浅草寺の観音菩薩の化身であったという観音霊験譚が骨子となっています。
国芳作品は、老婆が吊った石を石枕に寝る旅人の頭に落とすためその綱を斬ろうとし、娘が止める場面を描いていて、悲惨な結末は避けたようです。背後に千手観音が薄く見えています。前掲番付目録『これが江戸錦繪合』では、「小結 朧画見立共 大極上々吉」と自画自賛しています。浅草観音は千手観音ではありませんが、「大久手」に掛けて「多くの手」を意識させる趣向です。標題の周りは、浅草名物「とんだりはねたり」という玩具が取り囲んでいます。
Kom48 コマ絵の形は単純な長方形と見え、一ツ家老婆の石枕伝説に因んで、石枕あるいは石その物の意匠と想像したのですが、四ヶ所に切れ込みのような線が入っているところをみると、平木浮世絵美術館資料の言うように、浅草観音に合わせて「卍」のデザインと思われます。英泉・広重版木曽街道の「大久手」は、「ほろ岩」辺りの風景を描いています。国芳のコマ絵は、大湫の宿場から次の宿場「細久手」方向を見ているのではないでしょうか。
鴻巣 武蔵守師直
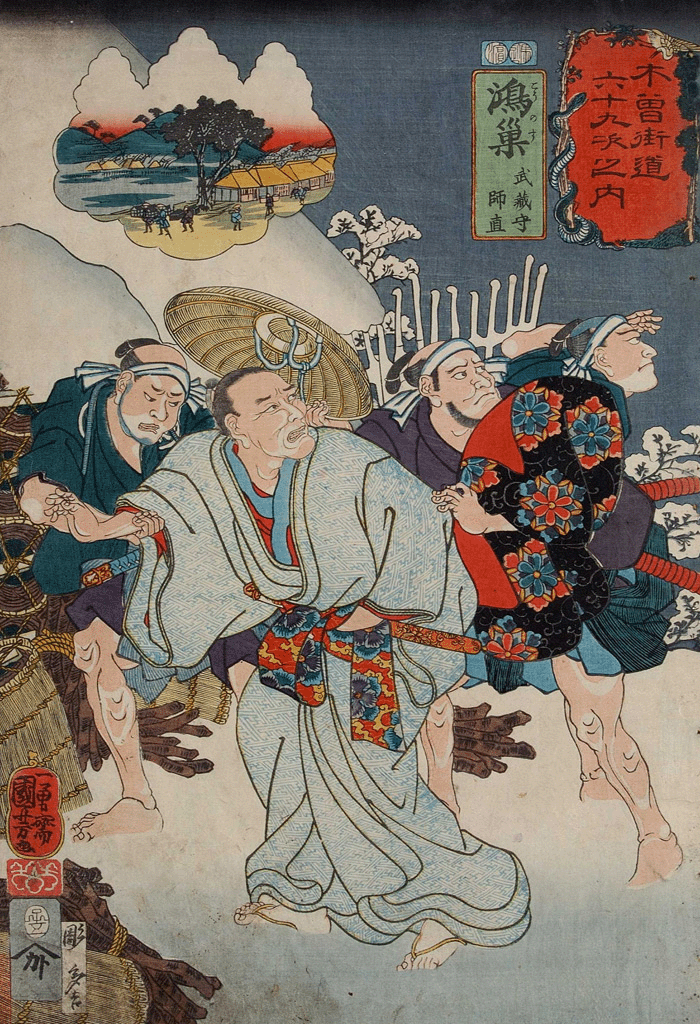
八 鴻巣 武蔵守師直
版元:八幡屋作次郎 年代:嘉永5(1852)年5月 彫師:多吉
Kn08 「武蔵守師直」と言えば、人形浄瑠璃、歌舞伎でお馴染みの『仮名手本忠臣蔵』の仇役「高師直」(吉良上野介)のことです(『カブキ101物語』160頁以下参照)。描かれている場面は十一段目の討入りで、師直の屋敷に討ち入った大星由良之助(大石内蔵助)等四十六の浪士から逃れようと、師直が近習に引かれて炭小屋に隠れるところです。物語のクライマックス直前を描いて、結末を想像させ、庶民心理を作品に引き込もうとの手法です。降り積もった雪と炭の対比が鮮やかです。
「高」師直の「巣」(屋敷)や「すみか」、あるいは「炭」小屋と「鴻巣」とが地口になっています。標題の周りは、コウノトリの巣を狙う蛇ということで、やはり「鴻巣」に掛けられています。いずれにしろ、宿場名「鴻巣」とは無関係な状況設定で、「地口木曽街道」と揶揄されても仕方がないのではないでしょうか?
Kom08 コマ絵の形は桐の文様で、これは高家の家紋です。問題なのは描かれた風景で、英泉・広重版木曽街道の「鴻巣」は「吹上冨士遠望」と題して、鴻巣の宿場をすでに越えた吹上村辺りの風景を描いています。おそらく、国芳版・コマ絵の鴻巣は、民家が並んでいる風情から判断して、英泉・広重版木曽街道を修正して、予定通り、鴻巣の宿場あるいはそこに近い風景を描くことを意図しているように思われます。特段の事情がない限り、国芳のコマ絵は、英泉・広重版木曽街道に倣っているようですが、本作品は違います。
本山 山姥

卅三 本山 山姥
版元:八幡屋作次郎 年代:嘉永5(1852)年7月 彫師:彫多吉
Kn33 「十七 松井田」の山姥は、山の霊としての存在でしたが、ここでの山姥は、以下にあらすじを紹介する、謡曲(能の詞章)に謡われるものです。そして、この謡曲山姥は歌舞伎の所作事にも採り入れられることになります。また、「廿六 望月」の怪童丸の母としての山姥は、歌舞伎『嫗山姥』に集成され発展したものです。
【謡曲山姥】 : 都に、山姥の山廻りの曲舞をつくってうまく演じたことから、百ま山姥(百萬山姥または百魔山姥とも)という異名を取って、人気を博していた遊女がいました。ある時、遊女は善光寺参詣を志し、従者とともに信濃国を目指して旅に出ます。その途中で、越中・越後の国境にある境川に至り、そこから上路山を徒歩で越えようとしますが、急に日が暮れてしまいます。一同が困り果てているところに、やや年嵩の女が現れて、一夜の宿を貸そうと申し出てきました。庵に一同を案内した女は真の山姥であることを明かし、自分を題材にして遊女が名声を得た山姥の曲舞を一節謡ってほしい、日を暮れさせて庵に連れてきたのもそのためだと訴えます。遊女が恐ろしくなって謡おうとすると、女は押し止め、今宵の月の上がった夜半に謡ってくれるなら、真の姿を現して舞おうと告げて、消えてしまいます。
夜更けになって遊女らが舞曲を奏でつつ待っていると、山姥が異形の姿を現します。深山幽谷に日々を送る山姥の境涯を語り、仏法の深遠な哲理を説き、さらに真の山廻りの様子を表して舞ううちに、山姥の姿はいずこかへ消え、見えなくなりました。(the能.comからの引用)
国芳の本作品は、山姥がまさに山廻りの曲舞をする姿を描くものです。標題もそれに合わせて、雲と蔦のつるで囲まれています。そして、「真=本当の山姥」→「本山」となります。
Kom33 コマ絵の形は、奥山を象徴し、山姥の着物の意匠にも使われている蔦の葉です。英泉・広重版木曽街道の「本山」は坂道のイメージで、地理的に似た場所を探せば、桜沢の高巻き道辺りに見つけられます。対して、コマ絵の風景は平坦で、本山宿辺りから木曽の山並みを遠望するものでしょう。
熊ヶ谷 小次郎直家

九 熊ヶ谷 小次郎直家
版元:八幡屋作次郎 年代:嘉永5(1852)年5月 彫師:多吉
Kn09 『平家物語 巻之九』「一二の駈けの事」に、寿永3(1184)年の一の谷合戦の際、熊谷次郎直実、小次郎直家親子と平山季重とが先陣争いをした記述があり、夜明け前の西木戸の城での出来事とされています。白月毛の馬に乗る「小次郎直家」の背後に城の石垣が描かれ、その後ろに波打ち際があることから、この場面を国芳が画題としたことが判ります。「熊ヶ谷」は熊谷一族ゆかりの地ですから、浄瑠璃・歌舞伎『一谷嫩軍記』などにも登場する直実、直家親子を描くことは納得できます。しかし、国芳は、よく知られている直実の話を敢えて避けて、子の直家の方を採り上げました。国芳の木曽街道は全シリーズを通して、周知の人物や事件を意識的に避けることがあり、本件もその事例です。標題は、したがって、直家の武具で囲まれていると考えられます。
Kom09 コマ絵が扇形をしていることについて、直実がわが子直家と同じ年の無官太夫平敦盛を扇で招き寄せたことに因んでと説明されることが多いのですが(平木浮世絵美術館資料)、『一谷嫩軍記』によれば、扇で招き寄せられたのは敦盛と入れ替わった直家自身という設定ですから(『カブキ101物語』24頁・「陣前の場」参照)、扇は直家に直接因縁するものとなります。つまり、扇型のコマ絵は、初陣姿の直家が扇によって絶命することを暗示する、国芳の苦心の工夫と評価すべきです。
扇の中に描かれる風景は、英泉・広重版木曽街道の「熊谷 八丁堤ノ景」と対照すると、荒川左岸の土手「熊谷堤」を進む駕籠かきの姿であることが判ります。英泉・広重版の前景の人物表現をカットした構図です
奈良井 おろく 善吉
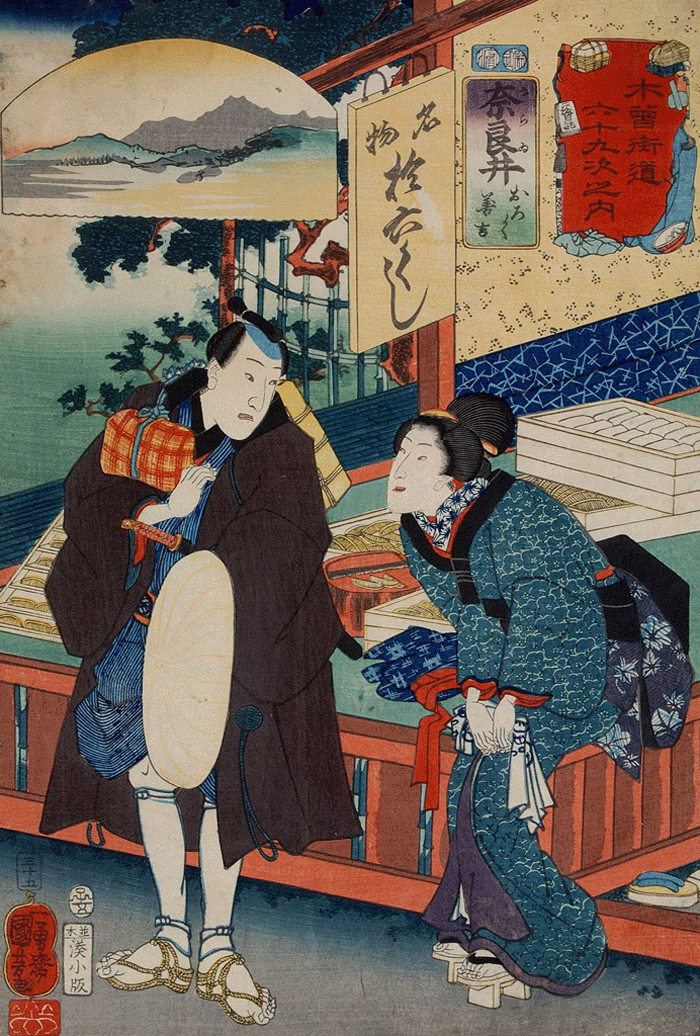
卅五 奈良井 おろく 善吉
版元:湊屋小兵衛 年代:嘉永5(1852)年5月
Kn35 「十九 輕井澤」で引用した、山東京伝の合巻『於六櫛木曽仇討』(文化4・1807年)によって、お六(櫛)は江戸に紹介されましたが、この「おろく(お六)」と蚕屋「善吉」夫婦を中心に据えたのが、曲亭馬琴の合巻『青砥藤綱模稜案』(あおとふじつなもりょうあん)(文化8-9・1811-12年)の後集(前後二つの集に別れていた本)です。絵は北斎が担当し、日本や中国の裁判記録を題材に、青砥藤綱が名裁判で事件を解決する形式です。その後、弘化4(1846)年7月市村座『青砥稿』(あおとぞうし)として歌舞伎で演じられています。
善吉は旅先の木曽路の宿場で知り合ったお六を妻として、木曽路で土産物屋を開いていたところ、善吉の別れた前妻の密通相手(故郷の村長)に冤罪を着せられます。しかし、お六が訴え出て、青砥藤綱が事件の裁きに乗り出して善吉夫婦を救います。国芳作品は、名物「お六くし」の店で出会った、善吉とお六を描いていますが、これは、お六櫛が「奈良井」周辺で名産であったことに因んでいます。『木曽路名所図会』巻之三には、宮腰、薮原、奈良井等に店が多いと記されています。標題を囲むのは、善吉の旅装束と旅道具です。
Kom35 コマ絵は、もちろん、櫛の形を模し、中に描かれるのは、木曽の山々を従える御嶽山の眺望です。英泉・広重版木曽街道の「奈良井」が画題として土産物屋を描く趣旨ならば、その場所は峠より手前の宿場ないしは下の茶屋と解した方が自然で、そこにイメージとして御嶽山が加えられたのでしょう。これは、国芳がコマ絵に御嶽山の眺望を描いたのと同じ思考です。つまり、両作品の構成意図は、ともに同じと考えられます。
小田井 寺西閑心

廾二 小田井 寺西閑心
版元:伊勢屋兼吉 年代:嘉永5(1852)年7月
Kn22 享和3(1803)年初演の歌舞伎『幡随長兵衛精進俎板』、通称「俎板長兵衛」という芝居があります。そこに登場する幡随長兵衛の敵役が、「寺西閑心」です(『鈴ヶ森』の幡随長兵衛については、『カブキ101物語』146頁参照)。物語は、次の通りです。すなわち、寺西閑心という剣客が幡随長兵衛の家にやってきて、手下の土手助が長兵衛の息子の長松に額を怪我させられたと言い掛かりをつけ、土手助に熨斗を付けて台に乗せ進上し、長兵衛が匿っている白井権八を渡せと迫ります(権八については、作品十一参照)。実は閑心は権八の恋人小紫に惚れていて、権八から奪おうという魂胆なのですが、長兵衛は俎板の上に息子の長松を乗せ、「好きに料理してくれ」と言うので、閑心は長兵衛の侠気に感心して引き下がるという筋立てです。
作品では、髑髏模様の着物を着て立つのが閑心で、台に乗せられ進上されたのが土手助の姿です。「お台」に乗っているので、「小田井」という地口になります。背後の菰樽には、国芳の芳桐、酒樽には版元伊勢屋の意匠が見えます。標題にも、閑心の着物模様の髑髏、骸骨が描かれています。
Kom22 コマ絵の形は、髑髏をデザインしたものでしょう。描かれる松並木は、英泉・広重版木曽街道の「小田井」が画題とする「かないか原」(皎月原)の構想図にはないものです。おそらく、『木曽路名所図会』巻之四にも記述される、その下り坂の様子などから、ここは小田井の実景を描写するものと考えられます。コマ絵は同木曽街道「追分」の前面に描かれる街道風景と似ていて、これがこの辺り一般の情景なのだと思われます。
日本橋 足利頼兼 鳴神勝之助 浮世渡平

一 日本橋 足利頼兼 鳴神勝之助 浮世渡平
版元:辻岡屋文助 年代:嘉永5(1852)年5月
Kn01 歌舞伎・浄瑠璃の一系統に『伊達騒動物』と呼ばれる領域があります。たとえば、『伽羅先代萩』(めいぼくせんだいはぎ)、『伊達競阿国戯場』(だてくらべおくにかぶき)などがよく知られています。話の核は、仙台三代藩主伊達綱宗が、吉原通いなどを理由に隠居に追い込まれるという、お家乗取り譚です。その綱宗に見立てられた人物が、「足利頼兼」です。綱宗が身請けを断られた吉原の遊女高尾太夫を手打ちした事件が背景にあって、廓帰りのある日、江戸日本橋に読み替えられる鎌倉花水橋で「浮世渡平」に襲われるのですが、忠義な相撲取りの絹川谷蔵(国芳作品では「鳴神勝之助」)によって救われるというものです。
まさに、国芳作品は、この場面を画題としています。擬宝珠のある日本橋の背後には、富士山、千代田城というこの地のランドマークが描かれ、威勢の良い河岸の男の代わりに渡平に喧嘩を売らせているのかもしれません。木曽街道の出発点「日本橋」に、日本橋の情景という自然な作品構成ですが、実は、このような対応は例外的なものなのです。それは、次回以降のブログの解説によって明らかになっていくと思います。なお、標題の周りが小判で囲まれているのは、綱宗が高尾を身請けする際に積んだ小判に因んでです。
Kom01 さて、コマ絵の形が単純な長方形でないことに気付きましたか?これには理由があって、伊達騒動物の一場面を扱った全体図に挿入されたコマ絵であることからすれば、その枠の形は、おそらく、作品(主人公)ゆかりのものと考えるべきです。標題が小判で囲まれていることから推理して、頼兼に見たてられた綱宗が高尾太夫を身請けする際にその小判を入れた「千両箱」のシルエットと見るべきでしょう。情景描写に関しては、英泉・広重版木曽街道の「日本橋 雪之曙」は、橋の北側部分を東に向いて描いていますが、国芳のコマ絵は日本橋の南側を西に向いて描いています。橋の袂にあった高札場が描かれ、天秤棒を担ぐ河岸の男達や庶民が見えています。何より目を惹くのは槍持ち姿で、北に向かう大名行列を暗示しています。日本橋を大名行列で飾る思考は、広重の保永堂版東海道五十三次と同じです。
岩村田 大井子田畑を潤す

廾三 岩村田 大井子田畑を潤す
版元:伊勢屋兼吉 年代:嘉永5(1852)年7月
Kn23 「近江の大井子」伝説については、すでに国芳には、弘化期の『東海道五十三對 水口』と『賢女烈婦傳 大井児』という先行する作品があって、怪力をもって大石(岩)を動かし、田畑に水を引くことができた快女児として描かれています。『東海道五十三對』では、その詞書きは、『古今著聞集 巻第十』(建長6・1254年)からの引用でした。以下の通りです。
「昔 高嶋といふ所に百姓の娘大井子(おほゐこ)といふ大力の女あり。力ある事を恥て 常にハ出さず。農業の間にハ馬を牽 旅人(りょじん)を乗て活業(なりわい)とす。折節 田に水をまかする頃 村人大井子と水の事を論じ 女と侮り 彼が田へ水のかゝらぬやうにせしかバ 大井子憤りて ある夜六七尺四方なる石を持来り かの水口(みずくち)に置けり。夜明て村人おどろき数人にて取んとすれど 中々動ず悩しに 大井子が仕業ときゝ 詮方なく種々(いろいろ)侘びけるゆへ 彼大石をかるがると引退(ひきの)けり。大力におそれて水論ハ止けるとぞ。今に此地に水口石(ミなくちいし)とて残りける也。」
本作品では、大井子伝説と「岩村田」がいかに係わるかが問題です。「岩を村の田」から退けた大井子という繋がりでしょうか。標題の周りは、鋤、鍬、笠、簑、藁など農作業をイメージする道具などに囲まれていることを考えると、振り袖姿の大井子というのは、やや違和感があります。見開き一対としての作品のバランスも考え、当世風の美人風俗あるいは狂言風に仕立て直して、当シリーズの人気を図ったのかもしれません。
Kom23 コマ絵の形は、大井子の怪力に因んで、農作業の道具から石臼が選ばれています。描かれている風景は、英泉・広重版木曽街道の「岩村田」の遠景部分を拡大するものではないでしょうか。つまり、穀倉地帯佐久平の中心岩村田の田園風景を描くもので、背後の山は、浅間山の山体崩壊(塚原岩屑)によって生まれた流れ山もしくは浅間山の外輪山の様子です。なお、全体図もコマ絵もともに農村風景で統一されています。
鵜沼 与右ヱ門 女房累

五十三 鵜沼 与右ヱ門 女房累
版元:上総屋岩吉 年代:嘉永5(1852)年7月
Kn53 「与右ヱ門 女房累」とくれば、怨霊物の代表格の一つです。作品四十八「大久手 一ッ家老婆」が観音霊験譚であったと同様、累の話は、高僧祐天上人の祈念によって怨霊が解脱した浄土宗(祐天寺)の霊験譚に基づいています。文化4(1807)年の曲亭馬琴読本『新累解脱物語』、文政6(1823)年の森田座夏狂言『法懸松成田利剣』(けさかけまつなりたのりけん)の浄瑠璃所作事『色彩間苅豆』(いろもようちょっとかりまめ)などに展開します。登場人物は、遺書を残して出奔した浪人の与右衛門とその子を身ごもった累(かさね)です。川辺に髑髏が流れてきてから怪談風となります。この髑髏は、与右衛門がかつて累の母菊と密通したときに殺した、累の父助のものでした。この助の霊が乗り移ったことにより、累の顔は醜く変わり、片足も不自由になって与右衛門に襲い掛かります。親の因果によって醜く変じた累は、土橋の柳の立木にて与右衛門に鎌で滅多斬りされます。所作事において、累の襦袢には血汐に見立てた赤い紅葉の模様が施されています。したがって、国芳作品も、まさにこの所作事を絵としたことが判ります。
遠くの橋の上に見えるのは祐天上人でしょうか。先の所作事では事件は木下川(きねがわ)堤で起こりましたが、下総国飯沼の弘経寺(ぐぎょうじ)にいた祐天上人がその累の怨霊を成仏させたということから、「飯沼」→「鵜沼」に当てられているのではないでしょうか。標題は、与右衛門の草刈り鎌など累殺しの場を飾る道具です。
Kom53 なお、『色彩間苅豆』の曲(清元)の最後に「つかみかかれば与右衛門も鎌取り直して土橋の上、襟髪つかんでひとえぐり、情容赦も夏の露消ゆる姿の八重撫子、これや累の名なるべし、後に伝へし物語、恐ろしかりける」とあって、ここからコマ絵の意匠は撫子と解されます。英泉・広重版木曽街道の「鵜沼」は「従犬山遠望」となっています。国芳のコマ絵は、『木曽路名所図会 巻之二』にある図版「岩窟(いわや)観音」に間違いなさそうです。コマ絵に描かれていない木曽川は、前作品五十二と同様、全体図の川(沼)が代替しています。
倉加野 自来也

十三 倉加野 自来也
版元:住吉屋政五郎 年代:嘉永5(1852)年5月 彫師:須川千之助
Kn13 自来也(児雷也)は、文化3(1806)年より刊行された読本『自来也説話』(じらいやものがたり)の主人公で、蝦蟇(がま)や大蛇(おろち)の妖術を使う義賊として語られています。その後、天保10(1839)年より刊行された合巻『児雷也豪傑譚』(じらいやごうけつものがたり)でさらに人気を博し、歌舞伎化に至ります。本図は、谷に落とされた赤ん坊を通り合わせた自来也(三好家浪人尾形周馬)が拾い上げる場面と思われます。画中右下方に家来に抱えられた赤ん坊侶吉(ともきと)が見えています。一方、自来也一行はどこから赤ん坊が落ちてきたのかと上方を眺めている情景です。
なぜ「倉加野」が「自来也」なのかですが、画中に焚き火が描かれていることを考えると、「倉加野」に「暗がりの中」あるいは「暗い野」を読み込んで、そこに自来也一行がいる場面ということでしょうか。標題に、鋸、才槌、がん灯などの盗賊の七つ道具が描かれているのも、暗がりで活躍する盗賊、つまり、暗がり→盗賊→自来也という発想を物語るものです。
Kom13 コマ絵の形は、自来也を象徴する蝦蟇の妖術から、蝦蟇の正面姿を意匠したものです。中に描かれる風景は、英泉・広重版木曽街道の「倉賀野」ではなく、一つ手前の「新町」を参照すると、弁天橋を渡った後、倉賀野までの間の景色と考えられます。英泉・広重版は道を堤方向に曲げてしまっていますが、それを直線に修正したとも言えます。『木曽路名所図会』巻之四によれば、(京より江戸に向かって)「左の方に赤城山見ゆる 富士に似たり」とあります。コマ絵の背景の山は、したがって、赤城山ということになります。
髙宮 神谷伊右衛門

六十五 髙宮 神谷伊右衛門
版元:小林屋松五郎(文正堂) 年代:嘉永5(1852)年8月 彫師:須川千之助・大久
Kn65_2 釣りをする「神谷伊右衛門」、通例は田宮(民谷)伊右衛門と来れば、『東海道四谷怪談』三幕目の「深川隠亡堀(おんぼうぼり)」がすぐに思い出されることと思います。作品二十一の「追分」での事件に引き続いて、帰宅した伊右衛門は按摩の宅悦に殺害されたお岩と折檻し殺害した小仏小平とを戸板の裏表に打ち付け、不義密通の罪を被せ、川に流します。そして、件の釣りの場面となります。日が暮れ帰りかける伊右衛門の前に戸板が流れつきます。引き上げると、お岩の死骸が形相凄く呪うので、突き放すと裏返って、今度は小平の死骸になるという緊迫の名場面です。国芳には、時々見られる手法ですが、まさに戸板返し直前を本作品で描いています。宿場名「高宮」との関連は、「(た)かみや」→「神谷」伊右衛門と繋げているのでしょう。なお、作品中の遠景の小さな人物は、お岩の妹お袖の形式的な夫で実の兄である、直助(鰻曳き)権兵衛かもしれません。標題の周りは、伊右衛門の釣り道具で囲まれています。
Kom65 コマ絵の意匠については、一体として見ればジャバラ折にされた文のようにも見えるのですが、折れ線の山の部分に補助線を入れれば、四本の矢羽根が浮かび上がってきます。すなわち、国芳の全体図が『東海道四谷怪談』から画題を選んでいたことに因んで、「四つの矢」→「四谷」という地口をコマ絵のデザインにしているのです(作品二十四参照)!もともと、塩冶(浅野)家の家紋は、丸に違い鷹の羽ですので、その羽組を壊して、不忠の伊右衛門を象徴させるという意図です。
英泉・広重版木曽街道の「高宮」は、犬上川の仮橋とその向こうにある宿場の風景を南(京)側から描いています。コマ絵の風景も、おそらく、同じ地点から宿場を眺めているように思われます。英泉・広重版が、松の木を額縁のように使ったのとは異なって、一本の大木越しに描いていますが…。
板橋 犬塚信乃 蟇六 左母二郎 土’太郎
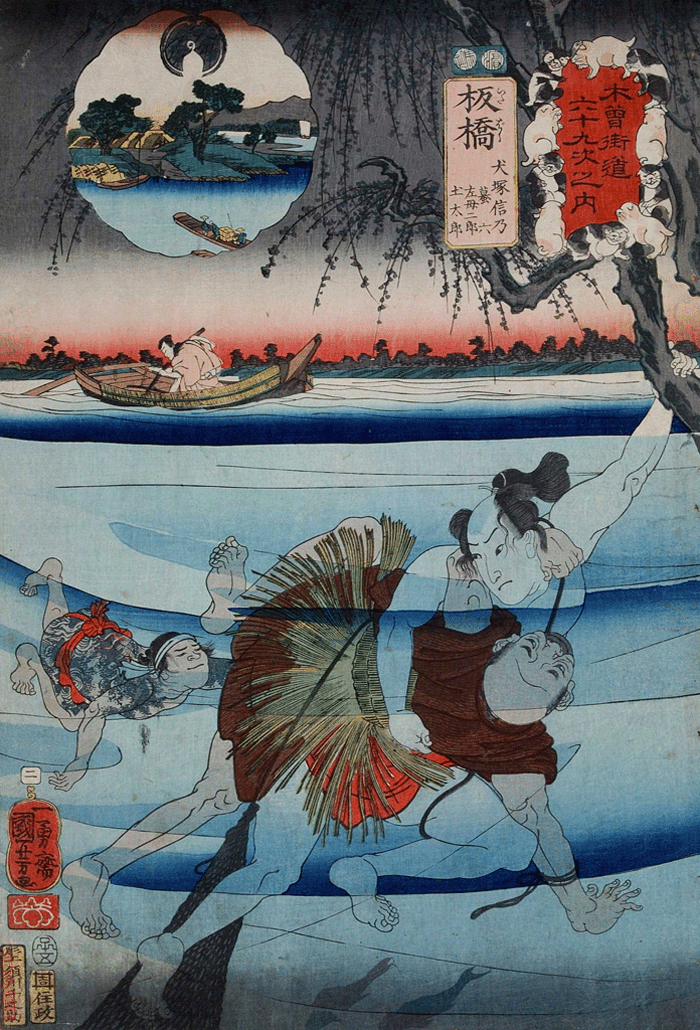
二 板橋 犬塚信乃 蟇六 左母二郎 土’太郎
版元:住吉屋政五郎 年代:嘉永5(1852)年5月 彫師:須川千之助
Kn02 後で再度触れますが、コマ絵に戸田川の渡しが描かれています。それに対応して、全体図では、戸田川の上流神宮(かには)川を舞台とする曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』第三輯巻之二の場面が画題とされました。すなわち、八犬士の一人で孝の玉を持つ「犬塚信乃」が、川にわざと落ちた船頭「蟇六」を助けようとするに乗じて、「土’太郎」が信乃の水死を謀り、その間に関東公方足利家の家宝・村雨丸を「左母二郎」がすり替え奪うというものです。画中手前の抱えられた男が蟇六、背後から信乃に近づく刺青の男が土’太郎です。水面下の水流を藍の濃淡で表現したところは、識者に好評です。標題は八犬伝に因んで10匹(?)の子犬に囲まれています。
Kom02 コマ絵の枠の形は、女の子として育てられた信乃が子供の頃着ていた着物の「蝶」模様を意匠するものです(『南総里見八犬伝』第二輯巻之五参照)。これによって、「日本橋」に引き続き、全体図の場面・人物とコマ絵とが深く関連していることが明らかになります。このことは、以後、コマ絵の意匠を考える際の重要なヒントにもなります。先に触れたように、コマ絵は「板橋」と「蕨」の間にあった戸田川を描くもので、「板橋」を一つ飛ばして、英泉・広重版木曽街道の「蕨之驛 戸田川渡場」が元になっていることが判ります。ただし、対岸の馬や旅人達など詳細部分は省略されています。
この時点では、全体図の情景とコマ絵の風景とは一応関連していると言えましょう。
加納 坊太郎 乳母

五十四 加納 坊太郎 乳母
版元:八幡屋作次郎 年代:嘉永5(1852)年7月 彫師:(須川)千之助
Kn54 田宮「坊太郎」は、寛永18(1641)年、四国の丸亀で親の敵を討ったといわれる少年です。ただし、江戸時代の敵討ち物戯曲の主人公として活躍する伝説上の人物と考えられています。人形浄瑠璃や歌舞伎、講談などで広まり、『金毘羅利生記物』として名高い話です。天明8(1788)年、司馬芝叟ほか作の『花上野誉石碑』(はなのうえのほまれのいしぶみ)において、それまで二人だった子供が一人になり、名前も坊太郎になりました。その四段目、坊太郎の乳母お辻が、身命を捧げて、金毘羅権現に坊太郎の仇討ち成就を祈願する「志度寺」(しどうじ、しどでら)が有名です。蓮の花びらが風に舞う中、少年「坊太郎」と水垢離姿の「乳母」お辻を描く国芳作品も、やはりこの場面を念頭に描いているようです。
坊太郎、乳母お辻と宿場名「加納」との関係ですが、金毘羅権現の御利益で坊太郎の仇討ちが成就したことを捕らえて、仇討ち「叶う」→「加納」と考えます。江戸時代、伊勢参りのオプションとして金毘羅参りは盛んでしたし、広重の保永堂版東海道「沼津」に描かれているように、代参も広く行われていました。標題の周りは、金毘羅権現の眷属である天狗を意識して、雲(風)と天狗の羽団扇でしょうか。
Kom54 コマ絵の意匠は、やはり、天狗の羽団扇です。英泉・広重版木曽街道の「加納」は、加納城を遠景に江戸に向かう大名行列姿を東海道を進むがごとくに描いています。国芳のコマ絵は、手前の茶屋に目を向けると英泉・広重版と同じ街道筋の加納宿に近い辺りを描いたことになります。
和田 和田兵衛
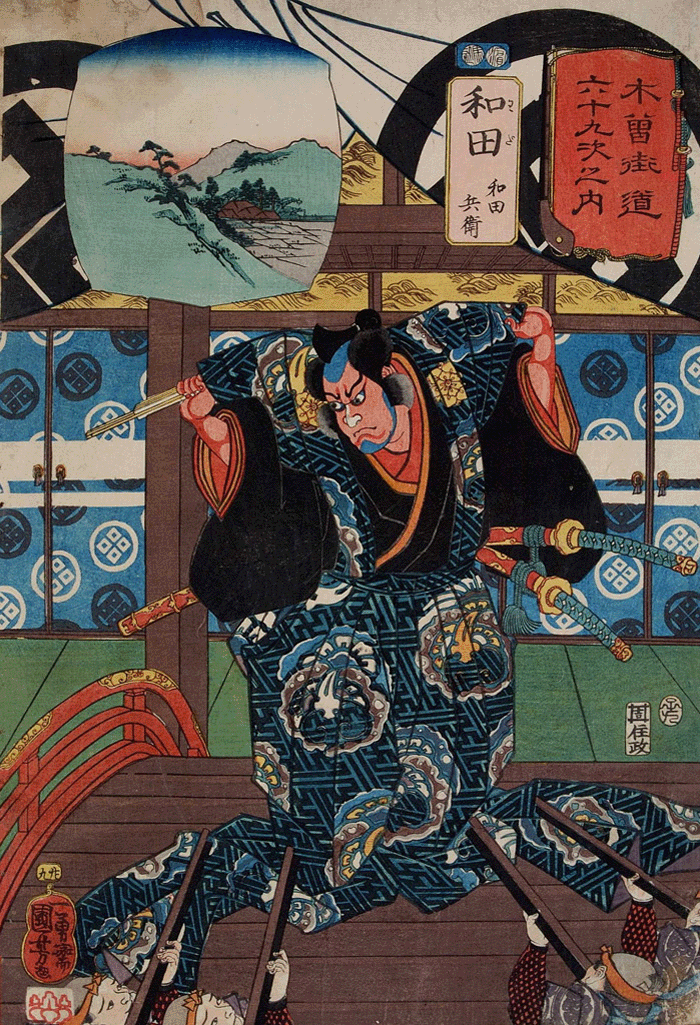
廾九 和田 和田兵衛
版元:住吉屋政五郎 年代:嘉永5(1852)年9月
Kn29 「和田兵衛(秀盛)」は、明和6(1769)年12月竹本座で浄瑠璃から歌舞伎化され、初演された『近江源氏先陣館』(『カブキ101物語42頁参照』)で活躍する武将です。なかでも「盛綱陣屋」が有名で、本作品もその一場面を描いています。『近江源氏先陣館』は、大坂冬・夏の陣を脚色して、時代を鎌倉時代に変え、真田信幸・幸村兄弟を佐々木盛綱・高綱兄弟になぞらえ、大坂城幸村方の猛将後藤又兵衛を和田兵衛として登場させています。本作品は、その和田兵衛が敵方となった盛綱陣屋に、生け捕りになった高綱の子・小四郎を救いに来る場面です。したがって、盛綱家臣に取り囲まれ銃を向けられています。なお、陣幕、襖の文様は、佐々木氏の四つ目の家紋ですが、真田氏の六文銭をも暗示しています。
言うまでもなく、その「和田兵衛」と宿場名「和田」が掛けられています。標題の周りにも刀にくわえて鉄砲が描かれていますが、これは、場面変わって、盛綱が高綱の首実検で嘘の証言をした責任をとって切腹しようとした際、再び、和田兵衛が登場し、鎧櫃の中に潜む、味方盛綱を監視する北條時政(徳川家康)の忍びを鉄砲で撃ち殺すからです。
Kom29 コマ絵の形は、「盛綱陣屋」の話の流れを考えれば、鎧櫃の意匠と考えられます。そこに描かれるのは、英泉・広重版木曽街道の「和田」を見るまでもなく、「和田峠」を見通す風光です。ちなみに、中山道広重美術館資料は、和田兵衛が「四斗兵衛」の異名を持つので、コマ絵の形を酒樽ではと提案しています。結論には賛同しませんが、コマ絵の意匠が何だろうかと述べ合うのが、当時も今も、浮世絵鑑賞の楽しさであることは間違いありません。
新町 獄門庄兵衛 黒舩忠右ェ門

十二 新町 獄門庄兵衛 黒舩忠右ェ門
版元:伊勢屋兼吉 年代:嘉永5(1852)年6月
Kn12 国芳は、「新町」という宿場名から、大坂新町橋を連想し、そこを舞台とする『黒船忠右ェ門物』と呼ばれる浄瑠璃、歌舞伎の一系統を題材にしました。「獄門庄兵衛」と「黒舩忠右ェ門」の両名による、義理人情からの談判を意味する「立引」(たてひき)が画題です。歌舞伎では、初代姉川新四郎が、享保3(1781)年、大坂嵐座『黒船出入湊』で自作自演したのが始まりと言われています。黒船役の新四郎が被った投げ頭巾は、姉川頭巾と呼ばれ、後世にも伝えられ、国芳もその姿に従って描いています。当該作品も役者絵がベースになっているということです。忠右ェ門の衣装は黒地に菊花と浪の文様をあしらい、庄兵衛は碁盤に黒白の石を散らし、共に意地を張り合った豪奢な姿です。標題は、尺八、手拭い、下駄、太刀などの侠客が身につけるもので飾られています。
Kom12 コマ絵の形は、「大宮」でも描かれていた梅の花と判断されます。新町橋は、新町遊廓への通路で遊廓が桜の名所でもあることを勘案すると、コマ絵は桜の花の方が相応しいとも思えるのですが、舞台となった難波津を代表する梅の花が選ばれたようです。任客を花で飾る浮世絵はよくありますが、その際、江戸の桜に対して難波の梅という対比もあることでしょう。そして、コマ絵の風景は、英泉・広重版木曽街道の「本庄」と対比すると、「神流川渡場」の舟渡しの部分を拡大して構成したことが判ります。神流川は、「新町」の宿場に近いので、この選択は自然です。背後の山は、赤城山でしょうか。
河渡 旅座頭
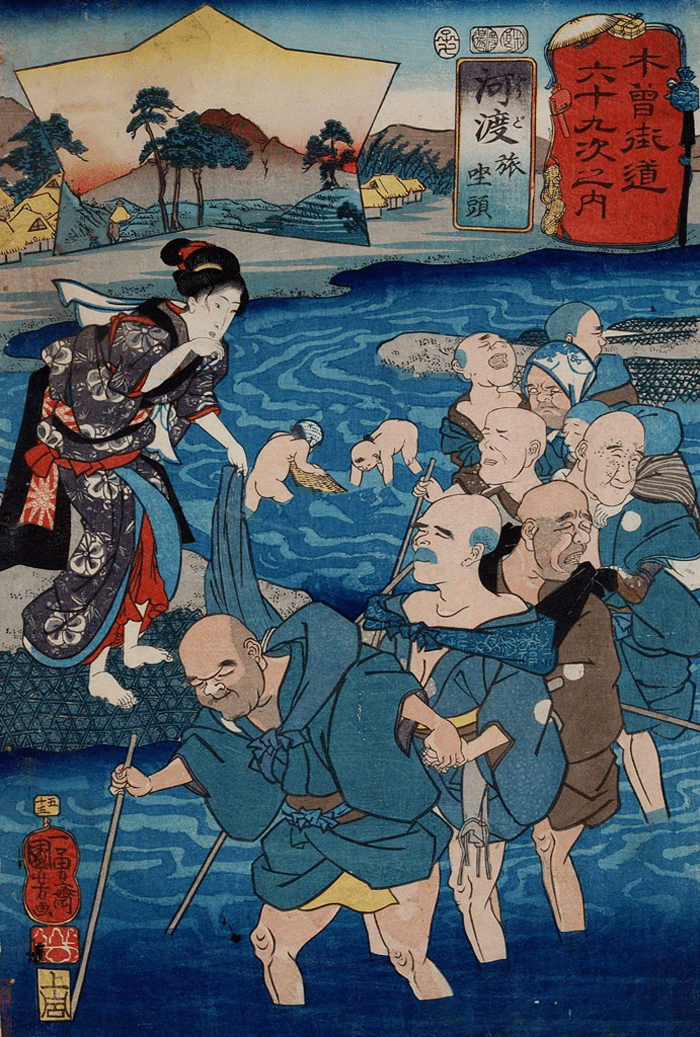
五十五 河渡 旅座頭
版元:上総屋岩吉 年代:嘉永5(1852)年7月
Kn55 「座頭」とは、江戸期における盲人の階級「検校、別当、勾当、座頭」のそれです。ここから転じて按摩、鍼灸、琵琶法師などへの呼びかけとしても用いられています。江戸時代、幕府は障害者保護政策として職能組合「座」を基に障害者に対し排他的かつ独占的職種を容認することで、障害者の経済的自立を図ろうとしました。たとえば、平曲、地歌三味線、箏曲、胡弓等の演奏家、作曲家、鍼灸、按摩、高利の金貸しなどが公認されました。
国芳作品は、「座頭の河渡り」あるいは「盲人の川越え」と呼ばれる画題を宿場名「河渡」に掛けて描いています。当時は、ユーモラスな光景として理解されており、画中の洗濯する女性や魚捕りに遊ぶ子供達も日常のこととして感じているのでしょう。目が見えないので、作品四十五「落合」の久米仙人と晒女のような出会いには至りません。標題は、笠、筆、草鞋、道中脇差しなど、旅道具に囲まれています。
Kom55 江戸時代に和暦の月の大小や暦注などを文盲者にも理解出来るように絵や記号等で表現した暦があり、「座頭暦」と呼ばれ、月日はサイコロの目と星の数でを示しました。「絵暦」の一種と言えます。コマ絵の星形は、確実ではありませんが、その「座頭暦」に因んだ星型かもしれません。あるいは、単純に、目が見えないことを闇夜(の星)に例えているのかもしれません。英泉・広重版木曽街道の「河渡」は、『木曽路名所図会 巻之二』を参照し、題名も同じ「長柄川鵜飼舩」です。国芳の全体図の川が長良川を例えているならば、コマ絵と合わせると同じ風景となります。また、描かれた山に意味があるならば、伊吹山が見える地点でもあります。
上松 江田源三
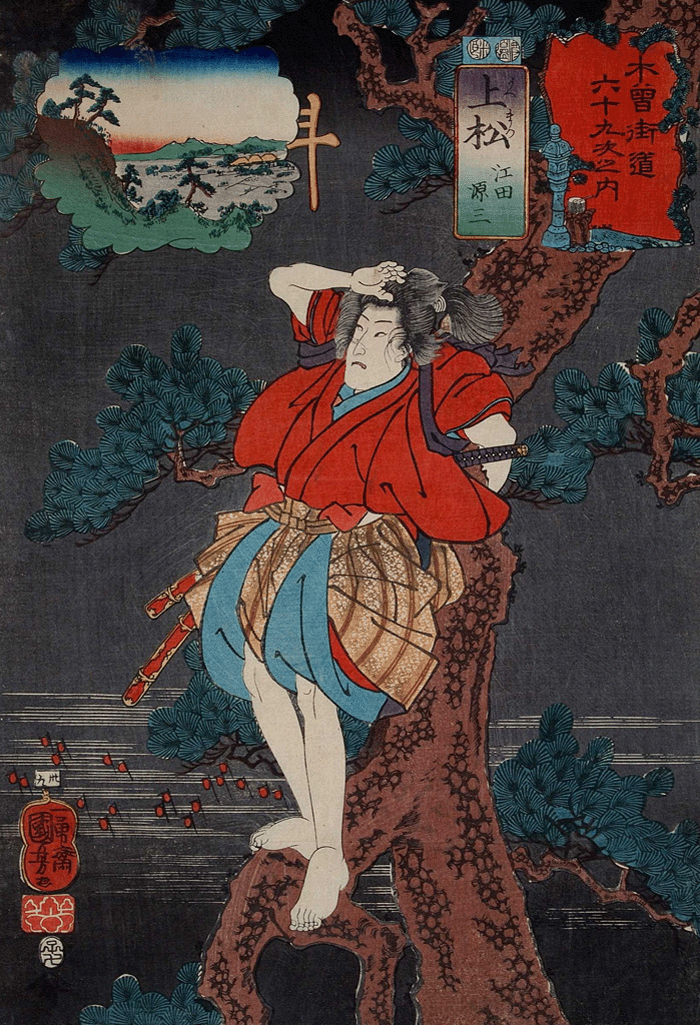
卅九 上松 江田源三
版元:八幡屋作次郎 年代:嘉永5(1852)年7月
Kn39 源頼朝から源義経暗殺の命を受け土佐坊昌俊が鎌倉を発つことを急報したとされているのが、『義経記』では「江田源三」です。そして、作品卅二での「弁慶尻馬」の後、結局、土佐坊は手勢を率いて、京堀河の館に源義経を襲うことになります。これらは、『平家物語』(巻十二、土佐房被斬)、同(剣巻)、『源平盛衰記』(巻四十六、土佐房上洛)、『義経記』(巻四、土佐坊義経の討手に上る事)等に記されています。
国芳作品は、おそらく、鎌倉から急報した江田源三と事後に起こった土佐坊の堀河夜討で、いち早く義経の郎党に知らせた下部の喜三太とを一つのイメージとして創作したものと思われ、江田源三が松の木の上で物見する姿は、「上松」の地口に合わせた結果です。なお、国芳は、「上松」に「うえまつ」とルビをふっていますが、これは「あげまつ」の誤りです。標題の周りは、松、灯籠、手水桶など堀河の夜討ちの舞台飾りと考えられます。
Kom39 コマ絵は、鬼の顔を意匠しています。コマ絵から覗いている「斗」と併せると「魁」(さきがけ)という字になる仕掛で、江田源三の急報・活躍を意味します。英泉・広重版木曽街道の「上松」は、「小野の滝」を描いてます。国芳作品のコマ絵の山が木曽御嶽山ならば、「上松」に向かう途中木曽谷から唯一御嶽山が見える場所からの眺望でしょう。ただし、『木曽路名所図会』巻之三にある「小野瀧」の図版を参照したようにも見えます。英泉・広重版の趣旨を尊重して、後説としておきます。
安中 清玄

十六 安中 清玄
版元:加賀屋安兵衛 年代:嘉永5(1852)年6月
Kn16 人形浄瑠璃・歌舞伎に『清玄桜姫物』という一系統があり、それは、清水寺の僧清玄が、参詣に来た桜姫の容色に迷い堕落し殺され、その執念が桜姫に付きまとうという内容を骨子とします。破れ衣に破れ笠の姿になった清玄が庵室で一心に妄信し、使いの男に殺される「庵室」の場が有名です。古くは土佐浄瑠璃に『一心二河白道』(いっしんにがびゃくどう)があり、同じ外題で、元禄11(1698)年に、近松門左衛門によって歌舞伎化されています。その他多くの作品があります(『カブキ101物語』108頁参照)。
国芳作品も、この庵室の場を絵にしていて、不動明王の前でさえ桜姫に執着を募らせる清玄とその貧しい庵室の模様を表現しています。窓の外に一人の男が葛籠を背負って歩いてきますが、この葛籠の中に桜姫が押し込まれています。結果、清玄と桜姫は庵室で出会いますが、清玄はこの男に殺されてしまいます。国芳は、この緊迫する場面の直前を描いて、この後に展開する結末を予告するに止め、庶民心理を焦らせているのかもしれません。なお、「庵室の中」の場面ということで、「安中」となります。標題は、清玄が僧であるので、経文、経机、香炉などの仏具で囲まれています。
Kom16 コマ絵の枠は、一心に妄想を募らせる清玄に合わせて、「心」の字形となっています。英泉・広重版木曽街道の「安中」は、宿場を越えた「琵琶窪」「原一村」(『木曽路名所図会』巻之四)辺りを描いたと推測されますが、コマ絵に描かれる風景は、同じ風景を英泉・広重版とは視点を逆にして描いているようです。背景の妙義山の上に日没直後の三日月が浮かぶ情景です。(心という文字の点と点との切れ目でしょうか?)
福島 浦嶋太郎

卅八 福島 浦嶋太郎
版元:井筒屋庄吉 年代:嘉永5(1852)年5月
Kn38 次の宿場「上松」近くの木曽川に「寝覚めの床」と言われる岩場があり、『木曽路名所図会』巻之三によれば、「浦島が釣をすれし所という俗説あり」と記述され、さらに、浦島に関して日本書紀などに記載はあるけれども、この地に至ったという文言は見えないとしています。ただし、この地が木曽街道中の名所であることは間違いありません。国芳は、「福島」と「浦嶋」とを掛けて、前倒しして、ここで浦島太郎伝説を画題としたようです。なお、作品番号卅七は、卅八の誤りです。
作品は、釣り竿を持つ浦島が、亀の気によって映し出された竜宮城を夢見しているところで、東海道四日市あるいは桑名にあった蛤の気による蜃気楼伝説と同種のものと考えられます。描かれる亀は海亀ではなく陸亀ですから、木曽川の「寝覚めの床」が場所として想定されています。作品卅四の「武内宿祢」が、やはり、浦島のモデルであるという見解もあります。山中の木曽川と海での浦島とは一見無関係のようですが、木曽川が伊勢湾に流れ込むことを考えれば、繋がりは否定できません。塩土老翁(山幸彦あるいは神武東征を助けた者)、武内宿祢(蘇我氏の祖、応神の補佐)、浦島太郎(亀を助ける)には、補弼する老人という共通性があって、相互に深い関係がありそうです…。なお、標題の周りは、浦島の釣り道具で囲まれています。
Kom38 コマ絵の形は、画中に描かれていた亀と考えら、頭を左にしています。。英泉・広重版木曽街道の「福島」は関所の西側からの情景を描いていますが、国芳は、さらに離れた所からの関山の風景ではないかと思われます。街道の両側から山が迫る特徴がよく出ています。なお、『木曽路名所図会』巻之三にも「福島関隘」と題する図版があり、「遠州荒井の如し」とも記述されています。
大宮 安倍宗任
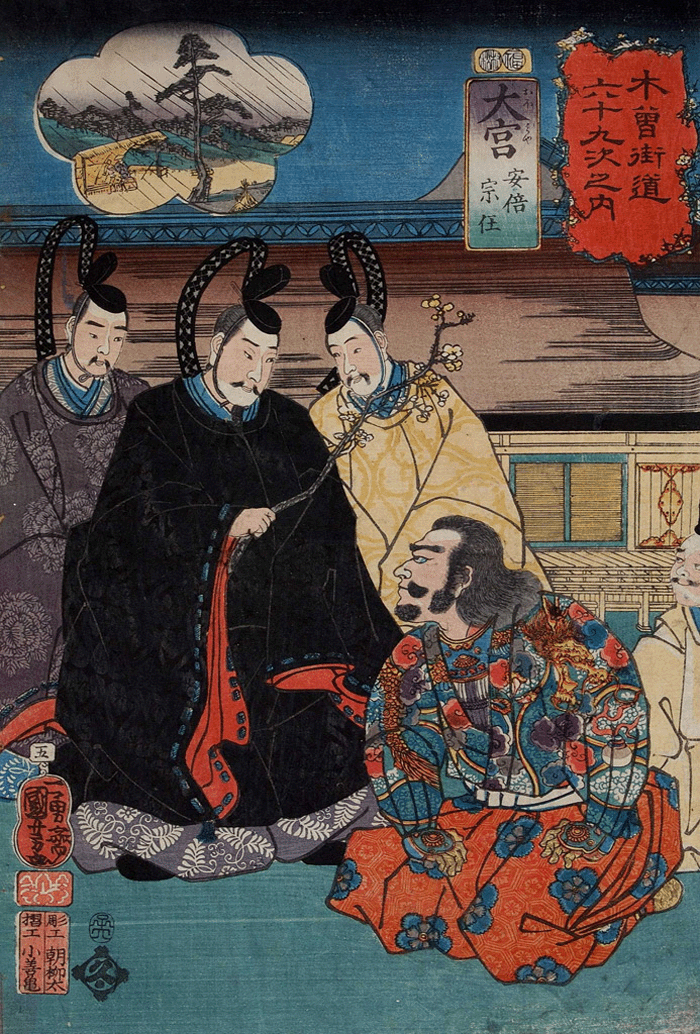
五 大宮 安倍宗任
版元:高田屋竹蔵 年代:嘉永5(1852)年6月 彫師:朝柳太 摺師:小善亀
Kn05 安倍宗任は、平安後期、奥羽の武将です。奥州奥六郡(岩手県内陸部)を基盤とし、父・頼時、兄・貞任とともに源頼義、義家と戦った前九年の役(1051~1062年)では、貞任と並んで、安倍軍抵抗の指揮をとりましたが、厨川柵(くりやがわのき)の戦いに敗れて降伏し、捕虜として都に連行され、後に九州に配流となっています。都に上ったとき、奥州の俘囚は花の名など知らぬだろうと侮蔑した公家が梅の花を示し、「宗任、これはいかに」と聞くと、「我が国の梅の花とは見たれども、大宮人はいかがいふらん」と歌で答え、都人を驚かせたという話が、『平家物語 剱之巻』(いわゆる『平家物語』とは別の物語)に紹介されています。
鋭い目を向け、厳つい髭姿に梅鉢模様の袴を着けた宗任に対して、梅の枝を持つ若い公家を国芳は対照的に描いています。京に対して東国の江戸っ子には痛快な話でしょう。すでに気が付かれているでしょうが、宗任から梅の故事、そして「大宮人」の歌を引き出し、宿場名の「大宮」に繋げました。もともと、宿場名「大宮」の由来は、当地にある氷川神社から来ていますから、梅の故事とは無関係ですが…。なお、標題も梅の枝で囲まれています。
Kom05 さて、梅の花の形をした枠に描かれたコマ絵の分析が問題です。注目すべきは、当該国芳作品の全コマ絵の内、唯一雨が降っている情景だということです。梅の故事と言えば、菅原道真が有名で、雷神と化した道真が北野天満宮に祀られたことを思い起こすと、その雷雨なのかもしれませんが、副題に菅原道真の名がないことから、この考えは少しばかり強引です。
まず、描かれた場所を先に解決しましょう。国芳のコマ絵の「大宮」は、一つ飛ばして、大宮から上尾に行く途中の加茂神社を画題に選んだ英泉・広重版木曽街道の「上尾」と比較することになりますが、そうすると、国芳のコマ絵に小さく見える鳥居は加茂神社の鳥居でしょうか?たぶん、それは間違いでしょう。なぜならば、既述したように、大宮は武蔵野国の一宮で、全国に勧請される氷川神社の総社のある所なのです。国芳のコマ絵は、『木曽路名所図会』巻之四の図版で確認すると、木曽街道から氷川神社への入り口・一の鳥居辺りの風景であると推認されます。
とすると、唯一雨が降る情景となっている氷川神社のコマ絵の理由は、この神社がもともとは池の畔にあった水神であったことと係わっているのかもしれません。また、梅の故事に因んで梅の花模様をした枠の中に降る雨、つまり、梅雨という語呂合わせになっている可能性もあります。しかも、それだけではなく、おそらく、浦和の団七の「水被り」場面と氷川神社の「雨降り」とを一対にした相似的表現を狙ったのではないでしょうか。
宮の越 大塔宮

卅七 宮の越 大塔宮
版元:住吉屋政五郎 年代:嘉永5(1852)年5月 彫師:須川千之助、大久
Kn37 「大塔(おおとう・だいとう)宮」とは、後醍醐天皇の皇子、護良(もりよし・もりなが)親王のことです。後醍醐天皇の意向を受けて、二度にわたり天台座主となっています。大塔宮は、元弘の乱(元弘元・1331年)に際し、還俗して鎌倉幕府討幕運動に参戦し、反幕勢力を募り、京都の六波羅探題を滅ぼしました。幕府滅亡後の建武の新政では、征夷大将軍に任じられましたが、足利尊氏と対立し、皇位簒奪を企てたとして捕らえられ、鎌倉に送られて、尊氏の弟足利直義の監視下に置かれました。翌年、北条時行の中先代の乱が起き、警戒した直義の命を受けた家臣淵辺義博に殺害されました。
『太平記』によれば、東光寺の土で壁を固めた牢に閉じ込められ(土牢は鎌倉宮敷地内に復元・現存)、淵辺義博に殺された護良親王は、公家の藤原保藤の娘、南方に弔われたと伝えられています。その悲劇は、人形浄瑠璃や歌舞伎にも採り入れられ、享保8(1723)年2月、竹田出雲・松田和吉(文耕堂)作・近松門左衛門添削『大塔宮曦鎧』(おおとうのみやあさひのよろい)、通称『身替り音頭』(みがわりおんど)として大坂竹本座で初演されています。
国芳作品は、土牢に閉じこめられた大塔宮が読経し、淵辺が襲おうとしている様子を描いています。宮の傍らにいるのは、南方でしょうか。標題は、敷地を覆う松に囲まれています。「土牢に残された大塔宮」→「宮残し」→「宮の越」という地口と判ぜられます。
ところで、淵辺の着物には(織田)木瓜紋が入っています。一見、『太平記』の大塔宮を画題としているように装いながら、「藪原」の明智光秀と対応させて、本能寺の変で光秀に殺害された織田信長を描いていると解しうるのです。とすると、天台座主であった大塔宮は、信長に焼き討ちにあった延暦寺を象徴することになります。「藪原」でも触れましたが、「宮の越」との二枚組は、延暦寺の焼き討ち、本能寺の変、山崎合戦を含意していて、かなり危険ながらも痛快な作品ではないでしょうか。ちなみに、版元は住吉屋政五郎、彫師は(須川)千之助です。『役者木曽街道』の「シタ売」作品の謎は、これで解けたように思います。
Kom37 さて、コマ絵の形ですが、宮を弔った藤原家の娘・南方に因んで、藤原家の「下り藤」の紋ではないでしょうか。公家の代表紋です。「上り藤」とする見解もありますが、デザインが相違しています。描かれているのは、鳥居峠辺りから見た木曽御嶽山の近影です。
上尾 三浦の高雄
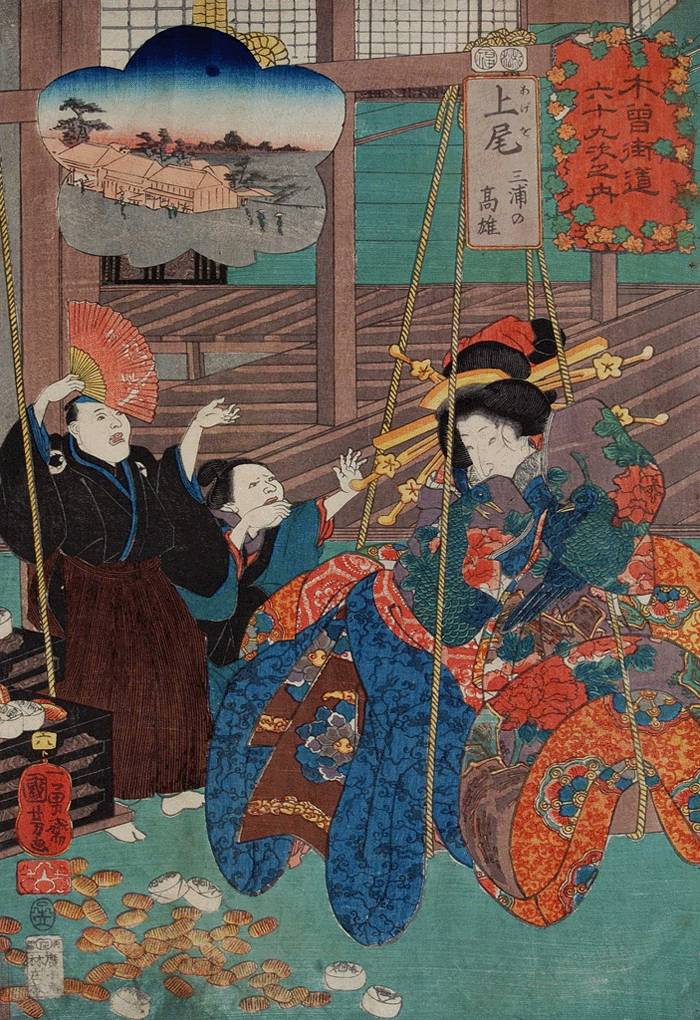
六 上尾 三浦の高雄
版元:林屋庄五郎 年代:嘉永5(1852)年6月
Kn06 「高雄」(高尾)とは、吉原遊女の最高峰の一人、三浦屋の高尾太夫のことで、その名は代々受け継がれていて、ここでは二代高尾、俗に仙台高尾と呼ばれる女性を指しています。当シリーズ「日本橋」で登場した足利頼兼(伊達綱宗)が身請けしようとした遊女のことです。国芳は、頼兼が高尾をその体重と同じ重さの黄金で身請けしたという伝説を画題としていて、天井より吊された天秤棒の片方に高尾が載り、反対側に小判がこぼれた複数の千両箱が見えています。高尾は着物を何枚も重ね着し、振り袖や着物の中に小物などいくつも隠して重くしたとも言われています。傍らに描かれる三浦屋の主人夫婦の表情からも読みとれますが、二人の欲張った策略でしょう。小判で吊り「上」げられた高「尾」ということから、「上尾」に掛けられています。一方で、高尾は紅葉の名所で、その名所の高尾に因んで標題は紅葉で囲まれています。
Kom06 同じく、コマ絵の枠も紅葉の形に切り取られています。そのコマ絵を見ると立場茶屋風の建物が何軒か続き、この構造は、英泉・広重版木曽街道の「上尾」の風景と同じように感じられます。英泉・広重版の「上尾」は、『木曽路名所図会』巻之四に紹介ある、大宮から上尾に至る途中の加茂村(社)の農家と立場茶屋を描いていました。情景に特徴がないので、コマ絵を上尾の宿場そのものとしても良いのですが、英泉・広重版の先行作を尊重して立場茶屋風景としておきます。多くの場合、国芳のコマ絵は、英泉・広重版木曽街道を意識しています。
長窪 お七 吉三
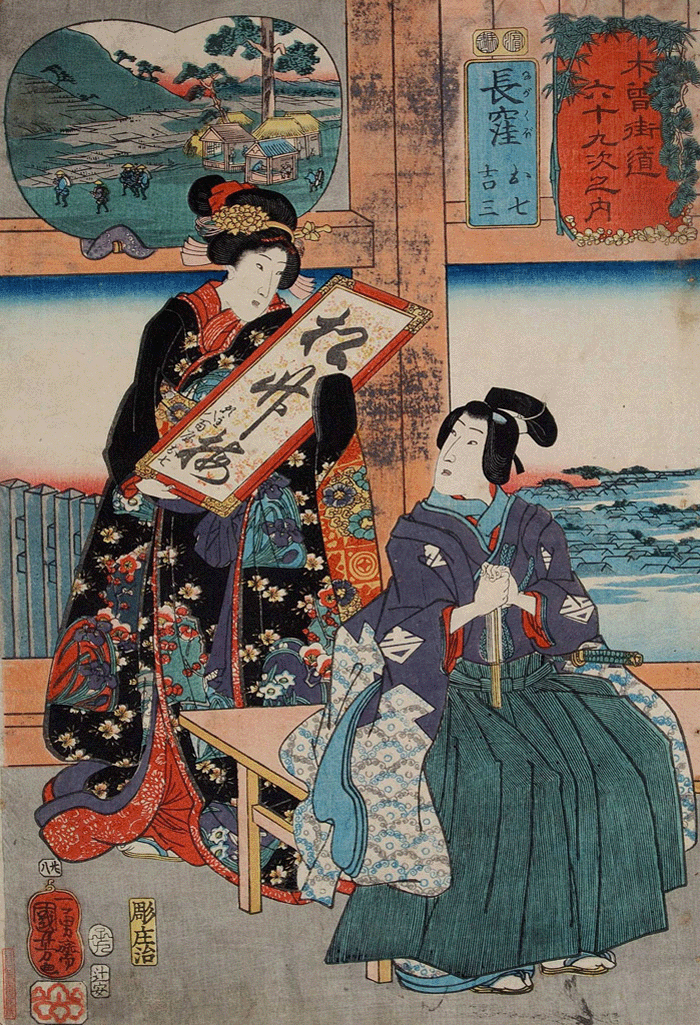
廾八 長窪 お七 吉三
版元:辻屋安兵衛 年代:嘉永5(1852)年9月 彫師:彫庄治
Kn28 人形浄瑠璃、歌舞伎に、『お七吉三物』(おしちきちさもの)、あるいは『八百屋お七物』と呼ばれる一系統があります。天和3(1683)年の春に放火の罪で火刑に処せられた江戸本郷の八百屋の娘お七を題材にした作品の総称です。火事になれば、寺小姓吉三郎に会えるという恋のために無分別へと走る町娘の純情さに焦点が合わされたもので、井原西鶴の小説『好色五人女』(貞享3・1686年)などを通して一般に流布し、宝永3(1706)年1月大坂嵐三右衛門座『お七歌祭文』で歌舞伎狂言化されています( 『カブキ101物語』206頁参照)。
国芳作品は、お七が「松竹梅」の掛額を湯島天神に奉納した場面を絵にしています。この掛額にお七の本当の年齢が記されていたことから、当時16歳での刑事責任を免れず、鈴が森にて火炙りの刑を受けることとなるのです。標題の周りも、この松竹梅で飾られています。ところで、「長窪」と「お七」との関係はどこにあるのでしょうか。帯の結び方に、「お七結び」というものがあります。江戸時代の商家の娘などが結んだ帯結びで、特徴は、帯枕なしで、帯を長く垂らした様式です。国芳作品のお七を見ると、帯が長く垂れています。ここを取って、「長く垂れた帯」→「長くお(び)」→「長窪」ということではないでしょうか?
Kom28 コマ絵は、湯島天神の扁額をそのまま利用した形式になっていますが、その扁額は団扇のような形に見えます。この形が、「お七髷」とも言われた、江戸時代の町方娘の髪型桃割れ、桃の意匠であったら、さらに面白いのですけれど…。そこに描かれた風景は、英泉・広重版木曽街道の「長久保」が明月と橋を渡る旅人の情景としていましたが、当コマ絵では、橋を渡って街道から、長久保を特徴づける中山方向を描いたものと考えられます。
美江寺 紅葉狩
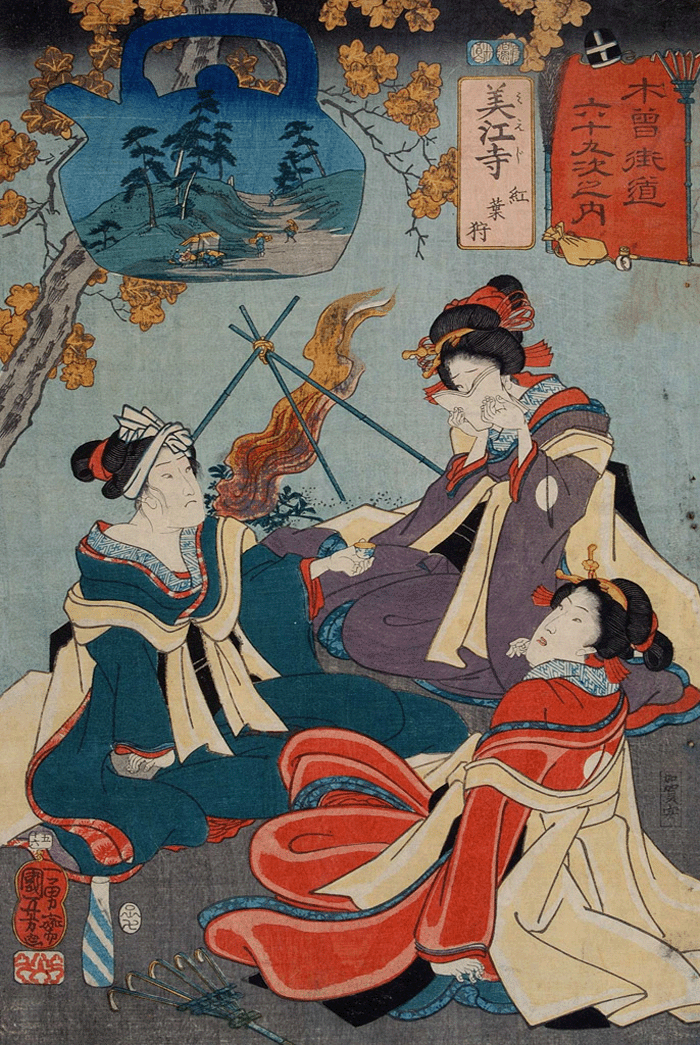
五十六 美江寺 紅葉狩
版元:加賀屋安兵衛 年代:嘉永5(1852)年7月
Kn56 「紅葉狩」とくれば、鬼女紅葉の伝説や物語を想像します。しかし、ここに描かれる「紅葉狩」は作品を見ると「怒り上戸、泣き上戸、笑い上戸」の三人が登場していることから、浄瑠璃・歌舞伎などの『源平布引滝』四段目の「紅葉山」であることが判ります(『カブキ101物語』90頁参照)。
平治の乱で平清盛に源義朝が破れ、さらに後白河院が鳥羽殿に押し込められた中、源氏ゆかりの多田蔵人行綱が平氏の動きを探るため館の奥に潜んだところ、その庭で、平次、又五郎、藤作の三人の仕丁が、紅葉を焚いて暖をとり酒盛りをしていました。そして、この三人が怒り上戸、泣き上戸、笑い上戸という性格で笑いの一幕を演じます。通例、「三人仕丁」「三人生酔」(さんにんなまよい)と呼ばれます。国芳の当該シリーズの「目録」には、「三人生酔」と記されています。国芳は、おそらく、宿場名「美江寺」に掛けて、「三衛士」(みえじ)=「三人の仕丁」ということから、「三人仕丁」の場面を画題としたと考えられます。また、「美江寺」の「美」から美人仕立てともなったのでしょう。もともとは、『平家物語 巻之六』「紅葉」に高倉天皇とその仕丁の話として書かれているものです。標題の周りは、仕丁の烏帽子、竹箒、熊手、煙管等、紅葉狩の場面での道具で囲まれています。
Kom56 紅葉に重ねて描かれるコマ絵の形は、焚いた紅葉で酒を燗することから、その銚子でしょうか。全体図の左隅に徳利があります。英泉・広重版木曽街道の「みゑじ」は、宿場西の犀川川岸の低地の風光を描いていますが、コマ絵は、輪中堤上を歩む旅人の情景ではないでしょうか。そこから、川岸に下ると英泉・広重版の「みゑじ」の景色になるという理解です。『木曽路名所図会 巻之二』の図版「河渡川」の背景「糸貫川」(本田村)あるいは「呂久川(杭瀬川)」の対岸に、コマ絵に近い風景を見つけることができます。なお、前掲「河渡」のコマ絵の風景と似ていますが、古代東山道と条里跡が残った、この辺り一帯の共通景色だと理解されます。
今須 曾我兄弟

六十 今須 曾我兄弟
版元:辻岡屋文助 年代:嘉永5(1852)年6月 彫師:上村安
Kn60 作品を眺めると、曾我五郎時致が蚊帳の中で寝ている人物(工藤祐経)を伺い、背後の曾我十郎祐成に何か合図を送っているようです。敵が「居ます」ということで、「今須」に掛けられているのです。この後、兄弟は祐経を眠りから起こして仇を討つことになります。もちろん、『曾我物語』を下敷きにした作品です。事件の発端は、作品二十五「八幡」を参照。この作品は、単なる地口からのみ成立したのではなくて、「今須」が「寝物語の里」という伝説を持っていることから、寝ている祐経を討つ場面が描かれています。ちなみに、「寝物語の里」と言われるのは、今須が近江と美濃境界にある宿場で、建物の距離僅か一尺五寸の近離距故に、寝ながらにして両国の者が物語りできることが所以となっています。標題は、五郎の着物の紋様の蝶々と十郎の着物の紋様の千鳥で囲まれています。いずれも、お目出度い意匠です。
Kom60 工藤家の紋・庵木瓜に重ねられたコマ絵は、一つは蝶々であることが判ります。さらにその右下に千鳥が重ねられ、曾我兄弟を表す工夫があるのだと思われます。英泉・広重版木曽街道の「今須」は、「江濃両国境」の榜示杭を近江側から眺める構図です。コマ絵は、『木曽路名所図会』巻之二の俯瞰図「寝物語の里」を参考に、宿場を見下ろす地点から描いているようです。
細久手 堀越大領
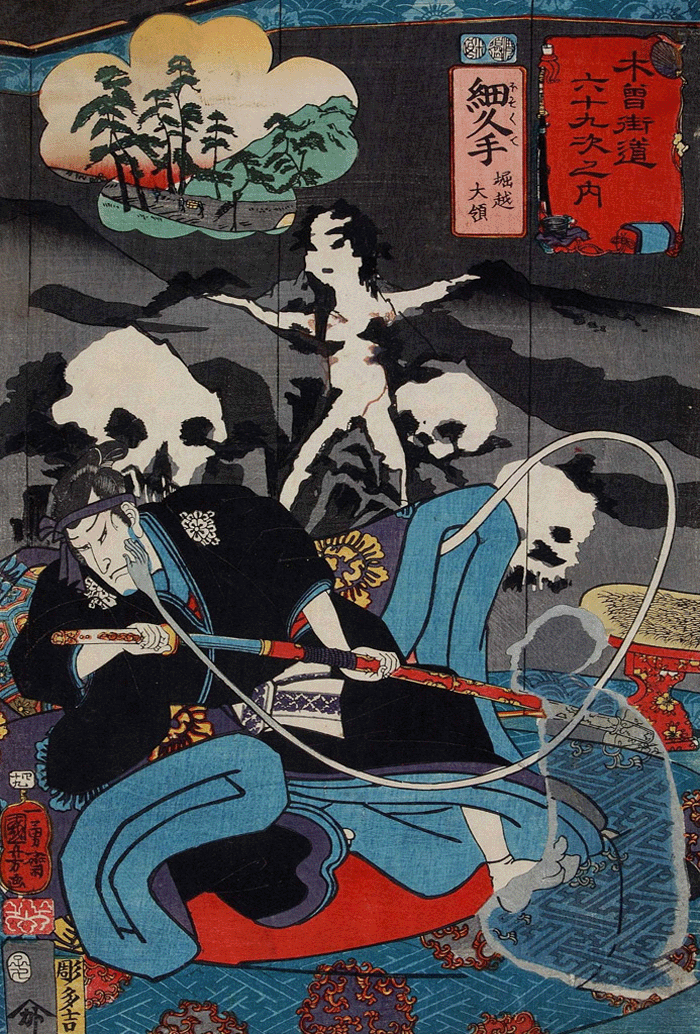
四十九 細久手 堀越大領
版元:八幡屋作次郎 年代:嘉永5(1852)年7月 彫師:多吉
Kn49 「堀越大領」は、嘉永4(1851)年8月江戸中村座初演の『東山桜荘子』(ひがしやまさくらそうし)に登場する、悪政を行う大領のことです。元になった講釈の『佐倉義民伝』では「堀田正信」と呼ばれ、歌舞伎では、「織越大領」とされています。その内容は、農民を扱った異色のもので、下総佐倉の織越大領の悪政に対して、名主・浅倉当吾(佐倉宗五郎)が将軍足利義政(徳川家綱)に直訴したところ、当吾夫婦は捕らえられ拷問に逢い、三人の子も斬殺されてしまいます。それ故、当吾が怨霊となって織越に祟るという怪異譚へと進みます。
国芳の作品では、病鉢巻をしているのが織越大領です。その背後の屏風には、三つの髑髏と磔にされた人物が浮かび上がっています。また、手前右には、透明化された人物が座っていますが、これが当吾の怨霊と思われます。蒲団の端から細長く手が伸びて、織越をいたぶっています。この「細長く手」が伸びるから、「細久手」となります。標題は、この怨霊の場面を象徴する、手燭、刀、水桶、枕、団扇などで囲まれています。
Kom49 コマ絵の形は、『東山桜荘子』の「堀越大領」ということで、桜を意匠するものです。大領の着物の紋様と同じです。この桜は、もちろん、下総佐倉を暗喩するものです。そこに描かれる風景ですが、英泉・広重版木曽街道の「細久手」は、宿場手前の入口門のように見える女男松と思われます。これに対して、国芳作品のコマ絵は、同じ場所を遠くから俯瞰するようにも見えるのですが、いささかか情景が異なっています。この辺りの一番の名所は『木曽路名所図会 巻之二』によれば「琵琶峠」で、掲載される図版を参照すると共通する風景とも考えられます。ここからは、御嶽、白山、伊吹山が眺望できました。
なお、作品四十八と四十九の二枚で組みとなって、怪奇譚仕立てとなっています。因果応報、怨霊信仰の世界が前提です。
望月 怪童丸

廾六 望月 怪童丸
版元:林屋庄五郎 年代:嘉永5(1852)年6月 彫師:彫竹
Kn26 前掲「十七 松井田」に登場する「山姥」は山の神(神霊)の象徴でした。他方で、怪童丸、すなわち、金太郎の母という説話の一類型があって、本作品もこの後者の例です。正徳2(1712)年初演、近松門左衛門の『嫗山姥』(こもちやまんば)など、人形浄瑠璃・歌舞伎を通して、足柄山での怪力の童子・金太郎、あるいは、酒呑童子を退治する源頼光の四天王・坂田金時等のイメージが定着してきました。
本作品は、猿と兔をお供にトリモチで烏天狗を取っている怪童丸を描いて、「トリモチに着く」、もしくは「トリモチで突く」から、「もちつく」→「望月」(もちづき)と洒落ているのでしょう。傍らの猿はざる篭を持ち、兔は怪童丸の着物を羽織っています。また裸の怪童丸の赤い肌が露出しているのは、その神童としての性格、神性を強調するものです。それ故、捕獲する鳥も、普通のそれではなくて、深山に棲む烏天狗なのです。標題の周りは、腹掛け、春駒、でんでん太鼓、風車、兔車など子供の玩具で飾られています。
Kom26 コマ絵の形は、マサカリ担いだ金太郎というわけで、マサカリです。コマ絵内の風景ですが、「塩名田」と「八幡」の山は、流れ山か浅間外輪山の同じ山並みと思われるのですが、「松井田」の山もそうでしょうか。この辺りの風景の中心は、浅間山ですから確率の高い思考です。
『木曽路名所図会』巻之四の「望月」には、「八幡」に向かう上り坂として「瓜生坂」の紹介があります。英泉・広重版木曽街道の「望月」が同「瓜生坂」を描いた可能性は、背後に見える山が浅間山ではなくて蓼科山であるならば、十分にありえます。なお、同坂には松並木がないということですが、同名所図会の図版「望月駅」を参照したとするならば、松の繁る絵があるので、このような情景も不思議ではありません。「瓜生坂」を前提とすると、国芳作品の山も蓼科山となりましょう。
松井田 山姥 松井民次郎

十七 松井田 山姥 松井民次郎
版元:辻岡屋文助 年代:嘉永5(1852)年6月
Kn17 「山姥」や「松井民次郎」に関する資料は多寡は別として存在しますが、ここでは国芳の考案の元となった資料から直接作品の解説を試みてみます。それは、国芳『本朝劔道略傅 松井冨次郎茂仲』(天保14・1843年から弘化4・1847年)の詞書きです。
すなわち、「幼稚時異人に倡(いざな)ハれ劔法を学びその後父の家に皈(かへ)り日夜学問執行なし暮せしに故あつて兄を何某に討れ其仇を尋んと所々方々廻りありき或時人も通ハぬ山中に分入このやま越にたどり行かバいづれへかむかふべし行て見むやと只一人道もなき山越にて日もはややう/\西にかたむきしころ一ツのながれに出たりしが何心なく此川をわたりしニ此方の岸なる草深き所より数千の蛇一群となりむかふの岸へわたりいづくともなくさりけれバふしぎと見るうち年の頃三十ばかりなる女忽然と来りて云たるハ今蛇の川を渡りたるハきのふ降たる雨に川水ましたれバ蛇疑ひて集り居たるが今御身の渡たまひしをみて夫をたよりに渡りしなりと語るこれ仙女にして冨次郎にさまざまの薬を与へ身の行末を教へ立去たる此後彼薬を服して大蛇をうち其毒氣を遁れしとぞ誠に名誉の達人と云つべし」というものです。
当資料に従えば、国芳作品にある「山姥」とは、「仙女」のことであることが判ります。傍らの猿に話しかけるような山姥の表現は、幼少時、「異人に倡(いざな)ハれ」た民次郎に因んで西洋異国風に描かれていて、銅版画挿絵からの学習の結果を国芳が披露したものとも言えましょう。国芳の全体図は、先行する作品の詞書きにある状況をそのまま絵にしていますが、それは、宿場名「松井田」から「松井民次郎」を連想してのことです。標題は、山中の草々(シダ)に覆われています。
Kom17 さて、コマ絵の形は、縁起のよい櫛松(くしまつ)紋を意匠したものと推測されます。山姥がその髪を梳かす櫛に松井民次郎の松とを重ねて櫛松紋となっていると見ています。中に描かれるのは、英泉・広重版木曽街道の「松井田」丸山坂辺りの風景と同様と思われます。遠方に小さく見えるのが、碓氷峠でしょうか。ひょっとすると、さらに先の、横川の関所を望む情景かもしれません(『役者木曽街道』「松井田 横川 關守兵藤」参照)。
三戸野 美止野小太郎

四十二 三戸野 美止野小太郎
版元:湊屋小兵衛 年代:嘉永5(1852)年6月 彫師:朝仙
Kn42 地名の「三戸野」に掛けて、「美止野小太郎」を画題としていますが、江戸中村座・嘉永4(1851)年4月の歌舞伎『世界花小栗外伝』などでは、漁師浪七実は「美戸小太郎」と呼ばれています。外題からも判るように、小栗判官と照手姫を主人公とする、小林繁作・葛飾北斎画の読本『小栗外伝』(文化10・1813年)から生まれ、人形浄瑠璃・歌舞伎に導入された話が、当該作品制作の動機になっていると思われます。(小栗判官と照手姫については、『東海道名所図会』の説明が引用された、歌川国芳『東海道五十三對 藤澤』の詞書きを参照。)なお、作品番号について、平木浮世絵美術館所蔵は「四十一」、中山道広重美術館所蔵は「四十二」となっています。前者を前提にするならば作品番号四十一は、四十二の誤りです。後者を前提にするならば、訂正の必要はありませんが、後者は墨で書き加えられているように見えます。制作数から判断しても、後摺で訂正した可能性は少ないように思います。
「美止野小太郎」は、平木浮世絵美術館資料によれば、小栗判官の家臣で、照手姫を東国に送る途中、追っ手と戦い姫とはぐれてしまい、下総那須原に至ります。古寺に一夜の宿を求めたところ、そこは山賊達の住処で、小太郎はそれらの山賊を一人で退治します。国芳作品は、古寺で賊達と斬り合っている場面を描き、山賊が化けていた鬼の面が背後に見えます。標題の周りは、古寺の仏具と山賊の道具で囲まれています。
Kom42 コマ絵は、古寺の木魚の意匠です。三留野から野尻の間は、『木曽路名所図会』巻之三には、木曽の桟と言われる、切り立った崖を渡る難路が続くとありますが、英泉・広重版木曽街道の「三渡野」は、木曽川両岸に展開していたのどかな田園風景を描いています。コマ絵も同様の趣向で宿場周辺を遠望していると思われます。次の「妻籠」と同様、北から南方向をを見ています。
草津 冠者義髙
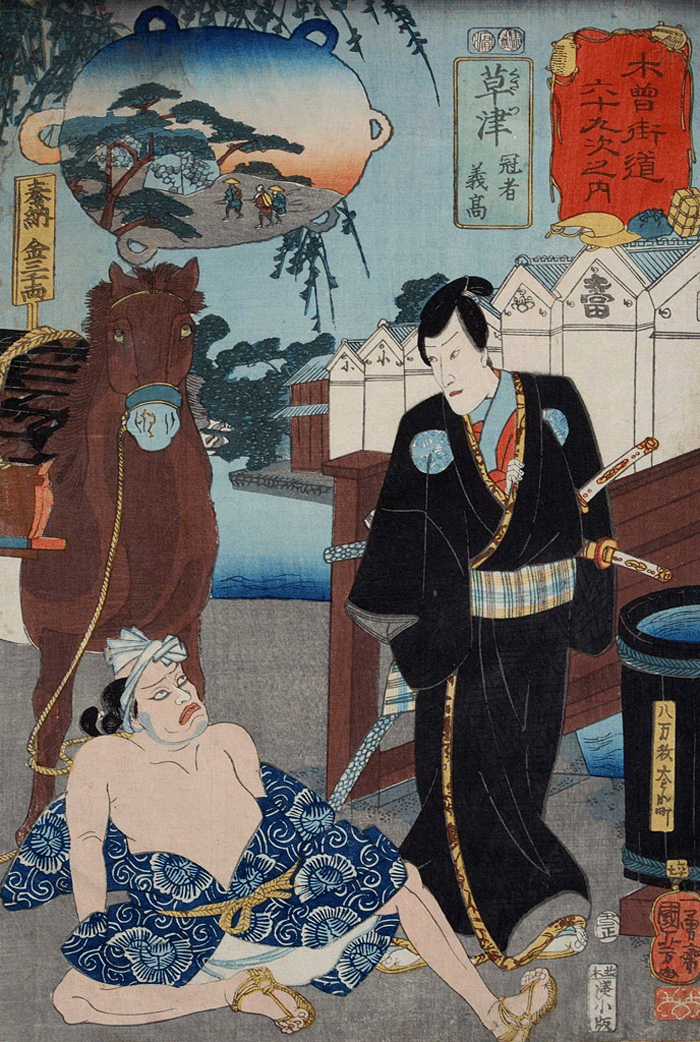
六十九 草津 冠者義髙
版元:湊屋小兵衛 年代:嘉永6(1853)年1月
Kn69 「冠者義髙」と言えば、清水の冠者義髙という人物がいます。木曽義仲の嫡男で、義仲と源頼朝との対立後、頼朝の長女・大姫の婿という名目で鎌倉へ下り、人質になった人物です。
ところが、国芳が画題としているのは、嘉永6(1853)年正月中村座初演の歌舞伎『襷廓三升伊達染』(こぞってみますくるわのだてぞめ)の「馬斬り」の場面だと判ります。三代豊国にもほぼ同じ場面を描く二枚続の役者絵があります。これらは、『太閤記』を世界とする狂言を題材にしたもので、懐手の侍は、小田春永(織田信長)の子・三七郎義孝(織田信孝)で、義孝は真柴久吉(羽柴秀吉)が高野山に納める祠堂金三千両を積んだ馬を堺の大和橋で襲い、馬士を切り捨て金を奪います。そこに捕手が駆けつけるのですが、義孝との名を聞いて一同平伏し、義孝は悠々馬を引いて立ち去るという結末です。「冠者義髙」とは、三七郎義孝(信孝)と考えるべきです。なお、作品番号六十七は、六十九の誤りです。
三七郎義孝(頼孝とも呼ばれます)は八代目市川団十郎、馬士の八蔵は中村鶴蔵の役者絵で、このシリーズでは唯一でしょうか、はっきりと役者の似顔絵となっています。国芳の当該木曽街道シリーズが役者絵を基本に据えているという、当講座の見解を証明するものだと思われます。背後の蔵には、「大當」の文字の他に、版元湊屋、絵師国芳の意匠が入っています。また、標題は、草鞋などの馬士(馬子)支度で囲まれています。
さて、宿場名「草津」がどうして「冠者義髙」と繋がるのでしょうか。当該シリーズの「目録」を見ると「草津 馬士の八蔵」と記され、国芳は、「冠者義髙」に斬られる「馬士の八蔵」の方に注意を促しています。とすると、「草津(追分)」→「馬子の追分節」→「馬士(馬子)の八蔵」という迂遠な繋がりが答えとなるのでしょう。ちなみに、追分節は木曽街道の「追分」がその発祥です。
Kom69 コマ絵の形は、既述した「馬斬り」の場面に掛けて、馬士の草鞋です。英泉・広重版木曽街道の「草津追分」は、天井川である草津川を北側から追分の常夜灯方向を望む情景を描いています。これに対して、国芳のコマ絵は石垣が二つ見えています。おそらく、草津の宿場の入り口にあった見附のイメージではないかと思われます。名所旧跡は多いにもかかわらず、「守山」「草津」と急に風景が曖昧になってきたように感じられます。
沓掛 黄石公 張良
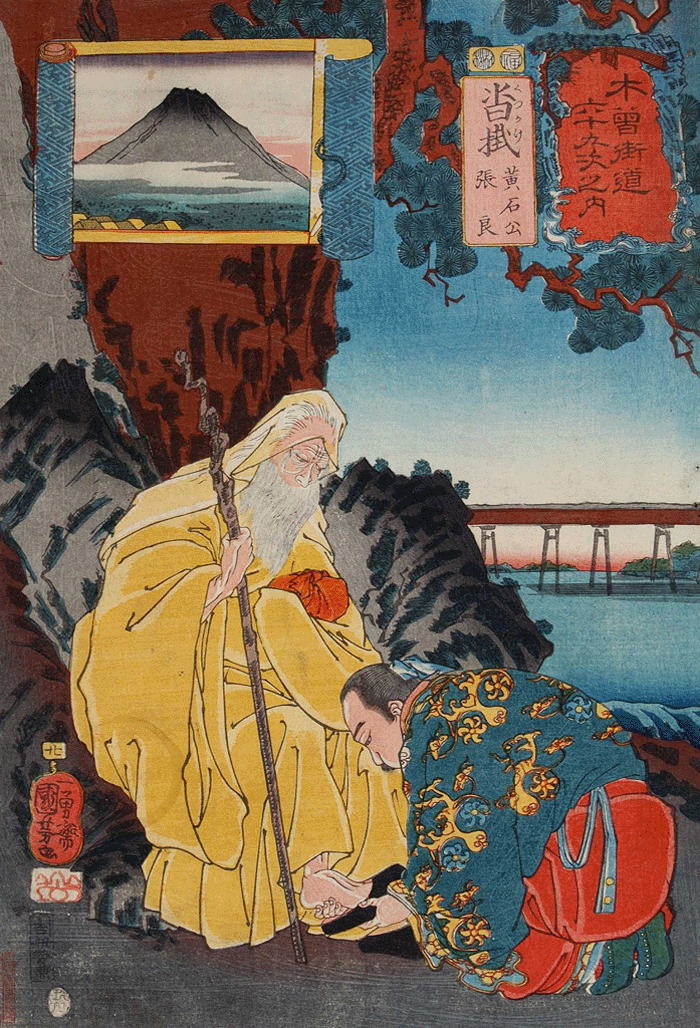
廾 沓掛 黄石公 張良
版元:伊勢屋兼吉 年代:嘉永5(1852)年6月
Kn20 黄石公(こうせきこう、生没年未詳)は、秦代中国の隠士。張良に兵書を与えたという伝説で名高い人物です。すなわち、張良が始皇帝を暗殺しようとして失敗し身を隠していたある時、一人の老人(黄石公)と出会い、その老人は沓を橋の下に落として、袂を歩いていた張良に「拾え」と命じました。三度試されましたが、張良が怒らずそれに従ったことから、その謙虚さに応じて、老人は張良に「太公望兵書(六韜)」を与えたというものです。張良は、後の漢の皇帝劉邦の謀臣となって、軍師の名を高めることになります。なお、黄石公は太公望とともに兵法の祖として仰がれ、その名を冠した兵法書の種類は多く、その中でも『三略』が有名です。
国芳作品は、謡曲「張良」に従っていると言われています(中山道広重美術館資料)。画中背後の土橋が、黄石公と張良の出会った橋です。また、老人が抱える赤い布に包まれているのが兵書でしょうか。なお、「沓を履く」あるいは「沓を履け」から「沓掛」と洒落ているように思われます。標題は、土橋の下の岩場とそこを流れる川の波濤のようです。
Kom20 コマ絵は兵書の巻物(まきもの)の形を意匠したものです。コマ絵の中の風景は、浅間山です。英泉・広重版木曽街道の「沓掛」ではなく、次の宿場「追分」の「浅間山眺望」に対応しています。軽井沢より信州に入っていることを考えると、名高き浅間山の登場を前倒ししたということでしょう。
醒ヶ井 金井谷五郎

版元:辻岡屋文助 年代:嘉永5(1852)年6月
「金井谷五郎」は、当該シリーズでは、松井田の「松井民次郎」、塩尻の「髙木虎之介」、それ以外では「宮本武蔵」などと同じく、
読本などの登場人物として採り上げられる武芸者の一人です。金井谷五郎が慶安4(1651)年の由井正雪による幕府転覆の陰謀に加担し、
後に自害したことを受けて、浮世絵や物語の世界で活躍させられています(怨霊信仰)。いわゆる『慶安太平記物』の中では、たとえば、
安永9(1780)年1月、江戸外記座初演『碁太平記白石噺』(ごたいへいきしろいしばなし)において、宮城野信夫の仇討話に絡んで別筋と
して登場します。海鮫を退治した「髙木虎之介」に塩尻で鯨を持ってきたように、宮本武蔵が山鮫を退治する作品がある中、画中で「金井
谷五郎」に山「鮫」を退治させています。これは、宿場名「醒ヶ井」に繋げるためのやや強引な便法です。標題の周りは、武者修行の道具
で囲まれています。
コマ絵の形は、武者修行者ということで、刀の鍔の意匠です。英泉・広重版木曽街道の「酔ヶ井」は、宿場の西外れの実景ですが、国芳の
コマ絵は、『木曽路名所図会』巻之一の「醒井(日本武尊居醒清水 腰懸石)」の図版を参照したと見え、「三水四石」を包括する「醒ヶ井」
の宿場全体の風光です。コマ絵を拡大すると槍のようなものが二本見えるので、視点は違いますが、英泉・広重版の槍を持つ二人の中間が
いるのと同様な情景を描いているのかもしれません。



みかけハこハゐが とんだいゝ人だ


相馬の古内裏