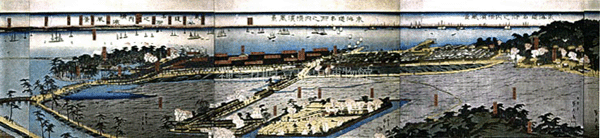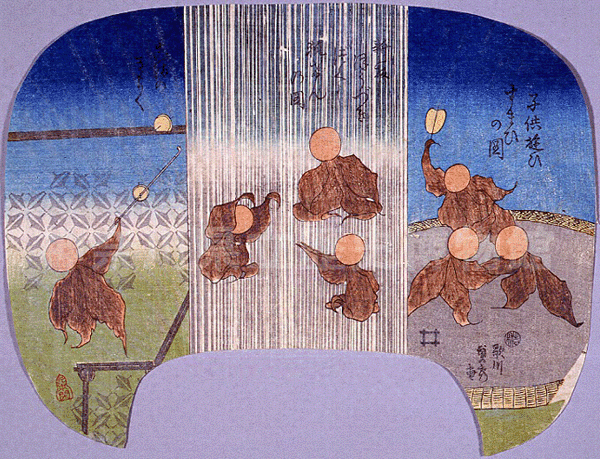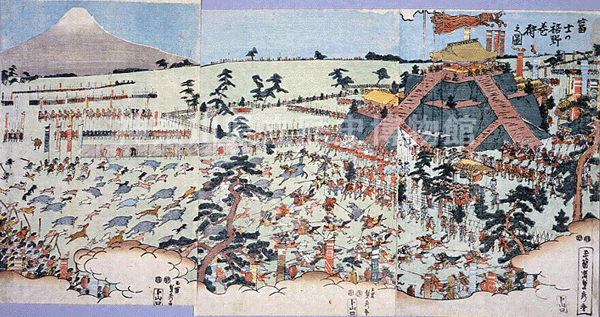蒲原
忠臣蔵義士本望の図 チュウシングラギシホンモウノズ 制作年代 天保末期(1840-43) サイズ (大判横3枚) 作者名/落款 五雲亭貞秀 解説 忠臣蔵は歌舞伎芝居にもたびたび上演され、浮世絵としても多くの絵師が手掛けている。貞秀もこのような作品を初めは多く描いていて、忠臣蔵も複数制作している。本図は討入を果たしたあとの場面で一種の風景画でもある。ここでは西洋画の遠近法だけではなく陰影をつけて立体感を出し、貞秀の個性が画面にでている。 富士の裾野巻狩之図 フジスソノマキガリノズ 制作年代 弘化4年(1847)頃 サイズ (大判横3枚) 作者名/落款 五雲亭貞秀 解説 貞秀の作品の特徴は幾何学的な事物の表現にある。それは線描としての直線、形態としては三角や四角に還元できる事物、特に群像としての人間の表現に多くある。弘化四年頃の作と見られる本図は頼朝の巻狩りを描いて、狩りをする人物や獲物の猪や鹿などかなり単純化されて空間を走り回る。また狩場の建物も幾何学的である。 日本八景づくし乃内 近江八景 ニホンハッケイヅクシノウチ オウミハッケイ 制作年代 天保(1830ー43)中期 サイズ (大判横3枚) 作者名/落款 五雲亭貞秀 解説 八景の名称は「比良暮雪」「堅田落雁」「唐崎夜雨」「三井晩鐘」「粟津晴嵐」「石山秋月」「瀬田夕照」「矢橋帰帆」である。本図は風景画が独立した浮世絵のジャンルとして認められて間もない頃の作である。構図は琵琶湖周辺の光景を少し俯瞰的な視点で描いている。まだのちの遠近感のある表現には乏しい。 新板ほうづきづくし シンパンホウヅキヅクシ 制作年代 弘化(1844-7)初期 サイズ (団扇絵1枚) 作者名/落款 五雲亭貞秀 解説 団扇絵に描かれたほうづきの戯画、ほうづきの袋は剥かれて手足となり、実は頭となり戯人化される。そのほうづきが縦横に人として動き回る。ここでは相撲などが取り上げられている。こうしたユーモア溢れる作は貞秀としては珍しい。このアイデアは一勇斎国芳の評判となった「ほうづきつくし」を参考にしているようだ。 東海道名所之内 横浜風景 トウカイドウメイショノウチ ヨコハマフウケイ 制作年代 万延元年(1860) サイズ (大判横8枚) 作者名/落款 五雲亭貞秀 解説 本図は横浜の中心部だけではなくその周辺も視野にいれ、3メーター近い大画面に描いている。右から本牧の鼻や十二天の森、北方村、増徳院、外国人の居留地や港の中心部、港崎遊廓、さらに弁天社、野毛、伊勢山、そして東海道へと続く芝生から湾曲させて、新町、子安に至る地域までを捉える。背後には富士山が象徴的に入る。